この小説は純粋な小説です。
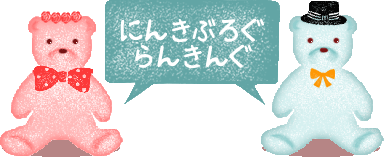
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
「お帰りなさいませ
海斗様」
「お帰りなさいませ」
とっぷりと暮れた夕食時、
勝手口からきらびやかに若き鷲たちが入来した。
鷲羽海斗の長身が敷居を越える。
女衆はそれぞれにに長の戻りを迎えては
小腰を屈めていく。
「いいにおーーい」
「鷲羽のご飯だ、
最高さ。」
続いて響いた愛らしい声に
一同の笑みが溢れる。
鷲羽がいただく巫が
屋敷一番の信を受ける客分、高遠に寄り添われて
ぴょんと敷居を越えてきた。
ゆったりと続く高遠は、
敷居を越えて足を止め頭を下げる。
いつしか、
瑞月の友人として、
という以上に、
鷲羽の老人の客分という顔がしっくりとする高遠だった。
自慢の竈には、
一粒一粒が誇らしく輝く白米が炊き上がっている。
次々と白米が櫃に盛られ
広敷に運ばれていく。
広敷ではもう夕餉は賑やかに始まっている。
そろそろ遅番の面々が食事を終え、
日勤の者が食事を始める頃合いだ。
食は鷲羽の魂。
みなが同じ菜に舌鼓を打ち、
晴れの時も褻の時も、
それを共に生きる。
煮炊きする土間、
上がって横に皆が集う広敷、
囲炉裏を囲む当主の家族は、
そのどちらにもぴったりと寄り添って食事をとる。
初夏の今、
囲炉裏のある板敷から、
一段高く広がる青畳に座は移ったが
その精神は同じだ。
この座については、
GWを終えたつい先日、
席替えが断行されたばかりだ。
鷲羽海斗が最奥、
一同を見渡す家長の座に着く。
女衆の目が届く土間近くに
すとんと瑞月が座り、
高遠も座る。
何だ当たり前じゃないか?
もちろん家長が家長の座につく。
もちろん当たり前だ。
ただ、
長たる海斗がそれを承服しきれていないところが、
ブスブスと燃え残る火種となりやすい。
そして、
その人物は
この頃遅刻が多い。
それもGWを経ての変化の一つだ。
「………遅いぞ じじい」
海斗が
ぼそっとつぶやく。
廊下の奥の灯りが
ぐっと明るくなった。
微かなざわめきが聞こえるな
と
思うや
それは妙に可愛らしい老人の声と
保母さんを務める女衆の、
のんびりと
開けっ広げな
海斗の渋面を思うと
空気を読まぬ賑やかさが、
とろとろと近づいてくる。
食事の場と定まった囲炉裏の間にある
たいそう立派な大黒柱を、
猫の黒が、
するりと優雅に尻尾を立てて
回ってくる。
背後の一行とは一線を画し、
囲炉裏の間に
御入来だ。
珍しく苛立ちも露に眉をひそめている海斗を
ふふーんと一瞥し、
土間へと進む。
「黒ちゃん 黒ちゃん」
と
無邪気に身を乗り出す瑞月の手に頭を擦り付けてやり、
咲が設えた黒専用の膳に向かう。
そして、
能天気な一行は、
広々とした囲炉裏を囲む板敷きの間の敷居で解散する。
女衆は広敷へと向かい、
食事を取るのだ。
保母も食事は必要だ。
次の保育所の入り口で
老園児は
大好きな強面のお兄さん保育士を
満面の笑顔で呼ぶ。
「かいとーーーーー
おかえりーーーーー」
ゆらりと
海斗が長の座を立ち、
人待ち顔にぽっかり空いていた
左の座に座り込んだ。
小さな小さな老人が
絽羽織の袖をはためかせて
キャーキャー駆け込んでくる。
「だめじゃだめじゃ
長は海斗なんじゃ」
「知るか!
次におチャラけたら
ここには二度と座らんと
言ったはずだっ!」
やだやだ
お願い お願い
のう のう いいじゃろーーー
老人は跳ね回り、懇願し、
海斗は〝問答無用〟と無視を決め込む。
老人の園児状態は屋敷の日常だが、
この騒ぎにはそろそろ飽きがくる二週間であった。
ひんやりと
空気の温度が下がった。
動くものもないのに、
空気が
一点に向かって収斂していく。
「御前………。」
声が響いた。
ぴたりと老人の動きが止まる。
そして、
長は最強の敵を迎え撃つべく
静かに振り向いた。
「長、
お席に。」
竹のなよやかさは、
その強さ。
割烹着の白は
背後に居並ぶ女衆を統べる証。
鷲羽財団にその人ありと知られた
御前の懐刀、
天宮咲が
そこにいた。
「そこは
わたしの席ではありません。」
「長の席です。
それを拒まれますか?」
天宮咲の声は
あくまで’優雅だ。
そして、
鷲羽海斗は、
何でもいいから
その座を回避するべく
意を決していた。
「家長の席でしょう。
ここは屋敷内。
長の名も、
総帥の名も、
外向きの話です。
そこは家長の席です。
家長は御老人です。
まだまだ健在だ。
総帥就任はしましたが、
家長は御老人。
春以来、
そうしてきたではありませんか。
今さら、
私がそこに座る必要が
どこにありますか?」
天宮咲の口許が弧を描く。
くくっと
片側の口角が目に見えて上がり、
その眸の光彩が
逆らうものを呑み込もうと火焔を放つ。
血を好むカーリーに
慈悲はない。
「形というもの、
意味あるものでございますよ。
特に平時においては、
千の言葉を尽くすより
重い意味をもちます。
戦は終わりました。
勝ち取った新生鷲羽の形を
お示しください。」
天宮咲が
ふっと言葉を途切らせ、
愛しげに瑞月を一瞥した。
慈母観音のオーラに
瑞月が
ん?
と
顔を上げ、
母の笑みにぱあっと顔を明るくする。
瑞月は
〝大人の話〟は聞かなくていいよ
という
囲炉裏の間ルールのお陰で
やや小難しい熟語が続く会話は
蚊帳の外だ。
振り向けば
慈母観音はカーリーの流し目で
贄の抗いを楽しむ。
「海斗様、
その座を拒むということは、
………。」
鷲羽海斗は素早く席を動き、
老人は
キチン!と空いた席に座り込んだ。
〝瑞月〟と
咲が口にするとは思えなかったが、
万に一つ、
その母が禁止令をかけたなら、
今夜の甘い時間はない。
それをかいくぐって
ロミオのごとく侵入したこともあるが、
成功したとは言いがたい首尾に終わった。
屋敷を支配する絶対君主制の頂点である
天宮咲は、
変化自在の化け猫〝黒〟に同じく
この屋敷の女怪とも言える存在だ。
咲はやる。
何事につけやる。
逆らおうなど、
屋敷にある者なら思いもすまい。
「では、
いただきますをお願いします。」
咲の采配で
食事は始まり
瑞月は
いつものじゃれあいを気にする風もなく、
きゃっきゃとしている。
その賑やかな団欒を
楽しむ気持ちもあるが、
海斗は
どこか居心地が悪い。
じじい
あんたが
ここにいてくれよ………。
それは
口にできぬ本音だった。
かつて
よく口にした〝海斗の中に溶けちゃいたい〟は、
今は洒落にならない現実だ。
今日のように、
少し距離をおくと、
それは滝のように雪崩れ込む瑞月に
実感する。
だからだろうか。
高遠とある瑞月を眺めていると、
咲の言う〝形〟が
ひどく胸苦しい海斗だった。
いったい、
今、
自分は何になっているのか。
その中身も
俺は知らない。
勾玉がもたらした
何かは
見えざるものだ。
あることは痛感させられても
それが己でなければならぬのかは
まだ決めかねていた。
瑞月と分かちがたく結ばれている。
それを疑うわけではない。
心の願うままにリアルに変容していく瑞月は
空恐ろしいほどだ。
ただ、
誰が長であるかを
分かりやすく周知徹底させるのが
〝長の座〟かもしれぬが、
海斗としては、
囲炉裏の間のその座にあるものは家長であり、
家長とは包むものを指すように思える。
そう考えれば、
幼稚だろうが、
騒ぎの元だろうが、
手がかかって小憎らしかろうが、
くそじじいの古狸だろうが、
家長は、
〝わし
サガちゃんが
大好きじゃ〟
と
揺らがぬ老人なのだ。
そして………高遠のように思える。
思わずため息が洩れた。
「海斗は、
かっこいいのう。
悩んどる海斗は
ほれ、
あれじゃ、
セクシーじゃ。」
老人は、
いつの間にか、
脇に座り込む黒に話しかけている。
うっふっふー
と
脇に座り込む小柄な老人あって、
瑞月を守る場を得られた。
そこで己も守られている。
それは
分かっているし
ここが己の生きる場だと定めてもいる。
が、
繰り言も消えぬ。
そばを離れない。
離したくない。
望みはそれだけだったはずだ。
得た平和の中で、
そんなことに
ぐるぐると思いを巡らす余計な時間ばかりが増えていた。
「あのね、
ぼく、
アルトになったの。」
「おうおう
そりゃあお披露目が楽しみじゃ
なあ咲さん。」
「ええ本当に
御前もおいでになりますよね。」
合唱か………。
バス問題が改めて重い。
人の中で
どう振る舞うか。
戦の中では簡単だったそれが、
平時には
どうしてこうも難しいのか。
〝鷲羽様ではございません?〟
車内で見た顔だけで
今の自分は特定される。
新生鷲羽という巨大な龍は
鷲羽海斗の顔と共に津々浦々まで知られた。
俺が龍を目覚めさせたのか
龍が俺を操っているのか
この巨大な龍は既に天空にある。
その顔も、
また、
不自由にはちがいない。
物思いに耽る海斗は
また余計なフェロモンを撒き散らし、
屋敷の女衆はそれを堪能した。
ともあれ
夕食は終わった。
母屋を出ると、
瑞月は俺の腕にしがみつく。
「ああ………海斗だよ。
嬉しいな。」
甘い声も
その小さな手の温もりも
いとおしい。
「ああ
俺もだ。」
二人の時間が
体に染み透っていく。
そして
瑞月は静かになった。
さっきまで老人とじゃれていたのが
嘘のようだ。
一度雪崩れ込んだ魂が
冴え冴えと月を映す湖面のように
胸の奥で静まっていくのを感じる。
かたっと
瑞月が動きを止めた。
歩くという行為も
不要なものとなったらしい。
「いい子だ。」
そう囁くと
俺は瑞月を抱き上げた。
ばたん
と
洋館のドアを入ると
民さんが驚いた顔で迎えた。
「まあ
瑞月さん
どうなさったんです?」
「私の中にいます。
どうも今日はさびしかったらしい。」
そのまま階段を上がり、
俺の部屋に入る。
抱っこのまま椅子にかけると
そっと額に口づける。
ふんわりと
そこに光が宿り
瑞月の中に消えた。
ふうっと
湖が仄かに染まり
瑞月の眸に海斗の顔が映る。
「おかえり。
俺が見えるか、
瑞月?」
「う、うん。」
「驚いた。
戻ってくれてほっとした。」
「ぼく
ずっとここにいたよ。
えっと
海斗の中にいた。」
「わかっていた。
でもな、
こうして二人でいないと
俺はさびしい。
お前にキスしたい。
お前はどうだ?」
「うん!
キスしたい!」
そこで
ようやく狼はほっとする。
日常のスリルに翻弄されながらも、
ともかくやっていくしかない。
膝の上で
見る間に小悪魔に変わる恋人は、
うふっとその目を閉じる。
こころもち突き出され、
ぷっくりとした朱唇が可愛いくも
艶かしくもある。
総帥には苦手分野ばかり押し寄せる平穏な日常だが、
瑞月は総帥を欲している。
深い口づけに溺れながら
海斗は幸せに酔った。
画像はお借りしました。
あいがとうございます。
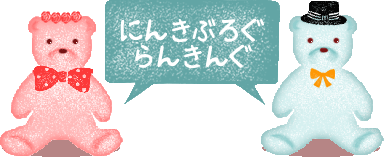
人気ブログランキング
