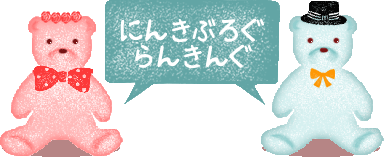この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
鷲羽財団総帥、
鷲羽海斗は、
洋館の入り口に立って、
目を見張った。
〝やすらぎ〟という題の絵画を
見るようだ。
飛び出してくる愛しい姿は
今日はなかった。
開かれた教科書、
その横に広げられたプリントは、
宿題に勤しんでいるのだろう。
問題を見つめる眸が
すっと横に移動する。
ペンをもつ手がさらさらと動く。
小振りのシャンデリアから落ちる灯りが
その髪に落ち、
輝く輪が浮かぶのが、
巧まずしてこの絵画の中心を示していた。
子どもは
夢中で
何かに取り組んでいる。
そして、
それは美しかった。
ふっと蛍飛ぶ水辺が浮かんだ。
美しいものを無心に見る己が
今に重なる。
鷲羽海斗は
己の子ども時代に夢中になって努力したという経験がない。
できることはできてしまった。
ただ一度
美しいものを夢中で見つめたことが
記憶にある。
乱れ飛ぶ蛍。
それも瑞月と出会うまで封印されていた記憶だ。
己に気づかぬ瑞月を見るということが、
鷲羽海斗にはなかった。
今、
ただ、
一心に宿題に向かう瑞月は、
絵のように美しく
目を奪われた。
ずっと見ていたい。
そう思った。
ふと己を見つめる視線に気づく。
高遠だった。
気づくと同時に目礼が返された。
今の己を見ていたのか。
そう思うと、
ふっと心が揺れる。
瑞月を愛している。
その重さにおいて、
今のお前は相応しいのかと測る目。
そこに映る己を、
また己が測っていた。
静かに咲が現れ、
ブリーフケースを受け取る。
咲の眸もまた全てを見通している。
今は瑞月をそのままにということだろう。
その着物の竹の紋様が涼しくもあり、
静けさを象徴するようにも感じられた。
ぴたりと
手が止まる。
眸がぐらりと揺れて
頭もふらついた。
すっと横から手が伸びる。
その肩を抱く手、
プリントを取り上げる手、
そして高遠は優しく肩を揺すった。
「ようし 頑張った!
できたな。
もう いいよ。
ほら あっちを見てごらん。」
瑞月の眸が
ふんわりと高遠の指す先へ、
鷲羽海斗へと動いた。
眸に力が籠る。
熱い波動が海斗の心臓に雪崩れ込む。
いた!
いた!!
いた!!!
目眩がするほどに繋がった魂の半分が震えるのを感じた。
腕に飛び込んでくる瑞月の細胞一つ一つまで
今の自分は感じることができる。
GWを経て、
この連動する魂に
鷲羽海斗はまだ慣れていなかった。
柔らかい。
すっぽりと腕に収まる小さな体に
ようやくそれを感じて
足が地についた。
「今週は宿題が多いんです。
今日の授業で、
ぐっとできる問題が増えました。
瑞月、数学は得意ですからね。
四月分取り戻しました。
それも褒めてあげてください。」
高遠が
落ち着いて話す声がして、
かたりと椅子を引く音が続く。
もう立ち上がった高遠が、
咲を振り向き、
静かに頷いている。
そして、
手早くテーブルの上のものをまとめる。
「さあ 瑞月、
自分の分持って。
まず片付けだよ。」
その声のままに
瑞月の背がしなるのが
手に伝わる。
「うん!」
可愛い声だ。
甘くて素直な声は
高遠に向かっている。
こうして繋がってしまえば
瑞月は
また
手が届かない。
繋がっていながら
その動きは
鷲羽海斗の思いに関わらない。
蝶は手から離れていく。
ひらひらと高遠の元に戻り、
髪をくしゃっとされて
嬉しそうに笑う。
「間に合ったよね、ぼく!」
「ああ 間に合った。
さあ これ二階に持っていくんだぞ」
教科書やらプリントやらを胸に抱き、
いそいそと階段を上る瑞月を
高遠と見送る。
ドアが閉まるまで、
何ということもなく動けぬ感覚があった。
それは高遠の見上げる姿勢から感じていた。
今は揺らすな
そういう言葉にならぬ威が、
ごく自然な佇まいの中に感じられる。
そして、
ドアは閉まった。
くるっと
高遠が振り向く。
明るい目だった。
「今日は
ちょっと大変でした。
海斗さんといられるはずの時間が消えて
バランスが悪かったかもしれない。
さっき取り戻しましたね。
見ていても分かります。」
分かる。
見えている。
そう高遠は伝えている。
何を話すにも、
瑞月の今を知ってでなければ、
始まらない。
「そうだな。
………驚いている。」
高遠には
そのままを伝える。
そう決めていた。
高遠は
〝驚いている〟を
さらりと受け止めたようだった。
「海斗さんへの連絡は、
一つだけ。
海斗さんはバスになりました。
今日、
パートの発表があったんです。」
声の調子がすっと変わる。
ここからは事務連絡ということだろう。
「瑞月はアルトか。」
予測していた。
「ええ。
そうなるんじゃないかと
思ってました。」
くすっと笑う。
「あの子は音を取れない。」
そこが’問題だ。
「ええ。
たぶん………サヨさんは
取れるはずです。
三人とも自信がないので、
へたれてます。」
「三人………?
ソプラノはどうした?」
「かっちゃんです。
聞かせたかったな。
すごかったですよ。」
「なるほどな。」
合唱は
瑞月だけでは済まない。
成功したと感じるのは、
音が取れたときではないだろう。
「わかった。
お前と西原はテノールか。」
「ええ。
マサさんがバスです。
男声は心配ない。
練習中はバスにいてくださいね。
海斗さんがいて、
心配ないと言えるんですから。」
ちくりと
痛かった。
バスにいて、
どう振る舞えばいいのか、
そこは分からない。
「………わかった。」
次の土曜日は
また作田にも来てもらおう。
総帥海斗は決めた。
他力本願というわけではないが、
そういう場に身を置いた経験が、
海斗にはなかった。
中学校での僅か二年を
作田にため息をつかせながら
過ごした。
クラスという単語は知っているが、
そこで生きるという意識はなかった。
ジムの中でも
それは同じだった。
ただリンクに上がり叩きのめす。
それだけだった。
データを無尽蔵に蓄積できる頭脳がありながら、
関わった人間の顔で覚えているのは
身元引き受け人となってくれたBAR PIETAのマスター神山と
作田刑事くらいだ。
後は影法師のように朧に霞む。
鷲羽という小世界に入り、
佐賀海斗は
初めて
集団を学んだ。
ただし指揮官として。
己が龍の頭となり、
その体の隅々まで己の思うままに動かす。
鷲羽海斗が知る〝何事かを成す〟とは
そういうことだ。
横並びの一人という位置は、
馴染まない。
だが、
その馴染まぬ位置が
どうやら必須条件のようだ。
顧問に着任した作田の存在は
このミッションでは
かなり重要となりそうだ。
画像はお借りしました。