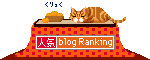この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
うらうらと
雲雀は空に唄う。
瑞月は変わらなかった。
白いジャージの稽古着もそのままに
幼い綾周と出会った瑞月が舞う。
静謐満ちる祭場はない。
鳥らは囀ずる。
百千鳥の中にその声を聞き分けるも徒だ。
篳篥は鳥たちの声に溶け
その楽を共にする。
渡邉の声は古を辿らなかった。
ちょうちょ
ちょうちょ
菜の葉にとまれ………。
瑞月は蝶になった。
海斗は見つめた。
幼い魂を送り出す舞いは
その幸せだったときを追ってゆく。
頼りない父と無心に遊ぶ幼い子が
ひそやかに過ごした月日が
松の治める結界に広がる。
何の変哲もない白ジャージの腕が
すっ
と
季節の変化を告げた。
幼子が目を見張る様が瑞月の眸に浮かび、
辺りに群れ飛ぶ光の大群が
その指先に現れた。
わー 綺麗!
光ってる
あれ なあに?
海斗は胸にせり上げてくる痛みに耐えていた。
お母さん
ねぇ
綺麗だね
ぼく
夢見てるの?
小さな男の子は
それぞれに
その光の海を夢中で歩いていく。
ほう ほう 蛍来い
あっちの水は にがいぞ
こっちの水は 甘いぞ
ほう ほう 蛍来い
どんなにその時が
幸せの時であったことか。
母の細い指先が
なんと優しかったことか
己の幼い日の幻の前を
若い父と
その子は
まるで二人の子供が寄り添うように漂う。
綾周
幸せだ
お前も 俺も幸せだ
この時を持てただけで
どんなにか幸せだったな………。
水辺に耀う無数の光
その久遠の果てまで続く光の道を
儚い影がゆらゆらと消えていく。
さっと
天に振られる手の先に
蒼天が広がった。
高い 高い
なんて高い空であったことか
秋の空だった。
遠く渡る鳥たちは
その端を既に朱に染めかけた空を
一文字に連なっていく。
見る間に染まりゆく雲は
華厳の炎となって
光を抱く。
わー
すごーーーい
お父さん
お空が火事だよ
明るい声が弾ける
その小さな手を握る父も
呆然と見詰める秋の夕映えだ。
夕焼け小焼けで 日が暮れて
山のお寺の 鐘が鳴る
おててつないで みなかえろ
からすといっしょに かえりましょう
旋回する白くしなやかな体に
その炎は巻き上がる
火の粉は舞い狂い
秋はその有終の美を繰り広げていた。
ねぇ
一緒に見るから
綺麗なの
ああ 綺麗だなって
わかるのよ
優しいアルトが
海斗の耳をそよがせた。
ああ 本当だ
わかる
今こそわかる 道子
肩先に感じる温かさが
晩秋の夕べそのままに感じられた。
瑞月を得て
その温かさを注ぐことができた。
人を感じる心が
ドキンと
最初の脈動をもったそのとき。
ありがとう
ありがとう 道子
遠い潮騒を微かに聞きながら
海斗は夕焼けの美に
酔いしれた。
瑞月が舞っていた。
そこにいる者たちにの折々のそのときを
瑞月が与えていた。
あっと
瑞月が空を見上げる。
ふわり
と
差し伸べる手に
一片の雪が
今舞い降りた。
お父さん
雪!
雪だよ!
わーつめたーい
駆け巡る男の子が見えた。
それを見詰める父親の
哀しくも透き通った眼差しが
一面に白くなっていく世界から音を消していく。
雪や こんこ
あられや こんこ
降っては 降っては ずんずん 積もる
瑞月は舞う
無心に舞う
雪は
もう降りやんだのだろうか
白く広がる丘陵に
遊び疲れた綾周がその愛らしい目を見張って両の手をついていた。
お父さん
降ってくるものって
真っ白だね
伊周が綾周を抱き上げた。
ああ
真っ白だ
そっと囁く声が
綾周を眠くするようだ。
綺麗だねぇ
ぼく
たくさん綺麗なもの見たよ
あどけない声が
その柔らかそうな唇から零れて
それが寝息に変わる。
また雪が舞い始めた。
綾周の頬に
その顔を覗き込む伊周の髪に
雪は降り積もる。
伊周が
綾周を抱いて
雪の丘に静かに立ち尽くす。
雪は舞い
その姿を朧にしていく。
ふっと
伊周が空を見上げ
そして
一同に向き直った。
深く下げられた頭、
そして
………………消えた。
篳篥が
その音色を最後に響かせて
ふっと途切れた。
瑞月が空に差し伸べた手をそのままに
ぴたりと止まる。
渡邉の独唱が
丘陵に流れた。
雪やこんこ あられやこんこ
降っては 降っては ずんずん積もる
山も 野原も 綿帽子かぶり
枯れ木残らず 花が咲く
チチ チチチチッ
チチチチチ チュンチュン………。
陽光が丘を満たしていた。
「………海斗」
瑞月の涙声が海斗を呼んだ。
「海斗!
海斗!!」
悲しくて悲しくて
その声は呼ぶ。
駆け寄って抱き締める腕の中で
瑞月は
くしゃっと顔を歪める。
「アヤちゃん
………………消えちゃった
消えちゃったーーーーーー」
顔全部を口にして
瑞月は泣いた。
あーん あーん
と
しがみつく細い体を
その震えごと抱き締めて
海斗は囁く。
「いいんだ
泣いていい
たくさん泣いていい
これでよかった
よかった
がんばったな
がんばった
もう泣いていい
………………………。」
百千鳥に
誰の泣き声も
もう分からない
降り頻る
ただ降り頻る鳴き声に
丘陵は
小さな男の子と
その若き父を送った。
水澤が
そっと立ち上がり
渡邉を従えて
歩み寄った。
瑞月の涙が零れては真珠の頬を伝う。
日の長に抱かれて
陽光の中に生い茂る草原の緑を吸い上げ
翠は優しく巫を包んでいた。
水澤と渡邉が
日の長の足下に膝をつき
鷲羽に戻った神器を差し上げる。
翠の光が葉末の露となって
笛に注がれた。
篳篥は竹の筒に葦の舌を接いで鳴る。
その竹がみるみる色を取り戻していく。
ごく素朴な笛が
そこに現れた。
祭儀のため
ホテルの屋上に立てられた白木の柱
その階となった板目も瑞々しい横木が
そこに重なる。
笛は
その海辺の姿をもって
巫の涙に応えていた。
イメージ画はwithニャンコさんに
描いていただきました。