この小説は純粋な創作です。
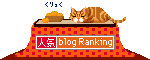
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
そこにあるものより、
ないものが語るものはあった。
光の消えた後に
虹色の玉はなく
伊周の体はなかった。
その空白が西原の心を
切なく締め付けた。
お前が一生懸命聴いてるんで
俺、
頑張れたんだぞ
綾周
お前、
消えちゃったのか?
図書館で西原の読み聞かせを聞いていた小さな男の子も
リンクの端で小さくなって覗いていた美しい少年も
もういなかった。
〝お兄さん
一緒に遊んでくれる?〟
可愛い声が耳に甦る。
忍び泣く声の主は
振り返るまでもなくわかった。
民はどれほど辛いだろう。
そして、
瑞月だった。
ぽとんと膝に落とした手の上に笛を乗せたまま
瑞月は動かなかった。
可哀想に………。
一人で
この悲しみを背負うのか
そこまで思って気づいた。
総帥………総帥はどうしたんだろう
長身の影が
板壁と見えた奥に立っていた。
ガタガタっ………、
ガターーンっ………。
今度こそ西原の目は光に射られた。
暗がりに慣れた目には白色光に辺りが一様に白く感じられる。
日差しが
雪崩のごとく
庫を埋め尽くしていた。
「瑞月
出ておいで」
逆光に
その影すらも眩しい。
そして、
全身に陽光を浴びた瑞月が
眩しかった。
瑞月
ほら 呼んでる
お前の大切な人が
待ってる
西原は
ただ見つめた。
瑞月は
まっすぐに立った。
顔に
胸に
腹に
陽光は弾んで跳ねる。
光を編んで宝玉とし、
精緻な細工を加え、
光で研磨する。
神々の美をすべて集めた天界の生き物のようだ。
そして、
その足下から伸びる影は色濃かった。
それが悲しみのようで
西原は息を詰めて瑞月を見詰める。
影あるからこそ美しかった。
地上に生きるものは
影から解き放たれることはない。
悲しみも怒りもある。
それがいかに深くとも
それを抱いて
なお
生きることを
光に向かうことを諦めないとき、
その姿は尊い。
瑞月
悲しくていい
泣いてていいから
ほら
歩いてごらん
西原は
葦の正体に気づいたときを
思っていた。
守りたい思いは
いつでも闇に転落しかねない。
人の抱く思いは厄介なものだ。
西原は思う。
一生分思うほどに思っていた。
瑞月
瑞月
頑張れ
頑張れ
立ち尽くす美しい光に
西原はエールを贈る。
選ぶ。
選ぶ。
生きるとは〝選ぶ〟ことの連続だ。
誰が
それを間違わずにできるのか………。
大事なのは価値観って奴かもしれない
西原自身が
覚えがあった。
西原にとって瑞月は最初〝総帥の命じた警護対象〟でしかなかった。
その第一の対象を任された誇り、
若手出世頭の誇り、
人生で勝ち続けてきた誇り、
それだけが価値観の全てだった。
お前が教えてくれた
本当に守りたいっていう気持ちを
そしたら
みんなが教えてくれることが
分かるようになったのさ
水澤先生が
マサさんが
アキさんが
かっちゃんが
皆が教えてくれた
もういっぱい過ぎて
思い出せない。
思い出せないけど
俺はきっと
今
人間の形をしている。
お前のお陰なんだ
だから
だから頑張ってくれ!!
立ち尽くす瑞月に
眩しい影から
言葉がかけられた。
「瑞月
今
お前が苦しいことは
ぜんぶ俺が背負う!
だから………!」
影の言葉は
西原の思いでもあった。
そして、
光の精霊は
キッと
その顔を改めた。
朱唇が開いた。
「海斗!
ぼく
ちゃんと自分で背負う。
海斗の分も背負う。
ぼくが守るよ
海斗も皆も
ぼくが守るって決めたんだから。」
そうして、
瑞月は歩き出した。
民が涙を振り払い、
政五郎が手を合わせた。
その瑞月を
総帥は
少しの間
ただ見つめていた。
西原はそう記憶している。
僅かな時間
それでも永遠とも言える時間
総帥は泣いていたのかもしれない。
西原は思い返すのだった。
長身は
さらに先導するように
庫から踏み出し地に足を降ろし
歩み出した。
瑞月が
それに続いて
光の中に降り立っていく。
ああ
明るい………。
西原は
一行の最後に
その庫を出た。
松が待ち受けていた。
己を瑞月の守り人と選び
迎え入れてくれた大木が陽光を浴びて丘に聳えている。
振り向けば
そこには
役目を終えた庫の残骸が
朽ちて乾いた木材の山となっていた。
陽光が降り注ぐ。
その木材を這う虫たちの命の営みが
もう展開を始めた。
西原は振り仰ぐ。
空はどこまでも青かった。
そして見遥かす。
初夏の丘陵は緑一色だった。
光が眩しすぎて
その足下の影さえ草原に遊ぶ光に消えていきそうだ。
西原の耳に水澤の声が届いた。
「忘れないことは
背負うことではありません。
私は別れと出会いを重ねて学んだことがあるんですよ。
聞いてくれますか?」
「はい」
瑞月の生真面目な声が
胸に痛かった。
甘えまいと必死なのだろう。
そう西原は感じた。
水澤は
松の根元に立ち
その幹に手をかけていた。
丘の中央
その頂の真っ芯に立ち
水澤は語り出そうとしていた。
水澤の授業が始まる。
「瑞月君、
君のことを
海斗さんが背負うと言いました。
あなたは
どう感じましたか?」
瑞月は
海斗に視線を移した。
そして、
その視線を動かすことなく
背筋を伸ばした。
「ぼく、
何回も何回も
海斗に背負ってもらいました。
たけちゃんも
トムさんも
いつも背負ってくれます。
ぼく、
嬉しかったです。
きっとこれからも
何回も背負ってもらうんだと思います。
ぼく子どもで
弱くて
力もありません。
そんなぼくを背負ってくれるなんて
ほんとに感謝してます。
ただ
ぼく
思ってます。
次は
ぼくが背負いたいって
思ってます。
みんなが悲しいです。
海斗が悲しいです。
ぼく
みんなのアヤちゃんを
消しちゃいました。
だから………。」
水澤の片手が
毅然として上がった。
瑞月が口を閉じた。
「そう。
アヤちゃんは消えました。
その魂は
今
君がその手に抱いています。
大事に思う人に会えなくなることは
悲しいです。
そして、
私たちはその悲しみを忘れられません。
瑞月君は
それも
学んでいる。
そうですね。」
水澤の声が
その場に生きるすべての者を包み込んだ。
その草原に
懐かしい面影が幾つも浮かんでは消えていく。
「私たちは
繰り返し
繰り返し
会えなくなった人の思い出をなぞります。
ときには
その人を追って自分を消してしまいたくなるほどに
悲しみは深い。
だからね、
人が人を喪った悲しみは
そう簡単に
肩代わりできるものではありません。」
水澤は
その言葉が
一同に染み込むのを待つように
言葉を切った。
風が渡る。
「悲しみを背負うとは、
それを引き受けて
相手のそれを忘れさせてあげるとも取れる言葉です。
そういうこともあるものです。
それを否定はしません。
が、
立ち直るとき、
人は悲しみを忘れていないことが
多いものです。
君は
すべてを思い出して歩き出しました。
瑞月君、
そうでしたね。」
瑞月が
一瞬
その顔を真っ白にした。
「せんせ………。」
「西原!」
西原が吠える言葉は
海斗に遮られた。
海斗は
ただ一歩前に踏み出した。
いつでも
瑞月に駆け寄れる。
その態勢を取り、
静まった。
西原は
頭を小さく張られて
振り返った。
政五郎だった。
瑞月の周りは静かだった。
バサバサッ
木から飛び立つ翼の音がやけに響くほどに。
空を渡る鳥の影が丘をゆっくりと下っていく。
瑞月が口を開いた。
その眸は
ひたと海斗に当てられた。
「はい
海斗が
受け止めてくれました。
何度も
何度も愛してくれました。
綺麗だ
世界一綺麗だって
言ってくれました。」
海斗は
静かにその姿勢を変えた。
瑞月は倒れなかった。
そして、
自分の言葉で語り出した。
海斗は
静かに聞き入った。
「それでも
ぼく
消えちゃいたくて
きっと海斗も我慢してるって思えて
我が儘言いました。
ぼく
ひどい発作の後で
とても弱ってました。
海斗は抱いてくれました。
幸せでした。
ぼく心臓を止めたんです。
ああ愛されたまま死ねて幸せだって
思いました。」
その幸せは
海斗のものでもあった。
本当に
そのまま二人で逝けたなら
どんなに幸せだろうと思ったのだ。
だが………。
と
海斗は思い出す。
「でも
海斗が泣いて
一生懸命呼び戻してくれて
ぼく
戻ってきました。
海斗が迎えてくれました。
ぼく
海斗と生きるって
とても幸せだって思いました。
ぼくの全部を愛してくれる人がいます。
ぼくも海斗の全部を愛してます。
ぼくたち幸せです。」
〝ぼくたち 幸せです〟
勝利の凱歌のように高らかに宣言するや、
月の巫は
まっしぐらに日の長の胸に
飛び込んでいった。
胸に抱いた笛ごと抱き締められた
瑞月の胸元に翠の光が広がる。
水澤が
静かに松を離れた。
瑞月に歩み寄り
その手の笛を取り上げる。
まだ、
この授業は終わらなかった。
「アヤちゃんは、
瑞月君に反応して
あの場に現れました。
おそらく
秦家の続く間、
一回もなかったことのはずです。」
水澤が
笛を手に
廃墟となった庫を見やる。
「マサさん
あなたはこの笛を守ろうと戦った。
この笛は鷲羽のものですね。」
政五郎が
庫の跡となった
枯れた柱や朽ちた戸の重なる前に
静かに歩み寄った。
その柱に
戸に
何か思い出す縁を求めるように
しばし
政五郎は眺めていた。
「そうです。
大事なものがいっぺんに襲われました。
あっしは
夢中で走った。
あそこは祭に使うもんを仕舞ってたんですね。
飛び込んでっから気づきましたよ。
秦は知ってたんでしょうね。
あいつが付いてきたときは
邪魔くせえなって思いやした。
でもね、
よたよた探すあいつが
あの匣を見つけてくれてよかったです。
最後
何が何だか
あっしには分からなかった。
ただね
真っ黒なもんが
いきなり庫いっぱいになっちまって
逃げろーーーって
わめいてましたね。
ところが
秦の奴は
飛び付いて行ったんです。
あの匣だったんですね。
飛び付いて
そして………呑まれちまいました。
あっしは
そのとき死んじまったんだか
どうか。
先生、
いきなり頭に浮かぶまで
あっしは何にも覚えちゃいなかった。
不思議なもんですね。」
昔語は終わり
水澤は
その笛を両手に高く捧げもって
皆に示した。
「私には
そのときの記憶がない。
また楽器の一つ一つを覚えてはいません。
あの海辺の祭儀も朧なのです。
ただ
とても特別な祭でした。
それは覚えています。
その折りに使われたものは
その特別を与えられたのかもしれませんね。」
水澤は
捧げ持った腕を下げ
瑞月の前にそれを差し出した。
「瑞月君、
音楽の授業で教わったかな。
これはね篳篥という楽器だ。
この楽器はね
雅楽では主旋律を鳴らす役目がある。
そしてね、
ここが大事なんだが、
口をあてるところは
筒とは別にできているんだ。
ほらね。」
水澤は
指し示す。
瑞月は
小さく頷き
その笛を一心に見詰める。
「ここはね、
葦舌という。
漢字で書くと葦の舌だ。
葦でできてるんだよ。」
瑞月が
一瞬
ビクッと身を引いた。
「先生………!
でも………っ」
そして、
身を引いたことを恥じるように
頬を染めて水澤を見上げる。
水澤は
それを微笑んで受け止めた。
「そうだよ。
アヤちゃんや伊周さんが
闇の本体ではない。
伊周さんは
その力を借りてアヤちゃんを守ったんだろう。」
水澤は
また
草原の続く丘陵を見渡した。
深水であった昔から考えてきた鷲羽の不思議を思うのか、
その瞳が閉じられた。
視力を失った間に
考えを巡らせてきた闇に
水澤は戻っていく。
「古代から続く闇は
秦の家とは別にある。
その折り折りに
人を食い物に生きているものだ。
きっとね
こうして戦いが始まるのには
何かきっかけがある。
そういうとき
海斗さんのような長が鷲羽には現れるんだ。
そして、
月の巫と巡り会う。」
朗々と響く声は
まるで予言のように厳かだった。
水澤は目を開いた。
改めて
その手の篳篥に目を落とす。
「この篳篥の魂が庫から逃れ出たことも
そのきっかけかもしれませんね。
伊周さんには、
マサさんの知る若者の魂が
宿ったのでしょう。
どこまでも守ろうとなさった。
そして、
最後に、
篳篥は鷲羽の手に戻ろうとしました。
アヤちゃんも
伊周さんもです。」
水澤が
纏う装束の袖を
大きく払った。
ピタリ
と
瑞月の前に片膝がつかれた。
「瑞月君
私がこの篳篥を鳴らします。
かっちゃんは謡います。
君は
何を舞う?
私たちは君に従う。」
瑞月が
しっかりと顔を上げた。
まず海斗を見つめた。
そして、
民を、
政五郎を、
西原を、
瑞月は見つめていく。
「アヤちゃん
すごく可愛くて
とっても綺麗な子でした。
ぼく、
ステージで大人のアヤちゃんに会ったときから
なんて綺麗なんだろうって
思ってました。
世界一綺麗なアヤちゃんを
舞います。
あの
皆もアヤちゃんや
お父さんのこと思い出せるように
舞いたいです。
思い出して
そして
アヤちゃんはここにいるって
思ってほしいです。」
皆に届け!
と
瑞月は精一杯に声を張った。
イメージ画はwithニャンコさんに
描いていただきました。
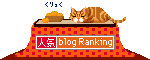
人気ブログランキング
