この小説は純粋な創作です。
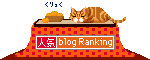
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
一条の灯りはあった。
定規をあてて縦に引いたように明瞭な白光を前に
水澤が振り返る。
「海斗さん
どうですか?」
視力を取り戻した導師は、
その眸を閉じた。
再び慣れ親しんだ闇に身を浸した水澤の白装束の袖が
ゆっくりと白光の前を上がっていく。
両袖を閉じた眼の前に合わせ
水澤は己の姿を皆に見せた。
伊周はきょとんとする。
特段何も起こりはしなかった。
影のない
薄墨色の虚空の通路で
互いの姿は
変わらずそこにあった。
「影がない。
この光はここに差してはいないようですね。」
瑞月の肩を抱いたまま
海斗は静かに応えた。
政五郎が
さっと背後を振り返り、
西原がそれに続いた。
「迫ってきています。」
西原は短く報告し、
そのまま通路を呑み込んでいく暗黒に対峙した。
「すげえな。
お星さまでもありゃあ
宇宙ってところじゃねえか?」
老将政五郎がくすりと笑う。
一行は振り返った。
重力をなくし身が浮き上がっていくかの錯覚が生じる。
今、
一行が足を置いた通路は
さながら宇宙空間へと突き出した桟橋のようだった。
そして、
それは刻々と短くなっていく。
さらさらと音もなく
ただ呑み込まれていく己の足下へと繋がるもの。
この儚い桟橋に残された時間は僅かだった。
綾周を抱っこした民の腕に力が籠る。
その唇は引き結ばれ
眸は光を増した。
「あ、あ、あれ……何なんですか?」
伊周の声が震える。
「闇というものだ。」
海斗は短く応え、
再び光へと向き直った。
道標は常に謎なぞを伴う。
答えはあるはずだった。
瑞月の温もりは腕に確かだ。
水澤はもう腕を下ろして静かに立っていた。
導師は促すように優しく目をしばたく。
渡邉は愚直に光に向かったままだ。
白装束の二人には答えは見えているのかもしれない。
海斗は静かに目を閉じた。
これは入り口だ。
この先に
秦の屋敷がある。
そう念じる。
「海斗、
開けないの?
ここ……廊下だし、
誰か来るかもしれないよ。
僕たち靴のまんまだし……。」
腕の中で
愛らしく身を捩る肢体が感じられるや
声をひそめた囁きが耳に届いた。
足下の感触が変わる。
板の間の固さが土足を拒むように
足裏から上ってきた。
そうだ
お前はスニーカーのままだったな。
そして、
俺は革靴だ。
お歴々のお相手をしなければならなかったからな。
お前を連れて部屋に入った俺は
革靴を履いていた。
「ここ
ちょっと
おじいちゃんのお屋敷に
似てるね。
………洋館からお屋敷に行くところみたい。
地下なのかな?」
囁く声は
ますます小さく、
そして早口になっている。
そっと後ろを窺う小さな頬が
左腕を擦る。
長く続く廊下なのだろうか。
愛らしく傾いた頭はそのまま動かない。
恋人の目になって見張っているつもりらしい。
「怖くない。
誰も来はしない。
さあ 入ろう。」
見知らぬ屋敷で
家人に見咎められるのを用心しているらしい瑞月に合わせ
海斗は囁き返す。
海斗は目を開いた。
左右は漆喰の壁だった。
二人の影が前の板戸に落ちていた。
海斗は背後へと
意識を繋いだ。
感じられた。
近づいてきますよっ!
うるせえなっ
見えてるもんを一々言うなっ
マサさん
これ消せます!
たぶん
いえ きっと消せる!
西原の声に
海斗は
にやりと笑った。
ほめてやるぞ
西原
消せる。
それは確信となった。
「海斗
みんな何を言ってるのかな。
騒いじゃいけないよね。
き、聞こえないけど、
小さな声なのかな?」
心配げに語尾が小さく消えるのを
肩を抱いた腕で
優しく揺すってやり
海斗は板戸に目を当てた。
前を向いたなり
海斗は声を飛ばす。
ここは秦の屋敷だ!
目を開けろ!
ガクッと伊周の膝が崩れ
たたらを踏んだ。
靴下裸足の足の下で
きゅきゅっと床が鳴る。
西原は
さっと前へ飛び出してきて
板戸の脇に身を寄せた。
政五郎は
身を開いて背後を固める。
傀儡らが飛び出してくるなら端から倒す構えだ。
民は
あらあらと天井を見上げ、
また見下ろしている。
その腕は抱いた綾周を優しく揺すっていた。
大した胆力の女性には違いない。
伊周は
いきなり放り込まれた場所に
ただ踞っていた。
闇に呑まれる恐怖は
次の衝撃に拭い去られたらしい。
「伊周
ここで間違いないな」
かけられた言葉に
その肩がびくっと震えた。
ふわあああああっ
小さなあくびが
薄暗くかび臭い廊下に
あどけなく
響いた。
伊周が
ハッとしたように
顔を上げる。
民が
伊周の前に膝をついた。
腕の中の綾周は
伊周を見つけ
あっ
あっと声を上げる。
小さな手が
パタパタと伊周の頬を叩いた。
民が優しく頷き
伊周は立ち上がった。
ほうら
いい子
アヤちゃん
いい子ね
民が綾周をあやす声を背に
伊周は板戸に進んだ。
「ここを知っています。
夢かと思っていました。
…………本当にあったんですね。
きっとここに答えがあります。
入りましょう。」
次の場を開くのは
この青年の務めらしかった。
からからと
滑らかに引き戸は横に流れた。
秦家を継ぐ青年の向こうにくすんだ色合いの絵が描かれた板戸が
ピシッと閉じられていた。
その合わせ目を前に
白木の台に置かれたものが
その場の主であるかのように一行を迎えた。
人の姿はない。
古色蒼然とした鞨鼓だった。
皮には火焔、
銅には龍が躍る。
楽の始まりを告げるというその響きが
今こそ打ち鳴らされようとしていた。
画像はお借りしました。
ありがとうございます。
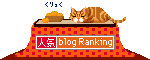
人気ブログランキング
