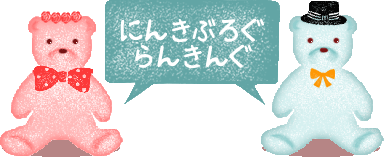この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
やや遅刻しての参会となったが、
晩餐の始まりには余裕がある。
デリクは
客間に集い
三々五々と輪を作る客たちを見回した。
令嬢らは
その保護者の手を離れ
女同士のおしゃべりを楽しむものもいれば
そこに紳士を招き入れて
何やら楽しげに笑いさざめいているものもいる。
そこに混じるべきなのだろうが、
主夫婦にご挨拶をして
飾られた東洋の器などを誉め
慇懃に礼を交わせば
もう義務といえるほどのことは終わる。
入場と共に
令嬢たちから
頻りに視線を投げ掛けられるのは
いつものことで、
気にはならない。
だからといって
デリクは
彼女らに話し掛けられるということはないからだ。
遠巻きに
何やらしゃべっているのは
女の習性なんだろうな
と
受け流してきた。
「おお
バートン君、
ぜひ見てもらいたい品があるんだ。
この間
のみ市で手に入れたんだがね……。」
的外れな自慢もあれば、
同好の士との語らいもある。
デリクは
大抵が
そうした男たちに囲まれて
何となく時間を潰すことができるのだ。
「すみません。
あの夜はドーソン卿につかまってしまい……。」
叔母たちが
やきもき心配しては送り出す夜会を
こうして
もっともらしい言い訳で切り抜けながら
もう30歳となる。
「デリク!
嬉しいな。
またメリル叔母さんですか?」
食前酒を手に
ご令嬢の一群と談笑していた青年が
デリクを見て
嬉しそうにそこを抜けてきた。
「君も同じだろ?
六番目のウィル。
今日は四番と五番は逃げ出せたのかな?」
一族にウィルが多いのは
大叔母の一族の特徴だ。
デリクは名付けから
既に傍系と言える。
「あいつらは、
もう片付いたんです。
あっという間でした。
メリル叔母さんですよ。
凄腕なんだから。
叔母さん、
ますます縁結びに力が入っちゃって。
デリクのせいですよ。
僕なんか
まだ23歳だってのに
デリクみたいになったらって
今から煩くて大変です。」
若者は
金髪碧眼の童顔を火照らせて
憧れの従兄に語りかける。
社交界には
とんと顔を出さず、
大学の図書館やら博物館やらにこもりきりのデリクは
なかなか会うこともない。
「悪かったね。
心配しなくても
君には可愛いお嬢さんが
すぐ見つかるのに。
いつも楽しそうに話してるじゃないか。」
アパートに訪ねてきて
頬を染めながら
売りに出された骨董の話を残念そうに相談してきた従弟を
デリクも可愛く思っていた。
好青年であるウィルは
叔母たちのお気に入りでもある。
「何言ってるの。
令嬢たちは毎度デリクのことばかり
僕に尋ねるんですよ。
何が好きなの?
踊れないの?
女性が嫌いなの?
もう
そっちも大変なんですよ。
その気になれば
デリクは明日にも教会に向かえるんじゃないですか?
叔母さんだって
そう思ってます。
なぜ結婚しないの?」
デリクは
整った顔をしかめ、
手を振る。
「ぼくはね、
ご令嬢の皆様に
話しかけてさえいただけない
朴念仁なんだ。」
晩餐の開始が告げられ、
大広間へと皆は移動を始めた。
デリクも
めったに会えない従弟と連れ立って
移動していく。
「あの、
デリク・バートン先生ですよね。
私、
先生の紹介された
女性と雨の描かれた浮世絵、
ほんとに感銘を受けました。」
思い切ったような
一生懸命な声が
デリクにかけられる。
青のドレスが
ほっそりとしたまま裾へと流れ
胸に組んだ手は同色の手袋をつけてしっかりと握られていた。
「ありがとうございます。
私も
強く感銘を受けたんです。
感動を共にできて嬉しいですよ。」
生真面目に応え、
デリクは
また食堂へと進む。
これは、
自分は遠慮しようかと
脇に下がっていたウィルが
慌てて従う。
「デリク、
話しかけていただいたじゃないですか。
どうして、
置いてっちゃうのかな。
彼女、
がっかりしてた。」
「浮世絵の話?
パーティーといえば、
毎度
その話ばかりだよ。
ぼくの話とはいえないさ。」
晩餐は
立食形式となっていた。
主催者の意図は見えるが
同時に逃げやすくもある。
デリクは
先ほどまでと変わらぬ会場の様子に
ほっとしていた。
ウィルを誘って
バルコニーに出る。
手摺にもたれれば
夜風が心地好く
中にさんざめく人々の行き交う姿も
街を歩く人々と変わらぬ
遠い風景となる。
こうして
その流れの外にいるのが
デリクには有り難かった。
横で
どこか憤然とした風に何か言いたげな従弟に
ともかく
見せたいものだけ見せておこうと
デリクは袱紗を懐から取り出した。
「何ですか?
珍しい布地ですね。」
それでも、
ウィルは目敏く
袱紗の不思議な紋様に気がつく。
白い花芯をもつ小さな花が無数に咲いたような紋様に
凹凸に富んだ手触りが
不思議な風合いをみせている。
ただ
一枚の布に
何かを包む用途も
どこか心をそそられたようだ。
「これは袱紗というんだ。
剥き出しにしては
よろしくないものを包むものさ。
包まれることで、
金も志になる。」
デリクは、
そっと
袱紗を開いた。
「ふーん
東洋の櫛ですね。
綺麗だなぁ。」
ウィルは
手を出さず、
しげしげと見詰めた。
シャンデリアの灯りを
その真下で受けては
この櫛の真価は出まい。
その予想は的中していた。
螺鈿の煌めきが
月光を弾く。
それでいて夜闇に沈む漆黒の艶なること。
「行灯の灯りに
黒髪。
そこに差されたこの櫛を思うと
ドキッとするよ。」
デリクは
そう説明した。
「みんな黒髪なんですよね。」
金髪に
シャンデリアの光を受けて
ウィルが確かめるように応えた。
「そうだね。
黒髪は女の命だそうだ。」
そういうデリクも
その国に行ったことはない。
ただ
長く真っ直ぐな黒髪が流れる様と
貝殻に入れられた朱を差した唇と
そこに置かれた櫛のイメージに酔うだけだ。
「夜に輝く櫛か……。
ちょっと罪の匂いだな。」
ウィルが
そっと触れようとして
手を退いた。
「罪か……。
そうだね。
むしろ夢かな。
夜は人を夢に誘うからね。
さあ、
君には現実が待っている。」
先ほど
声を掛けてきた女性は
まだ少女といっておかしくない年頃に思えた。
同じ年配の群れに入るでもなく、
ひっそりと壁際に立つ彼女は
なかなか清楚で愛らしかった。
デリクは、
自分は残るからと
ウィルを中へ戻した。
見ていると
そうっと
彼女に近づいていく。
四番目のウィルも
五番目のウィルも
そうして
女性たちの手を取っていった。
一人になると
下から上がってくる薔薇の香りが
むせ返るようだ。
うふふふふ
あはははは
誘う夢は
夜闇に薔薇の香を添えて
像を結ぶ。
流れる髪は金の糸だ。
頬を掠める夜風に
波打つ金髪は横をふわりと抜けていく。
薔薇は咲く。
今を盛りと咲き誇る。
いけないな
夢に誘われる
夜は
人を夢に誘う
昔から
ずいぶん前から
いつの頃からか
この夢は自分を誘っていた。
深い森へ
自分は踏み出したことが
あるのではないか。
今朝方の夢が
何かの啓示のように
思い出されていた。
画像はお借りしました。