この小説は純粋な創作です。
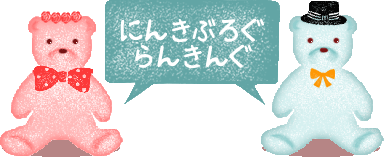
人気ブログランキング
実在の人物・団体に関係はありません。
居間は
不思議なほど小さく感じられた。
背は伸びた。
豪奢な館での華やかな夜会も経験した。
大きな館には違いないが、
片田舎の夏を過ごす別邸の広さは知れている。
それでも体に残る感覚はある。
子どもたち、
大きな従姉たちに従兄たち、
父母に叔父叔母、
庭に置かれたテーブルのおやつを食べながら
窓越しに見ていたここは、
人で溢れていたように思ったのだが……。
窓をゆったりと眺める位置に
ラウンジテーブルが一つ
そして
暖炉の前に設けられたソファーセット
そこに
三人がお茶を楽しもうと進む。
それだけで
この部屋は十分に空間を満たされていく。
ラウンジテーブルには
真っ白なクロス。
ティー・スタンドがスコーンと小振りのケーキ、
そして、
指先で摘まめるほどのサンドイッチを載せて
中央にある。
香ばしい焼き立てのスコーンの香りが
食欲をそそる。
そして、
給仕に立つロバートが注ぐ紅茶が
さっと香り立つ。
ああアフタヌーンティーだ……。
また違う風景が
香りに甦る。
生きた人間の織り成す賑やかな夏だ。
書類にサインするだけ、
ざっと雨風に損なわれた箇所の報告を受け、
その措置をする。
管理責任を引き継ぐことが
この相続のポイントだと考えていた。
根拠は薄弱ながら
〝美〟への傾倒を隠さぬ変人ぶりに目を付けての
相続人指命。
そう考えて
駅舎に降り立った。
丁重にして
事務的な有能な弁護士は
広壮な邸宅の居間に待っているだろう。
白い布を被せた家具は
そこが眠りについた館であることを
語っている。
陽光は
からりと部屋を抜け
一脚だけ布を取り払われた丸テーブルで
自分はサインを済ませる。
言葉にすれば
ざっと
そんなイメージがあった。
が、
館は、
今、
懐古の引き出しに優しく憩う
セピア色のときを生きている。
夏の装いも清々しい紳士と少年は
なんとこの別邸に似合っていることか。
古風なアフタヌーンティーの情景に
ぴったりと嵌まる
美しいピースがそこにあった。
また、
そこに迷い込んだ自分は
どんな顔をしていたらよいのか。
デリクは二人が醸し出す物語めいた情趣に
疎外感と憧憬を二つながら抱えて
戸惑っていた。
書いてみたかった物語が
そこにある。
そのときめきもあった。
が、
タイプライターを前に
髪をボサボサにしたまま唸っているなら
見つめてもいられるが、
きちんと自分もよそ行きのなりで
場を共にするのは、
物語を共にすることだ。
気後れする。
紳士は淑女のため
その椅子を引いて脇に立つ。
グレン・ウェストンは
少年のために椅子を引いた。
そして、
少年は微笑んで腰を下ろす。
その自然な所作に
わけもなくときめくのは
それが美しいからだ。
ロバートが引く椅子に掛けながら
デリクは
身の置き所に困る。
暖炉の上を四角く切り取る
どこか東洋めいた蔓草を象った枠は
大きな鏡を飴色に縁取っている。
四人の人物が
午後のお茶を楽しんでいる様が
ひどく自分とは遠い世界のように
鏡の向こうに見えていた。
目が合ってしまった男は
気恥ずかしげに
目を逸らす。
馬車で
駅舎からやってきたロンドンの香りのする男。
それを迎える主は
古来からの慣わしのままに生活をしている。
自分が
ロンドンの男か……。
そして、
グレン・ウェストンが主……?
名目上の主など
真実を映す鏡の前では
意味をなさない。
グレン・ウェストンは
館を生かし、
自分は
館を眠らせる。
「デリク様、
丘のふもとの別邸に
ウェストン様は夏をお過ごしになられています。
奥様は
もう
ずっと
長いこと
ウェストン様と夏をお過ごしでした。」
給仕を終えたロバートが
テーブルの脇に立つ。
慎ましく
三人の視線が集まるのを待って
老いた守り人は切り出した。
「奥様、
グロリア様が
デリク様を
このバートン邸の主にと
望まれました。
デリク様は
ウェストン様とのお付き合いを
きっと御理解くださる。
グロリア様は
そう信じておられました。」
ロバートの口から
大叔母のクリスチャン・ネームが
さらり
と
滑り出た。
「光栄だね。
ウェストンさん、
よろしくお願いします。」
ここに夏を過ごす。
それだけの付き合いに
この出会いの演出は大袈裟に過ぎる。
それが引っ掛かりながらも
デリクは微笑んだ。
そして、
思った。
大叔母も名前があったっけ。
ロバートは
大叔母をその名で呼ぶのか。
〝大叔母様〟以外に
呼び掛ける名を考えたこともなかったデリクに
それは、
また新たな情景を思い出させた。
グロリア、
そうか
グロリア……。
〝私はね、
このグロリアが
大好きですよ。〟
大叔母は
そう微笑んだ。
ちょっとしたかくれんぼで
遠い支那の国から渡ってきた大きな壺を
ひっくり返したときのことだ。
頭の上に
ずらりと厳めしく並ぶ御先祖様に
小さな頭を並べ
説諭された情景が
脳裏に甦る。
一頻り
あるべきバートン家を語られ
すっかり
シュンとなった辺りで大叔母は
くすり
と
笑ったのだ。
そうして、
え?
と
見上げる悪戯坊主らに
一枚の絵を指し示した。
正装に着飾った当主と
その家族を描いた厳めしい油絵の中に
野に座る老婦人を描いた水彩画があった。
優しい絵だった。
おや?
と
デリクは見回す。
…………見当たらない?
「お待ちください。」
心得たように
ロバートが
壁際に梱包してあった四角い包みに向かう。
梱包はほどかれた。
ああ
この絵だった
スミレの紫が
老婦人のドレスに映える。
野の花は慎ましく愛らしく
老婦人の微笑みは
描く人を見詰めて輝いている。
ほんとだ
素敵なおばあさん
…………綺麗だ。
そう幼心にも思ったものだ。
「グロリア、
ほんとに綺麗だった。
ウィル、
グロリアを愛してた。」
甘く、
愛らしい声が
心地よく響いた。
デリクは
隣に座る庭師に咲かされて
誇らかに花弁を震わせる白薔薇を
振り返る。
うっとりと
少年は
その絵に見惚れていた。
物語めいた少年は
絵にも物語を読むのだろうか。
ウィルとは
誰のつもりなのだろう。
「このグロリアは、
この一族を守った立役者なんです。
すごいしっかり者で
男顔負けだったそうです。
この絵を見ると
とても
そんな風には思えませんけどね。」
そう
少年の描いた物語に応えてから
デリクは
ふと
思った。
「ずいぶん年をとってから
遠縁の大叔母を引き取ったんです。
息子も娘も実子はたくさんいたのに、
この館は大叔母が受け継ぎました。
大叔母も負けずにしっかり者でしたから
一族はいつしか大叔母が支えるようになっていました。
人を見る目があったんですかね。」
デリクは
語りながら
大叔母の説諭を辿った。
〝私はね、
お客様を迎えるために
ここにいるのよ。
私はグロリアですもの。
ここの夏は美しいですからね。〟
そうだ。
そんなことを言っていた。
「グロリア……
素晴らしい女性でした。
お会いできて
幸運だったと心から思っています。」
静かに
ウェストンが応える。
その声に呼ばれるグロリアは、
また
温かな像を感じさせるものだった。
一族の長たる大叔母は、
グロリアという女性だったのだ。
館を受け継いだ
若き日の大叔母が
ひどく身近に感じられた。
「大叔母も
最初は戸惑ったでしょうね。
名前が同じ縁だったんでしょうか。
なぜ自分なんだろうって。
ぼくも戸惑ってますよ。」
思いが
そのまま口をついて出る。
はっと気づくと
グレン・ウェストンが
返事を待つように
自分を見詰めていた。
デリクは姿勢を正した。
「この館は夏の別邸です。
そんなものを持つ柄ではありませんが、
そうなりました。
夏の休暇を過ごすのに
隣人は有り難いものです。
大叔母同様、
親しくさせていただけたら
幸いです。」
「ありがとうございます。
この夏も
ここにおいでになりますか?」
「ええ。
そうですね。
仕事を片付けて
改めて。」
「楽しみにお待ちしています。」
にこやかに
お茶は
終わりを告げた。
夏は
まだ始まりを告げたばかりだった。
画像はお借りしました。
ありがとうございます。
☆えっと
森に棲むもの・晩夏
いきなり?
盛夏飛ばして?
真夏の終わりからってことで
いいか。
とにかく次章に行きます。
章題は〝森に棲むもの〟継続で。
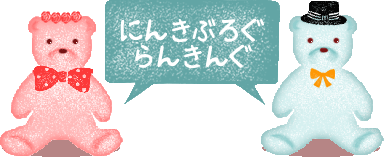
人気ブログランキング

