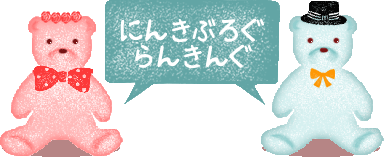この小品は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
陽光がそよぐ草にきらめく。
ザワザワと草は波打つ。
草原はなだらかに丘へと続き
館は緑の絨毯に乗せられた船のように草原を見下ろしている。
……まるでポートレートだ
デリクは
門が占めていた空間に
唸っていた。
厳めしかった門が
大きく開き、
四角い赤褐色のフレームに
咲き乱れる花たちの図が絵はがきのように切り取られている。
気恥ずかしくなるほど
分厚い扉だったはずだ。
それが開け放たれるとこうなるのか。
土の色が
一筆書きに描く道は
その絵はがきに向かう。
小暗い不思議な世界だった小径は
陽光に波頭をきらめかせる緑の海を渡る細い桟橋となった。
ああ暑いな……
でも風が心地良い
ザワザワ
ザワザワ
絶え間ないそよぎにシャツは帆となる。
門をくぐる。
風音は
ぴたりと止んだ。
庭園は花に溢れている。
デリクは
絵はがきの小世界の中にいた。
これは
ちょっとした異世界巡りだな
ふりかえると
門は
揺れる草原の向こうに広がる森
さらにその先のこじんまりした村を切り取っている。
ロンドンのアパート
それは狭いながら奥深い森だ。
タイプライターに向かえば
小暗い森はどこまでも誘う。
そんな毎日が
自分は楽しい。
だが、
こうして体ごと
非日常に飛び込むのも悪くない。
いや
心地良い。
自分が主となった風景は美しかった。
パタパタ
パタパタっ
突然
誰かの足音が
石畳に響いた。
軽い。
そして
走ってくる。
え?
子どもがここにいるのだろうか?
ザザッ……
薔薇の茂みが揺れた。
振り向いたデリクは
飛び出してくる少年を
抱き止めていた。
弾ませた息
その息が洩れる唇は赤く
ふっくらと瑞々しい。
透ける肌
真っ白な肌は仄かなピンクを頬にはいて
生きている輝きを放つ。
瞳は空を映して青く
波打つ髪は日を映して金色に輝く。
ふんわりと広がる白い袖、
その袖口から覗く華奢な指先が
自分の胸に置かれている。
「あっ
ごめんなさい。」
その赤い唇は動いた。
甘く可愛い声が
その唇から発したものと気づいたのは、
少年が不思議そうにデリクを見上げてからだった。
木偶のように
少年を抱いて見下ろしていた自分に気づき
デリクは慌てた。
「どういたしまして」
急いで
だが
礼を失しない程度にゆっくり
デリクは身を離した。
「アベル
ご挨拶をしよう」
薔薇は
次の登場人物を
その花影から生み出していた。
少年の肩を抱いて
デリクに向き合う男は
麻のスーツがしっくり似合っていた。
そして、
呆れるほどに美しい。
男神を象った彫像の一つが
命をもって動き出したかのような
彫りの深い顔立ちだ。
額にかかる褐色の髪が
やや濃い色のためだろうか。
陰影に富んだ造作のためだろうか。
憂愁が漂う顔立ちでもあった。
「デリク・バートンです。
この館の主です。
お二人は、
大叔母のご友人ですか?」
デリクは
変わり者と一族の認定を得てはいたが
偏屈という意味ではない。
少々ロマンチックに過ぎるし
引き込もって物書きなど若者のすべきことだはない。
そんな意味合いのことだ。
ごく普通の上流階級の若者で
30にもなって結婚していないのは一族の悩みの種だが、
すでに一人立ちもしている。
そして、
この館の主は自分だった。
これは…………絵だ。
美しい庭園
そこに遊ぶ天使
その絵を自分は見詰めている。
そんなロマンチックに浸りたくもなる出会いだったが、
現実はそう単純にはいかない。
「はい。
今日は
あなたがいらっしゃるということで
お待ちしていました。
グレン・ウェストンと申します。」
麻のスーツは
別邸の住人の証だ。
村人ではない。
開け放された門は
自分のためと思っていたが
この友人に自由な出入りを許すという意味なんだろうか。
「わたしを待っていた?」
「ええ」
デリクは、
思い迷いながら
二人を見つめた。
キイイイイイイッ……バタン
はっ
と
振り向くと
ロバートが門に閂をかけているところだった。
館は門を閉じ、
二人は特別な存在であると決まった。
「デリク様、
グレン様、
アベル様、
お茶の用意ができました。」
ロバートが厳かに宣言する。
花々は香る。
花を愛する住人の心映えが
品位の中にも無邪気に溢れていて
庭は美しい。
この二人は
いったい誰なんだろう。
そして、
確かに過ごした館での夏が
いったい
どう終わったのか。
記憶に残る風景の中に
何かをもどかしく探し求めながら
デリクは
改めて見惚れていた。
グレン・ウェストンは
少年の肩を抱いて
ごく自然に館へと歩き出している。
美しい絵だった。
本当に美しい。
「ねっ
黄色い薔薇も、
可愛いでしょ?」
くるくると波打って流れる金髪が
甘えて見上げる背に揺れ、
その横顔は花よりも愛らしい。
男が返す微笑みは
愛しさに溢れ
なぜか憂愁を深めて端正だ。
なぜ僕なんだろう……。
その疑問が
すとんと重さを増した。
そこに
すべての答えがある。
二人に続きながら
いつしか
デリクはそう感じていた。
画像はお借りしました。