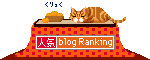この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
ホテルは
朝の支度に動き出した。
朝まだき、
まだ夜は明けきらぬ。
ムクリ……。
小さな影が
ベッドの掛布からピョコンと頭を覗かせた。
脇に横たわる影に身を屈め
しばらく寝息を窺う。
影は
じっと動かない。
よし!
と
小さな手が伸び上がり
くいっと呼び鈴を引いた。
パサッ
と
また掛布を被り
大きな影にピタリと寄り添う。
そんなことでは、
気づかれてしまうとは
小さな影は思わないらしい。
大きな影は
静かに動かない。
カチャリ……。
あるかなきかの音が
リビングに誰かが入ってきたことを告げる。
カサカサ カサカサ
リビングから誰かの気配がした。
そうして、
また
カチャリ……。
ゴソゴソ……と小さな影はベッドを這い下りる。
ぺトンと床に尻をつくと、
今度は小走りでリビングに通じるドアに向かう。
パタン!
そのドアが閉まると同時に
ベッドには
もう一つの影が起き上がった。
足下には
可愛らしいピンクのスリッパが残っている。
裸足で……。
冷たいだろうに
グレンは
ほうっ
と
ため息をつく。
カチャリ……。
出て行った時は
パタン!
と
無造作に閉めたドアが
息を殺すように
そうっと開けられた。
金髪の巻き毛が
居間に差し込む日を受けて
フワンと浮かぶ。
そうっと覗き込むのは
クリスマスに舞い降りた天使らしい。
リボンを掛けた可愛らしい包みを
大事そうに抱いている。
グレンは
目を閉じている。
ウフン
と
満足気に笑うアベルの声に
危うく笑い出しそうになったが
グレンは耐えた。
ヒタヒタと
裸足の足が
部屋を渡ってくる。
枕の後ろに
その包みは隠され
アベルは
またベッドに潜り込む。
もう限界だった。
すり寄る体を
そっと抱き締める。
きゃっ
と
上がる悲鳴を
キスで押さえる。
「い、いつ起きたの?
黙ってるなんて……。」
長くなりそうで、
またキスで封じる。
今度は長い。
文句を甘く蕩かすまで続ける。
「Merry Christmas!
アベル」
そうして、
優しく挨拶した。
「Merry Christmas!
グレン」
甘い声が
返される。
そう
もう内緒の時間は終わった。
アベルは元気に起き上がり、
続いて起き上がるグレンはガウンを着せかける。
「ありがとう」
ガウンに手を通すのも
気もそぞろの〝ありがとう〟も
枕の下から
大事なプレゼントを引っ張り出しながら。
アベルは
プレゼントに夢中なのだ。
アドベントカレンダーは、
もう
最後の窓まで全開で
25人の天使が勢揃いしている。
どうやら
こそこそ動き出す前、
一番最初に開いたらしい。
クリスマスの朝が来た!
プレゼントの時間だ!
そういうことらしい。
寝室の厚いカーテンも
日差しが隙間を抜けてくる。
明るくなるときは早いものだ。
グレンは
そっと呼び鈴を見上げた。
手を伸ばそうとして……躊躇う。
思い切ったように、
アベルを抱き寄せた。
「アベル、
プレゼントは
居間で開こう。
クリスマスのご馳走もある。
二人で祝いたいんだ。
…………お願いだ。」
ん?
食堂じゃないのかな?
と
驚くアベルを感じ、
グレンはアベルの顔を見られない。
最後の〝お願いだ〟には力がなかった。
頬に触れる小さな手を感じ、
グレンはそっとアベルの顔を見る。
「あのね、
クリスマスは、
大切な人と祝うんだって。
グロリアがね、
そう言ってたよ。」
その眸は
キラキラと輝く。
〝そうだ!
そうなんだね!〟
子どもが
分かった!と快采を上げるように
その眸には納得があった。
グレンは、
呼び鈴を引き、
アベルに着替えをさせた。
久しぶりの少年の服だった。
たっぷりのフリルがあしらわれたシャツに
細身のフロックコート。
アベルは部屋と聞いたことで納得しているようで、
コルセットを着けずに済むことを歓迎した。
グレンがドアを開ける。
「わぁ……!」
アベルの嘆声が上がる。
居間には
テーブルいっぱいに
クリスマスのご馳走が並んでいた。
アベルお気に入りのシャンパンも
冷やされている。
暖炉は赤々と燃え
支配人の心尽くしが小卓に置かれた可愛らしいキャンドルに
灯っていた。
「これが七面鳥?
初めて食べるよ、ぼく。」
アベルは
嬉しそうに一口食べ、
〝美味しいね〟
と
グレンに笑いかける。
一つずつ
二人は〝美味しいね〟を分けあった。
クリスマスは二人のものだった。
「あのね、
プレゼント
ぼく
見てもらいたいな。」
食事は、
プディングを残すのみだった。
グレンは微笑む。
パッとアベルの顔が輝き、
いそいそと
プレゼントを差し出した。
何にしたんだろう。
写真は燃やしたはずだが……。
手触りは額縁のように感じられた。
畳んだナプキンほどの大きさのポートレート?
アベルは
リボンを解く手元を
じっと見つめている。
開けてみて
グレンは目を見張った。
深緑のドレス姿に
生き生きと輝く眸のアベルが
誰かを見上げている。
これは……。
「あのね、
ぼくがグレンを見ているところなんだって。」
とすると、
昨夜ウィルはこれを描いていたのか。
見事な水彩画だった。
自分を見つめるアベル……その眸の輝きに
グレンは言葉がなかった。
「どう?」
黙り込んだグレンに不安になったように
アベルが覗き込む。
グレンは
また滲みかけた涙をぐっと堪え
微笑んだ。
「嬉しいよ。
アベル、
どんなに嬉しいかしれない。」
ウィルに感謝の言葉を言い残せないのが
残念だった。
グレンは、
そっと小さなビロードで覆ったケースを
テーブルに置いた。
「わたしからのプレゼントだ。
アベル、
君に贈りたい。」
「わぁ
ありがとう!」
プレゼントが成功したアベルは、
にこにことケースを開けた。
不思議そうに取り出したのは、
銀の鎖を通した白い角笛のような形をしたペンダントだった。
「アベル、
それはね、
昔私が身に付けていたお守りだ。
私は
それを父から受け継いだ。
一族の守りなんだそうだ。」
「え?
そんな大切なもの……。」
グレンは
そっとそれを取り上げ
アベルの後ろに立った。
アベルの首にかけ
留め金を留める。
「このお守りが
君を守ってくれますように」
静かに
そう言い切る。
そして、
グレンは
アベルの横にひざまづいた。
「どうしたの?」
驚くアベルの手を取り、
グレンは静かに
その眸を見つめた。
「アベル
私は
君の気持ちを待たずに
こうして君を連れ出した。
君は
私を許してくれるだろうか?」
グレンの声は
静かに
落ち着いていた。
許されないことを覚悟したことが
グレンを変えていた。
「え?
あの……許すって……。
ぼく、
もう許してるよ。
消えちゃうのを止めたとき、
許してるよ。」
アベルは
戸惑いながら
応えた。
グレンに取られた手が
もじもじとする。
アベルにとって、
自分が館を出てきたことも
グレンに生かされていることも
もう既に定まったことだった。
グレンは
どこか哀しげな眼差しで
そんなアベルを見つめる。
「アベル、
私たちは
もう
このホテルを立たなければならない。」
グレンは
ゆっくりと告げた。
「あっ、
それじゃ、
グロリアとウィルに
さよならしなくちゃ。」
アベルは屈託がない。
仲良しの二人は
アベルにとって特別な存在だ。
「できない。
私たちは
そっと旅立つ。
これからも、
どこに行っても、
誰と知り合っても
そっと旅立っていくんだ。」
グレンは間髪を入れず返した。
返して、
アベルをじっと見つめた。
アベルの唇は
開こうとして……ゆっくりと閉じた。
グレンは
昨夜感じた不思議な色を
アベルの眸に見た。
アベルは
手を取らせたまま
そっとグレンの唇に唇を重ねた。
唇を離すと
そっと手を抜き取り
胸のペンダントを大切そうに押さえる。
グレンが
さらに言葉を継ごうとした。
すると、
ぱっとアベルは視線を上げる。
「ねぇ、
クリスマスだよ。
大切な人と祝うんだよ。」
アベルは
クルクルッ
と
悪戯っぽく眸をきらめかせた。
グレンの手を握り返し
クリスマスプディングに目をやる。
ポウッ……。
プディングは揺らめく炎に
仕上げられた。
切り分けて
クリームを添え
クリスマスの特別なケーキは
美味しく食べられた。
ホテルの時間は
クリスマスディナーのランチタイムとなった。
階段は、
明るいざわめきに包まれ、
ざわめきは食堂へと流れる。
客たちは
てんでにツリーの下のプレゼントを選んでは
席に着いていった。
さあ
あとは
お待ちかねの二人を待つばかり。
客たちは
てんでにプレゼントを開いては
例年よりだいぶ可愛らしい中身に
さざ波のように笑い声をあげていく。
さあ
誰のがあたったかしらね
ああ私のは違うな。
おっ
と
ざわめく声に一同が入り口を振り返った。
バートン夫妻と支配人が
話しながら
入り口を抜けてくるところだった。
その後ろには誰もいない。
キョロキョロ
と
見回す食堂の面々に
バートン夫妻は目を合わせ、
バートン子爵が一歩前に出た。
集まる視線に
ウィルは
堂々と
かつ
残念そうに語った。
「いや
皆様
ウェストン夫妻は
旅立たれました。
如何ともしがたい急用でしてな。
私どもも
これはお見送りするしかないと
思った次第です。
あ、
ですが、
ちゃんとプレゼントは
選んで行かれましたよ。
細い赤のリボンに
手のひらに乗るくらいの可愛らしい丸い包みを奥様が、
太い緑のリボンに
肘ほどの長さの細長い包みをウェストン氏が
選んで行かれました。
幸運なお方は
どなたかな?」
まあ!
と
はしゃぐご婦人二人の声に
食堂は
賑わいを取り戻した。
ここは
それぞれが
それぞれの事情で集まる優しい隠れ家だ。
客たちは
納得していた。
色々なことがあるものだ。
そして、
このクリスマスは彩りあるものだった。
とびきり美しい二人の夢のような物語。
それは
終わりが来るから美しい。
グロリアは
堂々とした夫を惚れ惚れと見つめ
ウィルは
最愛の妻に腕を差し出す。
いつもの席に着くと
支配人が
慇懃に礼をした。
「お二人に
感謝していると
仰有っていました。」
小声の囁きに
二人は頷く。
「Merry Christmas!
グロリア」
「Merry Christmas!
ウィル」
二人は
微笑み合った。
若い二人には
なかなかの事情がある。
これは、
二人とも予想していた流れだった。
くすっ
と
グロリアが笑う。
「ウィル、
あなたって
本当に頼りになるわ。
私は幸せ者よ。」
「君こそ
本当に素敵な女性だ。
私は君を愛することができて
幸せ者だよ。」
老夫婦も
また
クリスマスの奇跡を幸せに思っていた。
「ねぇ、
グレンは
どうしたかしら?」
グロリアは囁く。
「覚悟を決めたさ。
私も決めたんだからね。」
ウィルは囁き返し、
グロリアは頬を染めた。
幸せに
幸せに
小さな街のクリスマスは
優しく終わりを告げた。
画像はお借りしました。