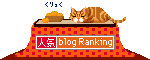この小説は純粋な創作です。
実在の人物・団体に関係はありません。
静かな時間の内に
昼食は近づいていた。
「ああ
アリス
どうしたかしら。」
やきもきするグロリアの横で
ウィルは見事な手捌きで
紅茶を二つのカップに注いだ。
「さあ
カモミールにしたよ。
落ち着いて。」
ウィルは
カップを愛しい女性の前に置き、
優雅にそれをすすめた。
グロリアは
恨めしげに見上げため息をついたが、
習慣というもので、
手はカップを取り上げる。
鼻をくすぐる優しい香りに
しばし香りを楽しむと
向き合って紅茶を楽しむウィルを見つめた。
夫は
もう一口めを楽しんでいた。
「グロリア、
紅茶は
君が教えてくれた幸せの一つだ。
さっき
グレンにそう言ったんだよ。」
ウィルは静かに切り出した。
グロリアは
はっと目を上げた。
「アリスにね
教えられたよ。
ただそばにいるだけじゃ
だめなんだ。
そう思った。」
ウィルは
いつしか声を低くすることを
止めていた。
それが余りに自然で
グロリアは
このときまで気づかなかった。
そう
えっと
さっきだわ
アベルを連れていくとき
……私、泣き出してしまった……。
騒ぎが起きたとき、
グロリアは泣いたことがなかった。
落ち着き払って先頭に立ち、
まず笑ってみせる。
それが
もう身に付いてしまい
自分が泣くということが
まず驚いた。
「ウィル……。」
私、
本当は怖かった。
どうしていいか分からなかった。
夫は落ち着いていた。
何より…………私を守ろうとしてくれていた。
〝お前はここにおいで〟
優しい声音が思い出される。
グロリアは、
初めて出会う姿に戸惑いながら
そのウィルがいつも側にいてくれたウィルであることを
しみじみと感じていた。
ウィルは
ひどく静かな眼差しをしていた。
「グロリア、
私はウィルだ。
生まれたときからウィルと
呼ばれてきた。
ただね、
あのときは、
ウィルと名乗るつもりはなかったんだよ。」
白髪が緩やかに波打つ。
目尻の皺は優しい眼差しを
思いを重ねた年月に支えるようだ。
静かな
でも
熱い眼差しだった。
「わたしはね……」
「待って!」
優しく続けようとした言葉を
グロリアは制した。
ウィルは
静かに
言葉を止めた。
ふうっと息をつき、
グロリアは目を上げた。
「あなたは〝ウィル〟。
私の愛する人。
私には
それで十分なの。
ウィル
だから教えて。
あなたはどう?」
グロリアは
ウィルの過去を聞くのが怖かった。
ただ、
今の思いだけを知りたかった。
「グロリア
私に
そんな資格があるか分からない。
ただ、
君に〝ウィル!〟と呼ばれたときから
私は君の虜だ。
幸せな虜だ。
この三年間は
それまでの人生すべてと引き換えても及ばない。
幸せな幸せな時間だった。」
「ウィル、
…………子供達はもう巣立ったわ。
私、
初めて恋をした。」
グロリアは
テーブルに置かれたままの辞書に
目を落とした。
古びた革の装丁、
ずっしりと分厚い
それを開こうとすると、
表紙にかかる自分の指が皺だらけで
それが
グロリアを躊躇わせる。
グロリアは
うつ向いたまま
自分の指を眺めた。
なんだか
自分の背が丸くなり
とても小さくなっていくように感じた。
その手に
温かい手が乗せられた。
その手も優しい皺が刻まれていた。
「グロリア、
私もだよ。
君は、
きらきらした蝶々みたいに
私の人生に飛び込んできた。
素敵なグロリア
私は
君の〝ウィル〟でいていいんだろうか。
わたしは…………バーンズと名乗るつもりだった。
ケチな株券で稼ぐつもりだった。
私は詐欺師だった。
この三年間、
私が恐れたのは
いつ本物のウィルが現れるだろうということだった。
君を……愛したから。
とても愛してしまったから。」
パタン……。
パタン……。
茶の重々しい装丁に
涙の雫が落ちた。
グロリアは、
そっと
最初のページを開いた。
ぐっ
と
息を呑む音がした。
見上げると
ウィルの視線が吸い付いたように
菫を見つめていた。
ウィルの手が
そっとページを繰っていく。
グロリアは
その様子を見つめた。
はらはらと
涙が溢れては零れた。
一つ一つ
グロリアは覚えていた。
一つ一つ
ウィルも覚えていた。
グロリアは
そっと立ち上がり
ウィルの横に座った。
ウィルは
まだ
花たちを見詰めていた。
ウィルの眸にも
光るものが溢れようとしていた。
グロリアは
ウィルの唇にそっと唇を重ねた。
初めて重ねた唇が
とても優しいもので
グロリアは驚いていた。
ウィルが
肩に手を回すと
グロリアはときめいた。
抱き寄せられ
深くキスを交わすと
蕩けるように幸せが心を満たした。
そして、
キスが終わると
グロリアは宣言した。
「ウィル、
わたし心配でたまらないの。」
ウィルは
にっこりと微笑んだ。
「写真を預かってるんだ。
それを届けることはできるよ。」
昼食は間もなくだった。
大人の恋人たちは、
午後の作戦を考え始めていた。
画像はお借りしました。