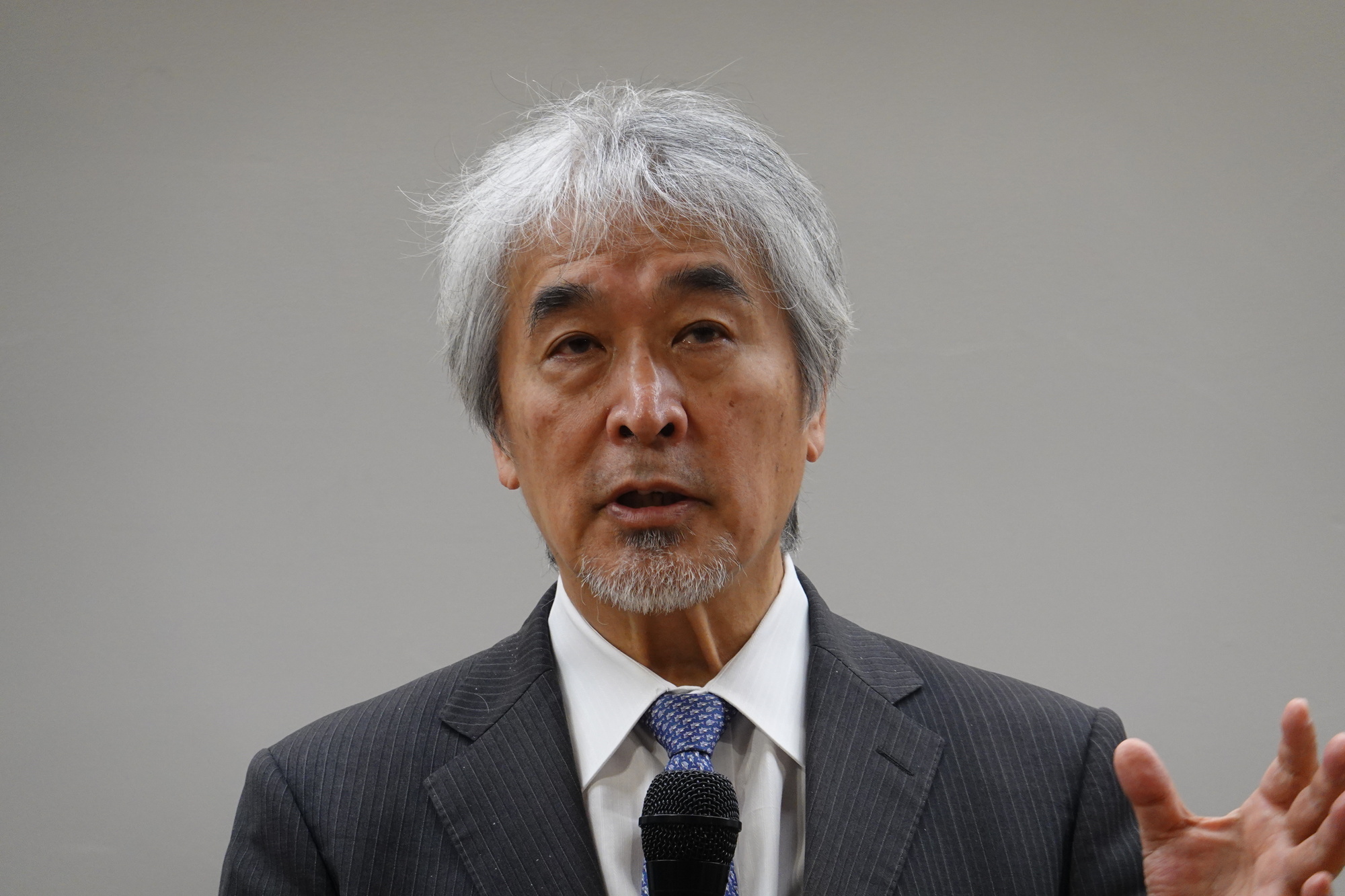おはようございます!
sunyoheiですo(^o^)o♪
「人類の脳の大きさの進化」について面白い記事を読んだので、以下、自分なりの備忘録です。(興味がない方は無視してください。ちなみに妻にはまったく響きませんでした…)
現代人の脳はゴリラの約3倍もあるそうです。しかし、200万年前までは人類も同じ大きさでした。
では、その大きさの差はどうして生まれたのか?ということについては様々な研究が行われているのですが、その中で「脳の大きさとその種が暮らす集団の規模は比例する傾向にある」ということがわかっているそうです。
脳の大きさがゴリラと同じ500ccだった頃、人類の祖先は10〜20人の集団で生活をしていました。
この頃はまだ人類は言葉を持っておらず、言葉を介さなくても意思疎通をしてスムーズに動ける人数がこれくらいだったということです。
ずっと一緒に住んでいる気心の知れた親戚たちだったわけです。
現代では、意思疎通をしてスムーズに連動するスポーツチームの人数の上限がこれくらいですよね。(ラグビー15人、サッカー11人など)
その後、狩猟採集生活をより安定させるために親戚以外の人たちと同じ集団で暮らすようになり、集団人数が30人、50人、100人と増えていき、狩猟採集生活の終わり頃には150人にまでなっていたそうです。
そして、それに連動するように脳の大きさも大きくなっていったのです。
これは、集団にいる親戚以外の人たちの特徴や性格を理解しながら自分がどう振る舞うかを判断するようになったことが影響していると考えられています。
つまり、場の空気を読んだり、他人を慮ることが脳を進化させたと考えられるのです。
ちなみに、150人というのは「仲間」として認識できる人数の上限だそうです。
ここで「仲間」と言っているのは、一緒にスポーツをしたり、歌を歌ったり、プロジェクトに取り組むことで喜怒哀楽を共にし、何かトラブルや悩みを抱えた時に「これはあの人に相談してみよう」と顔が浮かぶレベルの認識を持っている人たちのことです。
現代でいうと、スマホの連絡帳に登録されていたり、年賀状をやり取りしている人たちといったところでしょうか。
さて、人類はその後、言葉を使うようになり、農耕牧畜が始まって、何千人、何万人という集団の中で暮らすようになります。
しかし、それ以降、脳の大きさは変わっていないそうです。
人数が多すぎると同じ集団の人と認識しづらいということもあるのだと思います。
また、生き残るために必要なのは「考えること」ではなく「察すること」だったので、そちらの能力のほうが遺伝子に働きかける力が大きかったということもあるのかなと思いました。
それにしても、いろんなことを調べて、これだけのことがわかるというのは凄いことですよね。
何万年も前の人類のことなんて、決して多くはない化石や遺構から情報を収集するだけでも想像を絶するのに、「集団が何人だったか?」とか「脳の大きさはどれくらいだったのか?」といったことを導き出し、更にそれらの相関関係を考える。
そんなことができちゃうんだ!という驚きと、その結果を共有して驚ける喜びを感じることができました♪