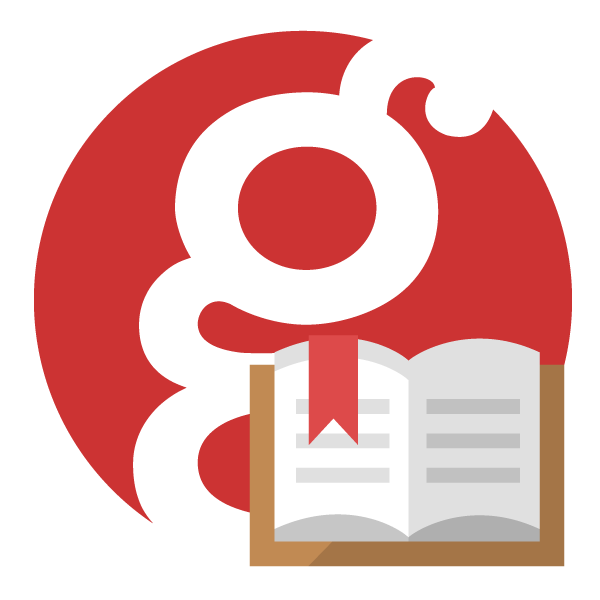今回の英文
例1
He's a great talker but he never does anything.
よくしゃべるが何もしない
出典:『英和活用辞典』
a great talkerは辞書などでは"熟語"として「おしゃべりな人」「多弁な人」という意味ばかりが載っていることが多いようですが、果たして常にその意味で使うのでしょうか。今回はこの点について考えていきます。
「おしゃべり」の意味でない例
さっそくですが、反例です。以下の例では、great talkersは「おしゃべり」「多弁」の意味で使われていません。
例2-1
Reagan, Clinton and Jobs are not known as just great talkers they are known as good communicators.
出典:Fortis Leadership
※not only[just]...but alsoの構文。後述の補足参照。
※試訳:「レーガン、クリントン、ジョブズは単にトークスキルがある人物としてだけではなく、優れたコミュニケーション能力のある人物としても知られている」
というのも、たとえばですが、引用元ではこの英文の直前に次のような記述があります。
例2-2
Certainly, these well-known leaders must have had the formal media training and understood the need to focus and stay on message, use good grammar and use good delivery skills. All of this is important for someone to develop credibility as a leader. Yet, I believe these leaders had an additional skill set.
出典:同上
※thisはto focus and stay...skillsの箇所での内容をひとまとめにして指していると思われます。後述の補足参照。
※試訳:「たしかに、これらの著名なリーダーたちは正規のメディアトレーニングを受けて、(そのトレーニングの結果として、)伝えたい内容に焦点を合わせて話を脱線させずに、適切な文法を用い、なおかつ優れたデリバリースキル(≒スピーチ術)を発揮する必要性を理解していたのは間違いないだろう。これらすべて、リーダーとしての信頼性を高めるためには重要なものだ。しかし、こういったリーダーたちにはまた別のスキルもあったとわたしは考えている。」
この部分をみるだけでも、元の文章での話題は明らかに「話術」や「コミュニケーション」であって、おしゃべりかどうかという話ではないことが分かります。だとすれば、例2でのgreat talkersはやはり「おしゃべりな人」「多弁な人」などの意味ではなく、「高いトーク力がある人」とか「優れた話術をもつ人」といった意味で使われている、とみるのが自然でしょう。
今回の英文から学ぶべきことは、辞書などに載っている「熟語」や「成句」と呼ばれるものは、あくまでも複数ある解釈のうちの一つの可能性にすぎないということですね。とくに、熟語がカンタンな単語で構成されている場合は注意が必要だと思います。なにせ、(見かけは)カンタンな単語はほぼ多義語ですから・・・。
「大の・・・」の意味になるときの条件はある?
ところで、今回みたgreatは「大の・・・」という意味として記載されている場合が多いようですが、このgreatはどういうときに使われるのでしょうか。ついでに、この点も見ておこうと思います。
まず、この用法のgreatの直後にどんな名詞がくるかについて、辞書などからザッと拾ってみると次のようになりました。
例3
a great admirer of...(...の愛好家、...の崇拝者)
a great believer in...(...の信奉者、大いに...を信じる人)
a great eater(大食家)
a great fan of...(...の大ファン)
a great friend(大の友達、親友)
a great hater of...(大の...嫌い)
a great lover of...(大の...好き)
a great leader(大指導者)
a great reader(大の読書家)
a great scoundrel(大悪党)
a great smoker(ヘビースモーカー)
a great sleeper(よく眠る人[子])
a great talker(大のおしゃべり)
-er形が多いことはすぐ分かりますが、これらの特徴について参考になる指摘があります。
[程度表示の可能な, 人を表す名詞を限定して]大の, 真にその名にふさわしい
出典:『ジーニアス英和大辞典』
なるほど、smokerならa heavy smokerと表現できるので、a great smokerともいえるということでしょう。ほかにもloverならa big lover[hater] of...という言い方ができるので、a great lover[hater] of...ともいえるということですね。
friendやscoundrelは少し毛色がちがいますが、a close[best] friendといえば親密さの程度を表せますし、またa big scoundrelという言い方もあるようなので、やはりジーニアスの指摘通りといえそうです。
greatを用いれば、それぞれの名詞につける「程度」を表す語が微妙に異なるという点を気にしなくていいのはメリットですね。
例2-1の補足
最後に補足です。かなり長くなるので適宜読み飛ばしてください。
まず例2-1について。
例2-1(再掲)
Reagan, Clinton and Jobs are not known as just great talkers they are known as good communicators.
出典:Fortis Leadership
※試訳:「レーガン、クリントン、ジョブズは単にトークスキルがある人物としてだけではなく、優れたコミュニケーション能力のある人物としても知られている」
これはいわゆる"not only[just]...but also"の構文で、talkersとtheyの間のbut alsoが省略されたパターンと考えられます。わかりにくければ、 they are knownを削除したうえで...not known as just great talkers, (but also) as good communicatorsと補ってみるといいかもしれません。
この省略については『ウィズダム英和辞典』に以下の記述があります。
[コーパス]構文の多様性 後半部のbut (also)が省略されることが3割、前半部のnot onlyが省略されることが2割程度ある。(後略)
出典:『ウィズダム英和辞典 第3版』
例2-2の補足
つぎに例2-2について。
例2-2(再掲)
Certainly, these well-known leaders must have had the formal media training and understood the need to focus and stay on message, use good grammar and use good delivery skills. All of this is important for someone to develop credibility as a leader. Yet, I believe these leaders had an additional skill set.
出典:Fortis Leadership
※試訳:「たしかに、これらの著名なリーダーたちは正規のメディアトレーニングを受けて、(そのトレーニングの結果として、)伝えたい内容に焦点を合わせて話を脱線させずに、適切な文法を用い、なおかつ優れたデリバリースキル(≒スピーチ術)を発揮する必要性を理解していたのは間違いないだろう。これらすべて、リーダーとしての信頼性を高めるためには重要なものだ。しかし、こういったリーダーたちにはまた別のスキルもあったとわたしは考えている。」
(1)第1文の全体構造
全体は、M1+S+must have+V1+Obj1 and V2+Obj2+M2 という構造で、各要素は次のようになっています。
M1: Certainly
S: these...leaders
V1: had
Obj1: the formal media training
V2: understood
Obj2: the need
M2: to focus and stay(V'1)..., use(V'2)...and use(V'3)....
V1とV2はandによって並列されている過去分詞。また、V'1とV'2とV'3もandによる並列で、M2全体はObj2にかかる形容詞用法の不定詞のカタマリになっています。
(2)focus and stay on message
この箇所は、focusをA、stayをB、on messageをCとすると、(A+B)C=AC+BCという構造。
第1文でおそらく一番厄介なのがこのon messageという部分です。いくつか辞典から引いてみると次のようなものが挙げられていました。
on/ off message (of a politician)
stating/not stating the official view of their political party
出典:OALD(9th ed.)
※試訳:「所属政党の公式見解を述べて/述べないで」
on message 公式見解に沿って(↔off message)
出典:『オーレックス英和辞典 第2版』
on message
Following a planned set of remarks or positions.
出典:American Heritage Dictionary
※試訳:「事前に決められている見解や立場に従って」
これを見るに、政治的な場面で使うものとして扱っているものが多いようですね。しかし「政党の公式見解に沿って」という解釈だと文脈に合いません。というのも、例2-2の引用元での話題は政治上の演説力だけに限っているわけではなく、もっと一般的なプレゼン力のことを言っているからです。
そこで参考になるのが以下のリンク先。
https://ja.hinative.com/questions/10767617
ここでは、質問者がLet’s stay on message.の意味は何か尋ねて、解答者はLet's stick to the story.とかStick to the point.のような意味だと答えています(stick to the pointについては以下を参照)。
おそらくこの解釈が正解でしょう。つまり、例2-2でのon messageは「話の要点から脱線しないで」とか「話の要点に沿って」という一般的意味で、それに「...のままでいる」の意のstayが加わったのがstay on messageということです。結局のところ、これも一見"熟語"に見えて実は違うということになるのでしょうか。
以下の記事ではstay on messageが同じ意味で使われているようなので、参考までに貼っておきます。
(3)All of this
例2-2(再々掲)
Certainly, these well-known leaders must have had the formal media training and understood the need to focus and stay on message, use good grammar and use good delivery skills. All of this is important for someone to develop credibility as a leader. Yet, I believe these leaders had an additional skill set.
出典:Fortis Leadership
※試訳:「たしかに、これらの著名なリーダーたちは正規のメディアトレーニングを受けて、(そのトレーニングの結果として、)伝えたい内容に焦点を合わせて話を脱線させずに、適切な文法を用い、なおかつ優れたデリバリースキル(≒スピーチ術)を発揮する必要性を理解していたのは間違いないだろう。これらすべて、リーダーとしての信頼性を高めるためには重要なものだ。しかし、こういったリーダーたちにはまた別のスキルもあったとわたしは考えている。」
第2文の文頭All of thisのthisは、第1文のfocus...skillsを不可分のスキルと筆者が見なして一纏めに指していると考えられます。
例2-1(再々掲)
Reagan, Clinton and Jobs are not known as just great talkers they are known as good communicators.
出典:Fortis Leadership
※試訳:「レーガン、クリントン、ジョブズは単にトークスキルがある人物としてだけではなく、優れたコミュニケーション能力のある人物としても知られている」
また、この直後にくる英文が例2-1なのですが、ここでいうgreat talkersが持つスキルこそがfocus...skillsの部分で言及されているものであることが文脈から判断できます。具体的には以下のような感じです。
ステップ①
例2-2において、Certainly...Yetの呼応関係から考えて、筆者が主張したいのはto focus...skillsの内容ではなく、Yet以下にあるan additional skill setである
ステップ②
例2-1のnot just...but alsoの構造から考えて、筆者が重要視しているのはgreat talkersではなくgood communicatorsである
ステップ③
上の①②から対応関係は
to focus...skills ≒ great talkersのスキル
an additional skill set ≒ good communicatorsのスキル
である
このような対応関係があることからも、例2-2の第1文のfocus...skillsをまとめて一つのスキルと見なしthisと呼んでいるのにはちゃんとした理由があることがうかがえます。
ちなみにですが、指すものが可算名詞であるとき、all of thisとall of theseではニュアンスに違いがあるようです。以下のリンクのBill Rosmusという回答者の挙げている例が分かりやすいので、興味のある方は読んでみてください。カンタンに言うと、複数の箱(boxes)を指してall of thisというときはその複数ある箱すべてを指すのに対し、all of theseというときはすべての箱ではなくその中の一部の箱(複数の箱)を指す、という話です。
まとめ
今回は本編の内容は大してなかったのですが、一応ささやかながらまとめておきます。
a great talkerは少なくとも以下の2つの解釈ができる
①「優れた話し手」という文字通りの意味
②「おしゃべりな人」「多弁な人」
最後までお読みいただきありがとうございました。