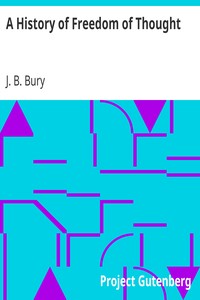今回の英文
(1)
IT is a common saying that thought is free. A man can never be hindered from thinking whatever he chooses so long as he conceals what he thinks. The working of his mind is limited only by the bounds of his experience and the power of his imagination. But this natural liberty of private thinking is of little value. It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours. Moreover it is extremely difficult to hide thoughts that have any power over the mind. If a man’s thinking leads him to call in question ideas and customs which regulate the behaviour of those about him, to reject beliefs which they hold, to see better ways of life than those they follow, it is almost impossible for him, if he is convinced of the truth of his own reasoning, not to betray by silence, chance words, or general attitude that he is different from them and does not share their opinions. Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts. Thus freedom of thought, in any valuable sense, includes freedom of speech.
出典:John Bagnell Bury, A History of Freedom of Thought
今回の英文は、A History of Freedom of Thought の冒頭段落から。そこまで入り組んだ文はないので簡単そうに見えますが、正確に解釈しようとすると結構難しいです。今回はあまりに長文になってしまったので、いくつかに分割して投稿していきます。
なお、こちらは著作権切れの作品を扱うProject Gutenbergの蔵書なので大丈夫とは思いますが、もしも問題があった場合には記事を非公開または削除する場合があります。
各文の解釈
長いので一文ずつに分けてやっていきます。各文のポイントとなりそうな部分を取り上げていますが、必ずしも正しいとは限りませんので、悪しからずご了承ください。また(1)と出典が同じものは省略してあります。
(1-1)
IT is a common saying that thought is free.
<Point 1>文全体
itはthat以下を指す形式主語構文。
<Point 2>a common saying
「ありふれた[よく使われる]言い習わし」の意。
<試訳>
「思想は自由だ、とはよく言われることである」
(1-2)
A man can never be hindered from thinking whatever he chooses so long as he conceals what he thinks.
<Point 1>主節全体
主節はA man...choosesまで。can neverは可能性が全くないということなので「...ということは決してない」といった訳が妥当です。
また、受動態が分かりにくい場合は、主語を適当に設定して能動態に変換すると大意がつかみやすくなります。たとえばこの場合は、No one else can ever hinder a man from thinking...「人が...を考えることを妨げることは、ほかの誰にも決してできない」とか、Nothing can ever hinder a man from thinking...「人が...を考えるのを妨げることは、何であっても決してできない」のような感じです。never = not+everなので、否定語主語とeverに分解するのがミソでしょうか。
<Point 2>thinking whatever he chooses
そのまま訳すと「選ぶものがなんであれ、それを考えること」。この場合、何をchooseするのか明確には書いてませんが、考えるテーマや内容をchooseするということでしょう。とすると、chooses to thinkのように補って解釈するのがよさそうです(この場合、choose ≒ decide)。よって直訳は「考えようと決めたものが何であれ、それを考えること」
<Point 3>so long as SV
as long as SV「SがVする限り」と同じ
<試訳>
「考えていることを表に出さない限り、何を選んで考えようとも、それが妨げられることは決してない」
(1-3)
The working of his mind is limited only by the bounds of his experience and the power of his imagination.
<Point 1>The working of his mind
直訳だと「心の働き」とか「精神の作用」ですが、これは文脈から考えてthinkingの言いかえですね。
<Point 2>the bounds of his experience
直訳だと「経験の範囲」。要するに、経験の幅が狭ければ思考は制限され、逆にその幅が広ければ思考は制限されにくくなるということを言っているのでしょう。
<試訳>
「人の精神的活動を制限するのは、経験の幅と想像力だけだ」
(1-4)
But this natural liberty of private thinking is of little value.
<Point 1>private thinking
そのまま訳すと「個人的に考えること」ですが、これだとイマイチ意味がはっきりしません。この場合のprivateとは(1-2)のso long as he conceals what he thinksの部分を受けた表現で、「秘密の、非公開の」の意と考えられます。要するに、誰にも自分の考えを表明することなく頭の中だけであれこれ考えるというのが、この文におけるprivate thinkingの意味でしょう。
<Point 2>of little value
of+抽象名詞=形容詞の意味になる典型で、「ほとんど価値がないような」の意味。
<試訳>
「しかしこういった生得的な、個人の頭の中だけで思考する自由には、ほとんど価値はない」
(1-5)
It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours.
<Point 1>if節は挿入か否か
ここでのif節は挿入されたものと考えられます。理由は、if節のような副詞節は文の後半に置かれる場合には、その節の直前(ここではhimselfの直後の位置)はカンマなしがふつうだからです(1-5-1を参照)。
(1-5-1)
It is impossible for you to change your listeners' outlook if you are not steeped in the theme of your address.
もしあなたがスピーチのテーマに精通していなければ, 聴衆の物の見方を変えるのは不可能だ.
出典:『ジーニアス英和大辞典』
また、othersの直後のカンマも挿入の目印のひとつになっていますね。というのも、2つの文をandでつなぐだけならその直前にカンマは必須ではありませんが、挿入される語句の前後にはカンマが必要です。つまり、前後にあるカンマのうちどちらか1つでも欠けていれば「挿入」である可能性が消えると考えていいと思います。
<Point 2>if節はどこにかかるか
長くなるので結論から言うと、前半の文と後半の文のどちらにもかかると考えるのが自然です。以下では順を追って考えていきます。
ここでは、if節が挿入されていることの意義は何かという面から考察してみます。一般に挿入語句は通常語順ではない位置に現れることが多いので、(1-5)においてもif節の本来の位置は別だという推測が立ちます。具体的には次の2パターンです。
①if he is...others, it is unsatisfactory...himself and it is obviously...neighbours.
②It is unsatisfactory...himself and it is obviously...neighbours if he is...others.
これらはそれぞれ2つの解釈ができます。①ならば、
a) if節は前半のit is unsatisfactory...himselfのみを修飾
b) if節は前半と後半のどちらも修飾
の2通りで、②ならば、
c) if節は後半のit is obviously...neighboursのみを修飾
d) if節は前半と後半のどちらも修飾
の2通りです。
ここで話が少し逸れますが、b) や d) のように1つの条件節に対して帰結節が2つ並列されている文は特に珍しいわけではありません(1-5-2を参照)。また、帰結節にwillなどの推量を表す助動詞がない場合が意外とあります(上記1-5-1を参照)。
(1-5-2)
You will not be allowed to test and you will lose your test fee if you do not have the correct photo ID.
出典:UCAT
※試訳:「適切な写真付き身分証明書をお持ちでない場合、受験は認められず、受験料も失います」
さて、ここまでを踏まえると、なぜ本来の位置にif節がないのかが見えてきます。要するに、①または②のように書くと a) や c) すなわち「前半の文のみにかかる」あるいは「後半の文のみにかかる」という解釈もされかねないので、b) または d) の「どちらの文にもかかる」ことを示すため意図的にif節を真ん中に挿入した、ということなのでしょう。
なお、以下の解釈もあり得るように見えるかもしれませんが、これらは文の構造からしてまずないです。
e) if節は前半の文のみを修飾する
f) if節は後半の文のみを修飾する
もし e) であるならばif節が挿入語句である意義がなくなります。前半の文のみにif節をかけたいなら、③のようにhimselfの直後のカンマを消した文にすればだけですから。ここにカンマを置くということは、 e) の解釈ではないという証といえるでしょう。
③It is unsatisfactory...himself if he is...others, and it is obviously...neighbours.
また f) についても同様で、もし後半の文にのみif節をかけたいならば and の前にわざわざ置く意味がありません。次の④のようにandの直後におけば、if節は後半の文のみにかかると解釈するのが大原則だからです。
④It is unsatisfactory...himself and if he is...others, it is obviously...neighbours .
念のため、類例をあげておきます。
(1-5-3)
The iPhone 15 launches on September 22, and if you plan on picking up Apple’s latest smartphone, you’ll find a slew of new features waiting for you after you unbox it.
出典:BGR
※試訳:「iPhone15が9月22日に発売となる。もしこのアップル最新スマートフォンを購入予定なら、数多くの新機能が開封後にあなたを待っていることだろう」
<Point 3>Itの指すもの
(1-5)※再掲
It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours.
少なくとも、2つのitがそれぞれ別のものを指すという解釈は文脈からしてまずないでしょう。とすれば、2つのitの指すものとしては以下の候補があります。
①2つのitはどちらも(1-4)のnatural liberty of private thinkingを指す
②2つのitはどちらともif節の内容を指す
素直に考えると①の解釈ですが、itがif節の内容を指すこともあるので悩ましいところ。しかも、(1-5)においてはどちらの解釈でも内容の方向性がほぼ同じに見えるので尚更です。
ちなみに、itがif節の内容を指すというのは、I'd appreciate it if you could reply to me.「ご返信いただけたら幸いです」のような場合のことですね(詳しくは最後の補足参照)。
ここではひとまず①の解釈だということにしておきますが、みなさんはどのように考えますか?
<Point 4>his neighbours
まず、hisとはthe thinkerを指します。次にneighboursですが、ここでは文字通り「近所の人」を指すわけではなく、少しあとに出てくる those about him と同じで the thinker の周りにいる人間を広く指していると考えるのが自然です。つまり、ここでいうneighboursとは直前のothersの言いかえでしょうね。
<試訳>
「もし自分の考えを人に伝えることが許されないならば、思考の自由は考えている本人にとって不満なものであるばかりか苦痛でさえあり、また周囲の人間からすれば明らかに何の価値もないものだ」
(1-5)についての補足
ここでは、itが「副詞節の内容」を指す場合についてまとめておきます。このパターンではitが形式主語または形式目的語である場合が多いです。
<形式主語itが副詞節の内容をさす場合>
(1-5-4)
If prices are high, it's probably because of excessive demand.
価格が高いとすれば, それは需要過剰のためだろう。
出典:佐藤治雄 『英語必修例文600』
(1-5-5)
If prices are high, it's because the wind is not blowing and the sun is not showing and therefore there is not enough supply.
出典:LinkedIn
※試訳:「価格が高いとすれば、それは風が吹かず太陽も出ておらずその結果として供給が不足しているからである」
(1-5-4)では主節に推量を表すprobablyがあるのに対して、(1-5-5)では推量を表す語句はなく原因を断定しています。
(1-5-6)
It wouldn't surprise me if the rain changed to snow during the night.
夜の間に雨が雪に変わっても驚かないだろう。
出典:佐藤治雄 『英語必修例文600』
(1-5-6)ではif節は後置され、仮定法のwouldが置かれています。またこの場合の if SV は even if SV の意味です。次の(1-5-7)はif節ではなくwhen節の場合。
(1-5-7)
It broke his heart when his son gave up his medical studies.
息子が医学の勉強を断念した時, 彼は悲嘆にくれた。
出典:同上
この用法のitが指すのはあくまで「副詞節の内容」なので、次の(1-5-8)のようにitを節で置き換えることはできないという点は要注意。itを置き換えできるのは原則的に名詞節の場合のみです。これは以下の<形式目的語itが副詞節の内容をさす場合>でも同じと思われます。
(1-5-8)
It doesn't matter when you start. (≒ When you start doesn't matter.)
いつ始めるかは問題ではありません
※このwhen節は副詞節ではなく名詞節
<形式主語itが副詞節の内容をさす場合>
(1-5-9)
I'd appreciate it if you could reply to me.
ご返信いただけたら幸いです
※文中の 'd は would の縮約語
(1-5-10)
I hate it when you have to put up with so much.
あなたがそれほど我慢しなければならないのは私はいやです
出典:『ジーニアス英和大辞典』
(1-5-11)
I can't help it if you think I'm odd.
君がぼくのことを変人だと思ったとしても, どうしようもない
出典:安藤貞雄 『現代英文法講義』
※この help は avoid の意
ひとまず、補足としては以上です。
ちなみに、if節を受けるitの成り立ちに関して興味深い記事を見つけたので最後に紹介しておきます。この記事では A Comprehensive Grammar of the English Language の記述を引用したうえで次のように述べられていました。
(1-5-12)
調べてみたところ、どうもthat節を受ける仮主語it+形容詞の文(例:It is strange that he is so late.)において、It isのisに助動詞が付いたり(例:It will be....)仮定法過去になると(例:It would be....)、that節がif節になるということのようです
出典:茗渓予備校のブログ
端的に言うと、willやwouldなどの推量や仮定法を表す語句に引きずられてthat節がif節に変わるということのようです。ということは、that節からif節へと変わると同時に名詞節から副詞節へと品詞自体も変わっているということになりますね。面白い現象です。
最後までお読みいただきありがとうございました。