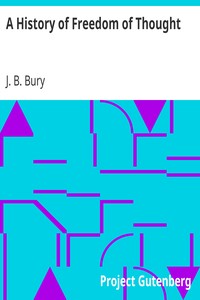今回の英文(前回のつづき)
(1)
IT is a common saying that thought is free. A man can never be hindered from thinking whatever he chooses so long as he conceals what he thinks. The working of his mind is limited only by the bounds of his experience and the power of his imagination. But this natural liberty of private thinking is of little value. It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours. Moreover it is extremely difficult to hide thoughts that have any power over the mind. If a man’s thinking leads him to call in question ideas and customs which regulate the behaviour of those about him, to reject beliefs which they hold, to see better ways of life than those they follow, it is almost impossible for him, if he is convinced of the truth of his own reasoning, not to betray by silence, chance words, or general attitude that he is different from them and does not share their opinions. Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts. Thus freedom of thought, in any valuable sense, includes freedom of speech.
出典:John Bagnell Bury, A History of Freedom of Thought
前回のつづきです。A History of Freedom of Thought の冒頭段落の第8文目からです。
※こちらは著作権切れの作品を扱うProject Gutenbergの蔵書なので大丈夫とは思いますが、もしも問題があった場合には記事を非公開または削除する場合があります。
各文の解釈(前回のつづき)
長いので一文ずつに分けてやっていきます。各文のポイントとなりそうな部分を取り上げていますが、必ずしも正しいとは限りませんので、悪しからずご了承ください。また(1)と出典が同じものは省略してあります。
(1-8)
Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts.
<Point 1>文全体の構造
Some have preferred, like Socrates, to face death...toughts.という文の真ん中に some would prefer to-day が連続して挿入されている構造。つまり、根底にあるのは
①Some have preferred, like Socrates, to face death rather than conceal their thoughts.
②Some would prefer to-day to face death rather than conceal their thoughts.
という2つの文で、これらのto face以下が共通しているために some would prefer to-day が真ん中に挿入されているわけです。
あるいは、to faceの前で Some have preferred, like Socrates, と some would prefer to-day, が並列されていると考えてしまってもいいかもしれません。
<Point 2>2つのsome
このsomeは以下の例と同じです。
(1-8-1)
Some like cofee, others prefer tea.
コーヒーの好きな人もいれば, 紅茶の方が好きな人もいる
出典:『ジーニアス英和大辞典』
<Point 3>Some have preferred...to face death
この部分を「死んだ方がマシだとずっと思ってきた人もいる」のように訳すと意味が変わってしまうので、注意が必要なところ。ここは、直後に like Socrates があることからも分かるように、「死んだ方がマシと考える人々が、これまでの歴史の中において、一部だが存在していた」ということでしょう。
(1-8)の意味が取りにくい原因のひとつは、完了形の主語がsomeのような不特定の人や物を指す名詞になっていることだと思いますが、そのような例は以下の(1-8-2)のように割と普通にあります。
(1-8-2)
A lot of people have died in this country for the freedoms that we have.
出典:BBC
※試訳:
「この国では、現在私たちの手にある諸々の自由を求めて、これまで多くの人間が命を落としてきました」
もしsome have preferred to...のままでは分かりにくい場合には、次の(1-8-3)のようにthere構文と関係代名詞を補って考えるといいかもしれません。
(1-8-3)
There have been some who have preferred to face death rather than conceal their thoughts.
以下の(1-8-4)はこの類例です。
(1-8-4)
There have been many who have preferred the laborious pursuit of knowledge to pleasure, fame, or wealth.
出典:James Jeans, William Bragg, E.V. Appleton, E. Mellanby, J.B.S. Haldane and Julian S. Huxley, Scientific Progress
※whoの先行詞は名詞用法のmany
※試訳:
「快楽や名声あるいは富を得ることよりも、労を惜しまず知識を追求することを好んだ者はこれまでに大勢いた」
<Point 4>would prefer...to face death
(1-8)※再掲
Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts.
would prefer 以降の解釈は以下2つの可能性があります。
①would rather do something than do と同じ
②単なる推量のwould+prefer to do something than do
①は、「~するよりもむしろ・・・したい」というイディオム的な解釈。この場合のwouldは、推量ではなく口調を和らげるためのものと一般的に考えられています。端的にいうと、「控えめな考えを表すwould」となるでしょうか。以下の(1-8-5)はその類例ですが、今回の(1-8)のように比較表現とともに用いるときはlikeではなくpreferを用いるのがふつうです。 would like to do の比較バージョンが would prefer to do と理解しておけばいいかもしれません。
(1-8-5)
I would like to come to your party.
パーティーにはぜひ伺いたく存じます
出典:『ジーニアス英和大辞典』
②はそのままの意味で、wouldを単なる推量と見なした場合の解釈。つまり、would prefer to do something than doの訳としては「~するよりも・・・したいだろう」となります。主語のsomeも加味すると「~するよりも・・・したい人もいるだろう」ですね。
ネット上にある該当箇所の訳をいくつか見てみると、②の解釈ばかりでした。個人的には、①の解釈つまり、would rather do something than do と同じ意味で would prefer...rather than... が使われているとみる解釈もあり得る気がしますが、結局どちらの解釈でとっても全体の文脈把握にはさほど影響がないと判断し、ひとまず②の意味でとっておきます。
①の可能性については長くなりそうなので、考察メモとして次回以降の記事で改めて扱おうと思います。
<Point 5>face death
直訳だと「死に直面する」あるいは「死に立ち向かう」で、die の遠回し表現であることは察しがつきますね。ただ、少し調べてみた限りでは、単なる die の婉曲表現というよりも accept one's own death に近い意味の言い回しと捉えたほうが良さそうです。
余談ですが、face death は「死にかける」の意味でも使われるようです(以下のリンク参照)。
https://redkiwiapp.com/ja/english-guide/questions/ARSHqLrAdO8L7Z4fUDFg
<Point 6>their
これは主語の some を指します。第7文で繰り返し出てきた they や their などとはまた別です。
<試訳>
「ソクラテスのように、自分の考えを隠すくらいなら死んだほうがいいと考える人間は今までにも存在したのであり、また今日においてもそう思う者はいるだろう」
(1-9)
Thus freedom of thought, in any valuable sense, includes freedom of speech.
<Point 1>文構造
SVOの第三文型の文で、主語の直後に修飾語句の in any valuable sense が挿入された形になっています。
<Point 2>in any valuable sense
個人的には今回の英文のなかで最も分かりにくい箇所のひとつ。ネット上にある和訳をみると、ここは「いかなる価値のある意味においても」とか「あらゆる価値のある意味において」といった感じのものが多いようですが、本当にそういった意味なのでしょうか。
ここでのポイントは間違いなく any の解釈。前回の記事の(1-6)でも書きましたが、anyの中核は「任意」で、特に「any+名詞」は基本的に次のうちのいずれかの意味になります(どちらの意味でも解釈できる場合もあり)。
①「種類的に任意の」 つまり 「どれでも」「だれでも」 (≒ any kind of~)
② 「数量的に任意の」 つまり 「少しでも」 「いくらでも」 (≒ any number[amount] of~)
また、「どれであっても」「少しでも、一つでも」というように、この any には if の意味合いが含まれているという点も重要です。この意味では any は if 節との相性が良いといえるので、(1-9-1)のように if 節中に any が現れる文をよく見かけるのも納得できます。
(1-9-1)
If I need any help, I'll call you.
助けが必要な場合は, あなたに電話します
出典:『ジーニアス英和大辞典 ジーニアス用例プラス版』
※前回の補足で触れたように、「any+可算名詞の複数形」と「any+不可算名詞」は種類だけでなく数量も任意であることが暗示されるため、その解釈はあいまいです。つまり、any を上記の①「種類的に任意の」の意味でとれば「何らかの助けが必要な場合は, あなたに電話します」となり、② 「数量的に任意の」の意味でとれば「少しでも助けが必要な場合は, あなたに電話します」となると考えられます。この観点からすると、ジーニアスの和訳はanyの曖昧さをそのまま残したものといえます
ただし、以下の(1-9-2)で言及されているように、if 節がなくても any の意味合いが含まれていることもあります。
(1-9-2)
This software will correct any mistakes in spelling.
このソフトはスペリングのミスがあれば直してくれる(!条件節でなくとも条件の意味が含まれていれば any が用いられる・・・以下略
出典:『ウィズダム英和辞典 第3版』
※(1-9-1)と同様に、この any は種類が任意なのか数量が任意なのかが曖昧です。したがって、(1-9-2)は「このソフトはどんなスペリングミスでも直してくれる」という解釈も可能と思われます
今考えている(1-9)の in any valuable sense もこれと同じで、if の意味合いが隠れているパターンと考えられます。
ただし、(1-9)の sense は in a sense「ある意味で」と同じで可算名詞の単数形なはずであり、かつ「any+可算名詞の単数形」のときの any は「種類的に任意の」という意味でとることが多いので、とりあえずこの意味で any を解釈しておきます(同形の any が別の意味にもなる可能性ついては後述の考察メモ参照)。
ここで一応文脈も確認してみます。たとえば、前々回の記事で扱った第4文と第5文をもう一度見てみるとそれぞれ次のようになっていました。
(1-9-3)
But this natural liberty of private thinking is of little value.
※試訳:
「しかしこういった生得的な、個人の頭の中だけで思考する自由には、ほとんど価値はない」
(1-9-4)
It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours.
※試訳:
「もし自分の考えを人に伝えることが許されないならば、思考の自由は考えている本人にとって不満なものであるばかりか苦痛でさえあり、また周囲の人間からすれば明らかに何の価値もないものだ」
これらの文を見るだけでも、段落全体の趣旨は「単なる思考の自由があるだけではほとんど何の意味もない。言論の自由があって初めて思考の自由には価値がある」ということだと分かります。もう少し噛み砕くと「思考の自由に価値があるとすれば、それは言論の自由を含んでいる場合だけだ」といった感じですね。
以上から、in any valuable sense は「何らかの価値があるとすれば」あたりが妥当ではないでしょうか。直訳だと「何らかの価値がある意味においては」ですかね。
<試訳>
「このように、思想の自由に何か価値があるとすれば、それは(思想の自由が)言論の自由を含んでいる場合なのだ」
(1-9)の考察メモ
(1-9)のPoint2のところで、「any+可算名詞の単数形」の any は「種類的に任意の」という意味になることが多いと書きました(この和訳の典型は「どんな~でも」とか「あらゆる~」などです)。
しかし以下の用例では、any は「種類的に任意の」と「数量的に任意の」のどちらの意味でも解釈できるようです。
(1-9-5)
If any boy can swim the river, I can do it, too.
川を泳いで渡れる少年が(1人でも)いるなら, ぼくだってできる
少年はだれでも川を泳いで渡れるのなら, ぼくだってできる
出典:『ジーニアス英和大辞典』
2つある和訳のうち上の訳が any を「数量的に任意の」という意味で解釈したもので、その下側の訳が any を「種類的に任意の」という意味でとったものですね。
もし (1-9)の in any valuable sense も同じように曖昧な表現だとすれば、「(思想の自由に)少しでも価値があるならば」あるいは「(思想の自由に)ひとつでも価値があるならば」といった解釈でも問題ないことになりますが、皆さんはどう思われるでしょうか。
以上、考察メモでした。何か進展があればまた別記事として扱う予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました。