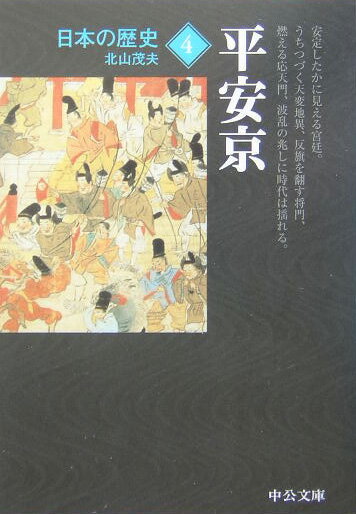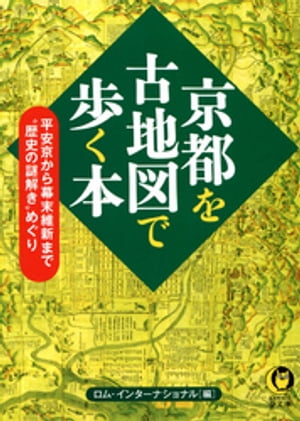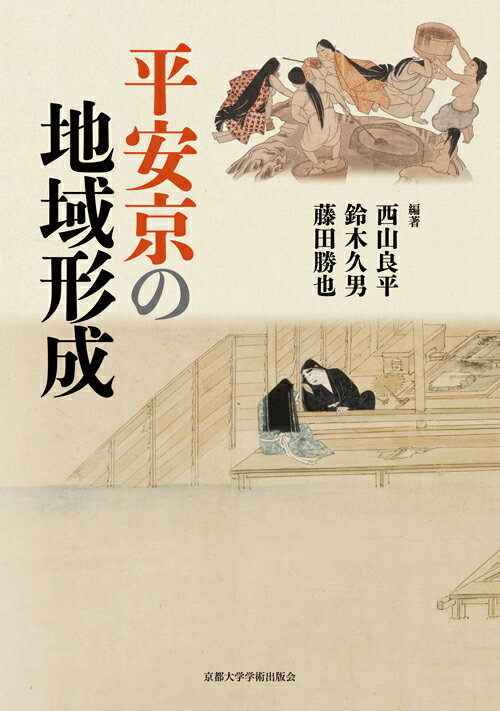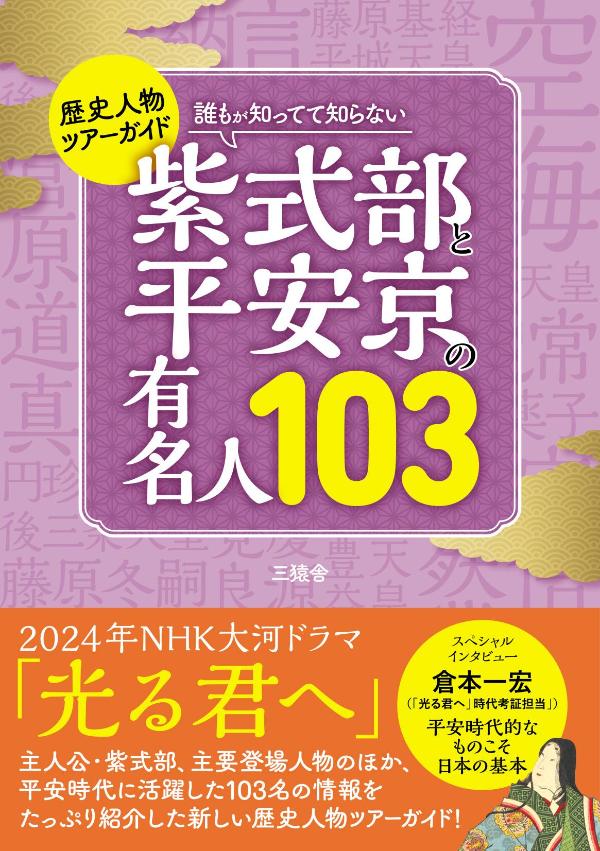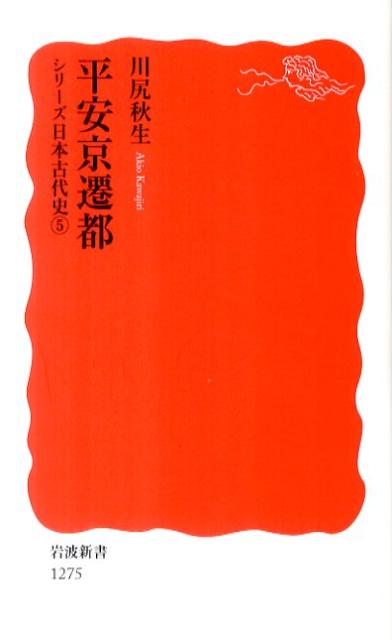一本御書所跡 ― 平安宮に残る書物管理の場
京都の街を歩いていると、時代を超えた歴史の痕跡に出会うことがあります。そのひとつが「一本御書所跡」を示す石標です。
一本御書所とは
一本御書所(いっぽんごしょどころ)は、平安宮(内裏)の東側、侍従所の南にあった施設です。その役割については諸説あり、研究者の間で意見が分かれています。
1つ目の説は、世間に流布する書籍を「一本」(一部)ずつ書き写して保管していたとするもの。
2つ目の説は、「一本書」、すなわち一冊しか存在しない貴重な稀覯本を納め、保管していたとするものです。
どちらにしても、書物の写本や管理を担い、知の保存に関わる重要な場所だったことがうかがえます。
歴史に登場した一本御書所
記録に現れるのは10世紀半ばから。平治の乱(1159年)の際には、後白河院が押し込められた場所としても知られています。当時の政治的な事件の舞台にもなったことで、その名は歴史に刻まれています。
なお、「御書所」や「内御書所」とは別組織であり、独自の役割を担っていたと考えられています。
石標としての現在
現在、この一本御書所の跡を示す石標が建てられています。これは、平成18年から20年にかけて「全京都建設協同組合創立五十周年記念事業」として建立された11基の石標のひとつです。
このシリーズには、綾綺殿跡、弘徽殿跡、承香殿跡、宜陽殿跡、昭陽舎跡、大蔵省跡、西限藻壁門跡など、平安宮ゆかりの重要な場所が含まれています。また、聚楽第南外濠跡や山崎院跡、寺戸大塚古墳といったスポットも同時に標示されており、京都の歴史散策に欠かせない存在となっています。
おわりに
一本御書所跡の石標は、一見するとただの石碑に過ぎないかもしれません。しかし、その背後には、平安時代の知識や文化を支えた「本」と人々の営み、さらには政治的事件の記憶までもが刻まれています。
京都を歩く際には、ぜひ足を止めて、この静かな石標に込められた歴史の物語に耳を傾けてみてください。