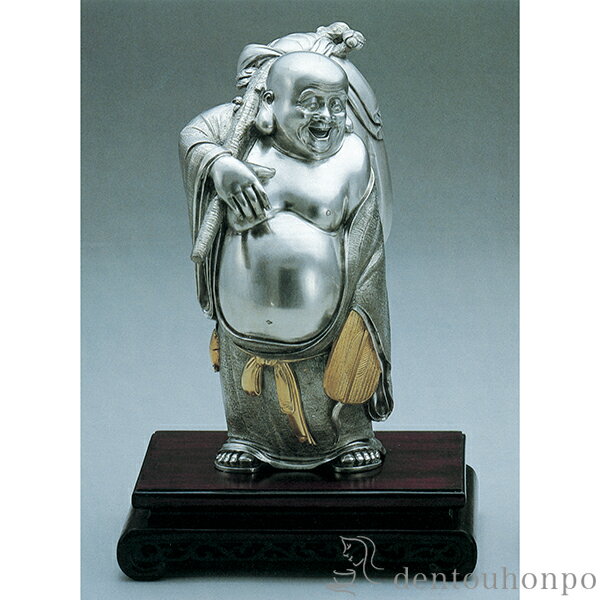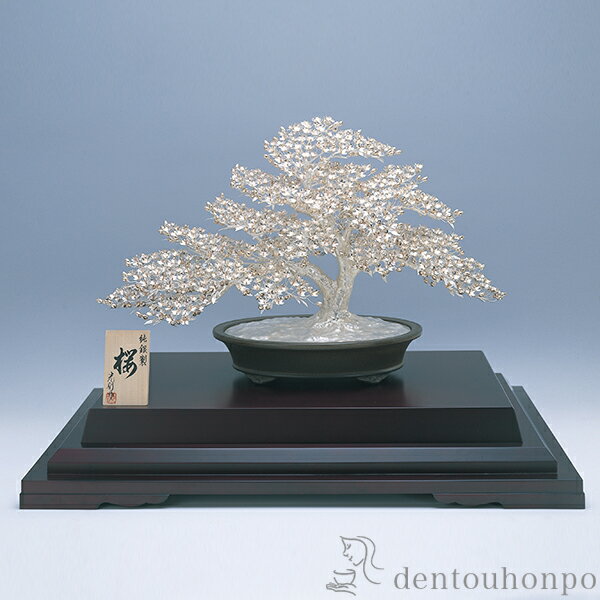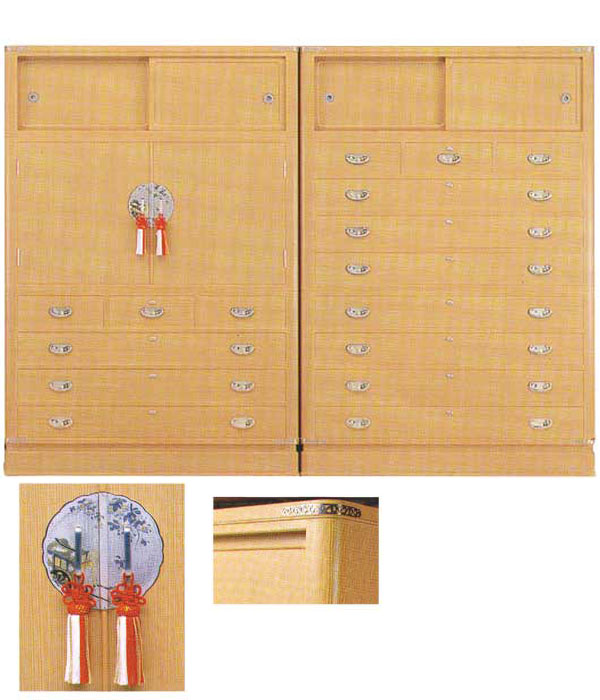平安時代の官僚の定年は70歳で、唐の制度をそのままに61歳から65歳までを「老」、66歳以上を「耆(き)」と定めていました。ただし、平安時代の貴族には定年はなく、終身雇用が建て前だったと言われています。平安時代の平均寿命は諸説ありますが、長い説でも男性が50歳、女性が40歳です。貴族階級の人々は、室内中心の生活による運動不足や偏った食生活、不衛生などから栄養失調や脚気(かっけ)、皮膚病などに罹る者が多く、早死にしがちでした。
奈良から平安時代にかけては40歳(四十賀)、50歳(五十賀)、60歳(六十賀)をそれぞれ長寿の年として、貴族の間でお祝いする風習が生まれました。