- 前ページ
- 次ページ
明日は引越し。
大部分の本や漫画は実家に置いていく。
しばらく読めなくなるので、引越し直前の今日、読み直してみた。
エンゼルバンク ドラゴン桜外伝(1) (モーニングKC)/三田 紀房

¥550
Amazon.co.jp
元高校英語教師が転職代理人になって
社会の仕組みや会社の仕組み(特に人事)について知ったり
仕事を通して、自分がどういう人間になりたいのか考えてみたりする。
簡単に言ってしまうと主人公の成長の物語なのだけど
決して「おもしろかった」で終わらず
思わず我が身を振り返ってしまう。
例えば、1巻。
終身雇用制度を採用する企業の強みについて
人材の流動性が高い企業と比較して語られている。
そういう話を一個人が知ったところでどうにもならないが
終身雇用って非合理的なシステムなんじゃないのか、と
曖昧なイメージとしてしかとらえていなかったものの現実を知るのは
それはそれでおもしろい。
そんな大所高所からの話があるかと思えば
「転職は人生のリセットじゃない。チューニングなんだ」
という格言めいたセリフが飛び出したりする。
こういう転職にあたって失敗しないための考え方なんていうのは
個人の行動にすぐ結び付けられる。
また、これは他の巻なのだが、採用担当者の戸惑いも描かれていて
採用試験を受ける時も気負うことはないぞ、と思えたりする。
個人的には主人公の上司の「日本支配計画」にロマンを感じる。
「世界を変えるのはサラリーマンだ」という。
そういう青臭さが好き。
やっぱり、いい漫画だ。
持っていけないのが惜しい。
大部分の本や漫画は実家に置いていく。
しばらく読めなくなるので、引越し直前の今日、読み直してみた。
エンゼルバンク ドラゴン桜外伝(1) (モーニングKC)/三田 紀房

¥550
Amazon.co.jp
元高校英語教師が転職代理人になって
社会の仕組みや会社の仕組み(特に人事)について知ったり
仕事を通して、自分がどういう人間になりたいのか考えてみたりする。
簡単に言ってしまうと主人公の成長の物語なのだけど
決して「おもしろかった」で終わらず
思わず我が身を振り返ってしまう。
例えば、1巻。
終身雇用制度を採用する企業の強みについて
人材の流動性が高い企業と比較して語られている。
そういう話を一個人が知ったところでどうにもならないが
終身雇用って非合理的なシステムなんじゃないのか、と
曖昧なイメージとしてしかとらえていなかったものの現実を知るのは
それはそれでおもしろい。
そんな大所高所からの話があるかと思えば
「転職は人生のリセットじゃない。チューニングなんだ」
という格言めいたセリフが飛び出したりする。
こういう転職にあたって失敗しないための考え方なんていうのは
個人の行動にすぐ結び付けられる。
また、これは他の巻なのだが、採用担当者の戸惑いも描かれていて
採用試験を受ける時も気負うことはないぞ、と思えたりする。
個人的には主人公の上司の「日本支配計画」にロマンを感じる。
「世界を変えるのはサラリーマンだ」という。
そういう青臭さが好き。
やっぱり、いい漫画だ。
持っていけないのが惜しい。
簡単に紹介。
1.魔王
魔王 (講談社文庫)/伊坂 幸太郎
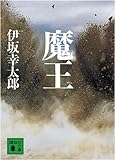
¥650
Amazon.co.jp
毎度おなじみ、伊坂さんの作品。
ずっと前に読んでいたのだが、再度読んでみた。
青臭い主人公や
宮沢賢治の詩を使って扇動しようとする政治家が登場する。
刺激的な作品。
コミックもあるらしい。
魔王 1―JUVENILE REMIX (少年サンデーコミックス)/伊坂 幸太郎
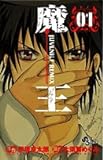
¥410
Amazon.co.jp
2.道は開ける
道は開ける 新装版/デール カーネギー

¥1,680
Amazon.co.jp
「人を動かす」で有名なカーネギーさんの著作。
いかに悩みを解決するかという本。
まだ100ページ程読んだだけだが、効いた。
具体例が豊富で説得力がある。
3.いのちを守る安全学
サイエンス・サイトーク いのちを守る安全学 (新潮OH!文庫)/日垣 隆
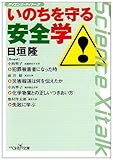
¥570
Amazon.co.jp
日垣隆さんと、4人の専門家との対談。
(1)犯罪被害者になった時(小西聖子さん)
(2)災害報道は何を伝えたか(廣井脩さん)
(3)化学物質との正しいつきあい方(中西準子さん)
(4)失敗に学ぶ(畑村洋太郎さん)
一市民としてできることは限られている、というのが感想。
せめて、ちゃんと知ること、勉強することか。
1.魔王
魔王 (講談社文庫)/伊坂 幸太郎
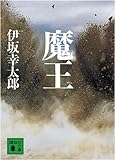
¥650
Amazon.co.jp
毎度おなじみ、伊坂さんの作品。
ずっと前に読んでいたのだが、再度読んでみた。
青臭い主人公や
宮沢賢治の詩を使って扇動しようとする政治家が登場する。
刺激的な作品。
コミックもあるらしい。
魔王 1―JUVENILE REMIX (少年サンデーコミックス)/伊坂 幸太郎
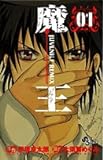
¥410
Amazon.co.jp
2.道は開ける
道は開ける 新装版/デール カーネギー

¥1,680
Amazon.co.jp
「人を動かす」で有名なカーネギーさんの著作。
いかに悩みを解決するかという本。
まだ100ページ程読んだだけだが、効いた。
具体例が豊富で説得力がある。
3.いのちを守る安全学
サイエンス・サイトーク いのちを守る安全学 (新潮OH!文庫)/日垣 隆
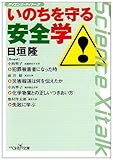
¥570
Amazon.co.jp
日垣隆さんと、4人の専門家との対談。
(1)犯罪被害者になった時(小西聖子さん)
(2)災害報道は何を伝えたか(廣井脩さん)
(3)化学物質との正しいつきあい方(中西準子さん)
(4)失敗に学ぶ(畑村洋太郎さん)
一市民としてできることは限られている、というのが感想。
せめて、ちゃんと知ること、勉強することか。
先日、映画「ソーシャルネットワーク」を見た。
モテないオタクが女の子を見返すために頑張った話とか
天才が仲間を裏切った話とか聞いていたけど
私の印象はそうではなかった。
マーク・ザッカーバーグは天才経営者だった、というものだ。
プログラマとしても天才なのかもしれないが
フェイスブックというSNSがどれほどの価値を持つものか
正しく評価できていたことがキモだったように思えた。
正しく評価できるからこそ何をすべきか見えている。
それがマネージャーに必要な資質であるのではないかと思った。
閑話休題。
ベーシックインカムが導入されるとか
八年後に地球に隕石が衝突し地球が滅亡するなどということにならなければ
社会と関わって、つまり、社会にアウトプットを提供して生きていかなければならない。
そういう前提で話をする。
世界がフラット化する中で、これまでと同じかそれ以上のレベルの生活をしようと思ったら
ドラッカーの言うところの知識労働者になるしかない。
知識労働者として生き残るには
高度な専門知識を身につけることが必要条件だ。
そうなるとドクターを取るという選択肢を選ぶのはわりと自然なことのように思える。
ドクターを取るということは専門知識を武器にすることであり
専門知識を武器にするとは、一つのテーマを推進することにとどまらず
大きなアウトプットを出すためにチームの方向付けをすることだ。
つまり、マネジメントすることだ。
と、すると、私は大学院に進学し、まず何をしなければならないか。
それは正しく評価する訓練だ。
数学の世界において正しく評価するとはどういうことか。
ある問題が解決されると他の問題も解決されるとか
それまで知られていなかった方法が必要になるとか判断できるようになる
そういうことになるのだろうか?
もしそうだとして、それができるようになるにはどうすればいいのだろうか?
まずは、重要な問題であろう100万ドル問題やフェルマーの最終定理
あわよくばヒルベルトの23の問題を理解することだろうか。
それがどれほどレベルの高いことなのかということが
全くわかっていないので、恐ろしいことを言っているのかもしれない。
でも、やろう。
いい教材はあるんだし。
数学21世紀の7大難問 (ブルーバックス)/中村 亨

¥861
Amazon.co.jp
数学ガール/フェルマーの最終定理/結城 浩

¥1,890
Amazon.co.jp
余談だが、ベーシックインカムが導入されたら
草野球リーグのコミッショナーになってガッポリ儲けようかな(笑)
で、儲けたお金で本を大量に購入して独学する。
数学に限らず広く。
ある程度やっていけると思ったらできることを探す。
隕石が落ちてきて地球が滅亡するということになったら
シェルターの強度の計算とかするのかな。
もしそんな情報と能力があれば。
モテないオタクが女の子を見返すために頑張った話とか
天才が仲間を裏切った話とか聞いていたけど
私の印象はそうではなかった。
マーク・ザッカーバーグは天才経営者だった、というものだ。
プログラマとしても天才なのかもしれないが
フェイスブックというSNSがどれほどの価値を持つものか
正しく評価できていたことがキモだったように思えた。
正しく評価できるからこそ何をすべきか見えている。
それがマネージャーに必要な資質であるのではないかと思った。
閑話休題。
ベーシックインカムが導入されるとか
八年後に地球に隕石が衝突し地球が滅亡するなどということにならなければ
社会と関わって、つまり、社会にアウトプットを提供して生きていかなければならない。
そういう前提で話をする。
世界がフラット化する中で、これまでと同じかそれ以上のレベルの生活をしようと思ったら
ドラッカーの言うところの知識労働者になるしかない。
知識労働者として生き残るには
高度な専門知識を身につけることが必要条件だ。
そうなるとドクターを取るという選択肢を選ぶのはわりと自然なことのように思える。
ドクターを取るということは専門知識を武器にすることであり
専門知識を武器にするとは、一つのテーマを推進することにとどまらず
大きなアウトプットを出すためにチームの方向付けをすることだ。
つまり、マネジメントすることだ。
と、すると、私は大学院に進学し、まず何をしなければならないか。
それは正しく評価する訓練だ。
数学の世界において正しく評価するとはどういうことか。
ある問題が解決されると他の問題も解決されるとか
それまで知られていなかった方法が必要になるとか判断できるようになる
そういうことになるのだろうか?
もしそうだとして、それができるようになるにはどうすればいいのだろうか?
まずは、重要な問題であろう100万ドル問題やフェルマーの最終定理
あわよくばヒルベルトの23の問題を理解することだろうか。
それがどれほどレベルの高いことなのかということが
全くわかっていないので、恐ろしいことを言っているのかもしれない。
でも、やろう。
いい教材はあるんだし。
数学21世紀の7大難問 (ブルーバックス)/中村 亨

¥861
Amazon.co.jp
数学ガール/フェルマーの最終定理/結城 浩

¥1,890
Amazon.co.jp
余談だが、ベーシックインカムが導入されたら
草野球リーグのコミッショナーになってガッポリ儲けようかな(笑)
で、儲けたお金で本を大量に購入して独学する。
数学に限らず広く。
ある程度やっていけると思ったらできることを探す。
隕石が落ちてきて地球が滅亡するということになったら
シェルターの強度の計算とかするのかな。
もしそんな情報と能力があれば。
大きなアウトプットを生むには多くのインプットが必要。
多くのインプットをするには自制心だけでは不十分。
自制心を発揮するのに使うエネルギーすらインプットに使いたい。
となると、楽しいと思える仕組みづくりが必要。
だから自己投資と称しあれこれと買ってみるのだ。
実際にはただの新しいモノ好きなんだけど。
しかしGravityは今まで買ってきたものより値段が少しばかり高いな・・・

いやいや。
たとえば7年しか使えなかったとしても(木製パーツの保証は7年)
ひと月あたりの使用料は約4000円。
日経新聞の購読料並み(笑)
これで快適なインプット環境が手に入れられるなんて素晴らしい!
どこ探しても使ってみたレビューが無いんだな。
まずは体験してこよう。
多くのインプットをするには自制心だけでは不十分。
自制心を発揮するのに使うエネルギーすらインプットに使いたい。
となると、楽しいと思える仕組みづくりが必要。
だから自己投資と称しあれこれと買ってみるのだ。
しかしGravityは今まで買ってきたものより値段が少しばかり高いな・・・

いやいや。
たとえば7年しか使えなかったとしても(木製パーツの保証は7年)
ひと月あたりの使用料は約4000円。
日経新聞の購読料並み(笑)
これで快適なインプット環境が手に入れられるなんて素晴らしい!
どこ探しても使ってみたレビューが無いんだな。
まずは体験してこよう。
日本の「安心」はなぜ、消えたのか 社会心理学から見た現代日本の問題点/山岸 俊男

¥1,680
Amazon.co.jp
中世ヨーロッパ。
地中海貿易で活躍する二つのグループがあったそうです。
マグレブ商人とジェノア商人。
彼らは付き合う相手(代理人)の選び方が対照的でした。
マグレブ商人は付き合う相手をかなり限定していました。
付き合う相手からすれば、マグレブ商人は確実に取引してくれるお得意様になるわけで
手数料を下げていました。
そのかわり一度裏切ったら、二度と付き合うことができませんでした。
マグレブ商人はこうして低コストで安心してビジネスを行っていました。
一方、ジェノア商人は付き合う相手を必要に応じて変えていました。
そうすると、手数料を高くする必要があります。
さらにリスクも大きくなるので、法制度を充実させる必要があります。
結果としてコストが高くつきます。
一見するとマグレブ商人の方が成功するような気がしますが
歴史的には、マグレブ商人は地中海貿易の舞台から姿を消し
ジェノア商人だけが残ったそうです。
それはなぜか。
ジェノア商人が払っていたのは機会コストだったからです。
どういうことかというと
ジェノア商人は付き合う相手を限定しないことで
新たなチャンスに遭遇する可能性を高めていたのです。
そして結果的に新たなチャンスをつかみ発展していきました。
著者はマグレブ商人の社会を「安心社会」
ジェノア商人の社会を「信頼社会」と呼んでいます。
安心社会では、身内どうしは協力し外部の者には協力しない。
裏切り者は外部の者となってしまうため、生きる余地はありません。
つまり協力しないとソンをするから、協力するようにしむける社会。
一方の信頼社会では、相手が誰であろうが、まずは信頼してみる。
リスクがあるし、フェールセーフのためにコストをかける社会。
日本はこれまで安心社会として発展してきました。
しかし、グローバル化が進み
閉鎖的な社会の中だけではものごとが完結させられなくなってきました。
閉鎖的だからこそ保証されていた安心が失われたのです。
さらに安心社会では「他人を見たら泥棒と思え」というのが基本スタンスなので
閉鎖性が崩れたからといって、日本人が急に他人を信頼できるよになるわけではありません。
そして不信が不信を呼ぶ負のスパイラル。
日本に充満している不信感について
一般的に日本人の品格が失われたなど、心の問題として扱われていますが
実は社会のあり方の変化に原因があるんじゃないのかねー、というのが著者の主張。
さらに信頼社会にするために、まず信頼しましょうよ、とも。
個人的に思い出したのが小学生の時の自分の態度。
小学1、2年生の時は担任が若い先生で
まわりもおちゃらけた奴ばかりだったので
自分も便乗してギャーギャー騒いでいました。
それが小学3年生になると担任が厳しい先生になり
同じ態度でいるとめちゃくちゃ叱られました。
小学4年生になると担任はまた若い先生になり
1、2年生のときのように騒いでも大丈夫だろうな、とは感じていましたが
実際にはそうしませんでした。
ギャーギャー騒ぐことによる正の利得と
叱られることによる負の利得を天秤にかけ
負の利得の方が大きかったからです。
つまり、自分が「いい子」にしていたのは
それが正しいと信じていたからではなく
それがトクだと感じていたからでした。
ですので、心の問題ではない、という著者の主著湯は納得できるものでした。
自分にはまだ安心社会の人間の性質が強く残っています。
ジェノア商人になれるよう、まずは相手を信頼してみようと思います。

¥1,680
Amazon.co.jp
中世ヨーロッパ。
地中海貿易で活躍する二つのグループがあったそうです。
マグレブ商人とジェノア商人。
彼らは付き合う相手(代理人)の選び方が対照的でした。
マグレブ商人は付き合う相手をかなり限定していました。
付き合う相手からすれば、マグレブ商人は確実に取引してくれるお得意様になるわけで
手数料を下げていました。
そのかわり一度裏切ったら、二度と付き合うことができませんでした。
マグレブ商人はこうして低コストで安心してビジネスを行っていました。
一方、ジェノア商人は付き合う相手を必要に応じて変えていました。
そうすると、手数料を高くする必要があります。
さらにリスクも大きくなるので、法制度を充実させる必要があります。
結果としてコストが高くつきます。
一見するとマグレブ商人の方が成功するような気がしますが
歴史的には、マグレブ商人は地中海貿易の舞台から姿を消し
ジェノア商人だけが残ったそうです。
それはなぜか。
ジェノア商人が払っていたのは機会コストだったからです。
どういうことかというと
ジェノア商人は付き合う相手を限定しないことで
新たなチャンスに遭遇する可能性を高めていたのです。
そして結果的に新たなチャンスをつかみ発展していきました。
著者はマグレブ商人の社会を「安心社会」
ジェノア商人の社会を「信頼社会」と呼んでいます。
安心社会では、身内どうしは協力し外部の者には協力しない。
裏切り者は外部の者となってしまうため、生きる余地はありません。
つまり協力しないとソンをするから、協力するようにしむける社会。
一方の信頼社会では、相手が誰であろうが、まずは信頼してみる。
リスクがあるし、フェールセーフのためにコストをかける社会。
日本はこれまで安心社会として発展してきました。
しかし、グローバル化が進み
閉鎖的な社会の中だけではものごとが完結させられなくなってきました。
閉鎖的だからこそ保証されていた安心が失われたのです。
さらに安心社会では「他人を見たら泥棒と思え」というのが基本スタンスなので
閉鎖性が崩れたからといって、日本人が急に他人を信頼できるよになるわけではありません。
そして不信が不信を呼ぶ負のスパイラル。
日本に充満している不信感について
一般的に日本人の品格が失われたなど、心の問題として扱われていますが
実は社会のあり方の変化に原因があるんじゃないのかねー、というのが著者の主張。
さらに信頼社会にするために、まず信頼しましょうよ、とも。
個人的に思い出したのが小学生の時の自分の態度。
小学1、2年生の時は担任が若い先生で
まわりもおちゃらけた奴ばかりだったので
自分も便乗してギャーギャー騒いでいました。
それが小学3年生になると担任が厳しい先生になり
同じ態度でいるとめちゃくちゃ叱られました。
小学4年生になると担任はまた若い先生になり
1、2年生のときのように騒いでも大丈夫だろうな、とは感じていましたが
実際にはそうしませんでした。
ギャーギャー騒ぐことによる正の利得と
叱られることによる負の利得を天秤にかけ
負の利得の方が大きかったからです。
つまり、自分が「いい子」にしていたのは
それが正しいと信じていたからではなく
それがトクだと感じていたからでした。
ですので、心の問題ではない、という著者の主著湯は納得できるものでした。
自分にはまだ安心社会の人間の性質が強く残っています。
ジェノア商人になれるよう、まずは相手を信頼してみようと思います。
つい一ヶ月ほど前、ブログの中で
問題意識に基づいていない知識は低級だなど
わけのわからないことを書いていたので編集した。
たとえば宇宙の起源を知ることは問題意識ではなく
知的好奇心がエネルギー源になっている。
知るとか見えるということは
人生を豊かにすることにつながる。
だから知りたいからという理由で得た知識は低級ではない。
知っていることで自分は豊かだ、と主張するのは構わないが
知らない人に対して、知らないことをバカにするのは気に食わない。
それであんなアホみたいな主張をしたのだろう。
問題意識に基づいていない知識は低級だなど
わけのわからないことを書いていたので編集した。
たとえば宇宙の起源を知ることは問題意識ではなく
知的好奇心がエネルギー源になっている。
知るとか見えるということは
人生を豊かにすることにつながる。
だから知りたいからという理由で得た知識は低級ではない。
知っていることで自分は豊かだ、と主張するのは構わないが
知らない人に対して、知らないことをバカにするのは気に食わない。
それであんなアホみたいな主張をしたのだろう。
イチローさんと糸井重里さんの対談番組を見ました。
最初の30分は見逃してしまったのですが
それ以外の中でおもしろかった話をいくつかメモ。
【1】毎年がゼロからのスタート
インタビュワーのアナウンサーからの質問で
自分の技術が完成に近付いているという実感を持っているか、というものがあった。
それに対しての答えの中での言葉。
そういう実感は全くなく
今まで何も積み重ねていない。
ようやく、スタートラインに立ったのだ
と、毎年感じているらしい。
常に、まだまだうまくなれる、という気持ちを持てたら
きっと楽しいだろうなぁ。
【2】プロポーズの時間帯について
夜はどうしても気持ちが盛り上がってしまう。
そういう勢いを含めず、純粋に相手に対する気持ちだけを伝えるために
冷静な午前中にするべきだと。
一緒に生活するとなると、そういう時間の方が多いし。
【3】無理をしない
アスリートは往々にして自分を追い込む傾向がある。
が、イチローさんは無理をしないらしい。
楽しくないとも言っていたし
100%のパフォーマンスを引き出すためには
必ずしも100%の努力が必要なのではなく
80%の努力がそれを引き出すのかもしれないとも言っていた。
【2】の話と合わせて、イチローさんは持続可能性を重要視しているのではないか
というのが、糸井さんの感想。
無理をせず、続くかどうかが判断基準になっているのでは?と。
【4】選手生命の常識について
プロ野球選手は40歳ちかくになったら引退するという
常識、雰囲気のようなものがある。
それを変えたいという話があった。
世の中の考えが進んでいるのだから、野球界も変わっていこうよ、と。
今回の番組内ではないけど、50歳まで現役でいたいという話を聞いたこともある。
こういう常識はずれな話、大好き。
できれば、何度でも見たい対談でした。
最初の30分は見逃してしまったのですが
それ以外の中でおもしろかった話をいくつかメモ。
【1】毎年がゼロからのスタート
インタビュワーのアナウンサーからの質問で
自分の技術が完成に近付いているという実感を持っているか、というものがあった。
それに対しての答えの中での言葉。
そういう実感は全くなく
今まで何も積み重ねていない。
ようやく、スタートラインに立ったのだ
と、毎年感じているらしい。
常に、まだまだうまくなれる、という気持ちを持てたら
きっと楽しいだろうなぁ。
【2】プロポーズの時間帯について
夜はどうしても気持ちが盛り上がってしまう。
そういう勢いを含めず、純粋に相手に対する気持ちだけを伝えるために
冷静な午前中にするべきだと。
一緒に生活するとなると、そういう時間の方が多いし。
【3】無理をしない
アスリートは往々にして自分を追い込む傾向がある。
が、イチローさんは無理をしないらしい。
楽しくないとも言っていたし
100%のパフォーマンスを引き出すためには
必ずしも100%の努力が必要なのではなく
80%の努力がそれを引き出すのかもしれないとも言っていた。
【2】の話と合わせて、イチローさんは持続可能性を重要視しているのではないか
というのが、糸井さんの感想。
無理をせず、続くかどうかが判断基準になっているのでは?と。
【4】選手生命の常識について
プロ野球選手は40歳ちかくになったら引退するという
常識、雰囲気のようなものがある。
それを変えたいという話があった。
世の中の考えが進んでいるのだから、野球界も変わっていこうよ、と。
今回の番組内ではないけど、50歳まで現役でいたいという話を聞いたこともある。
こういう常識はずれな話、大好き。
できれば、何度でも見たい対談でした。
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら/岩崎 夏海

¥1,680
Amazon.co.jp
私が本を読む時は
どういう情報が欲しいからその本を読むのか
どういう仮説を検証したいからその本を読むのかということが明確になっており
しかも、その情報やら仮説の検証やらの必要性は
得られずにはいられないくらいに高まっています。
つまり、ある本を読むか否かの選択は
目的に対する手段として適切であるか否かに基づいており
決して流行に流されているわけではありません。
ということを主張したくなるほどの流行の本を読みました。
もとはと言えば、仕事ができるようになるにはどうすればよいか
ということで読んだ「プロフェッショナルの条件」
プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか (はじめて読むドラッカー (自己実現編))/P・F. ドラッカー

¥1,890
Amazon.co.jp
が、ドラッカーさんとの出会いでした。
「プロフェッショナルの条件」には、これからの社会のあり方に基づいて
個々人が組織の中でどのように成果を上げるかということが書かれており
読み進める中で、これからの社会のあり方に興味を持つようになりました。
で、「イノベーションと企業家精神」「ポスト資本主義社会」などなど購入したのですが(積ん読のまま・・・)
本流の(?)マネジメントについてはノータッチでした。
自分はマネジメント層ではないし、そういう権限があるわけでもないから
必要性が感じられませんでした。
が、よくよく思い出してみれば「プロフェッショナルの条件」に
これからのプロフェッショナルの持つべき素養の一つとして
マネジメント能力が挙げられていたような気がします。
(もしかしたら上田惇生さんの「ドラッカー入門」だったかも。)
どういうことかというと、今後、知識労働者の専門分化はますます進み
全体の中で自分の専門がどのような役割を果たすか知る必要がある、というのです。
専門家になるつもりでいる私にも「マネジメント」を読む必要性があるわけです。
専門家になると言っても、まだ専門家ではないし、ちゃちゃっと読んだろ・・・
と、発売間もない去年の今頃、書店で「もしドラ」を見かけた時に
考えたのかもしれません。
理由なんて、後付ですから(爆)
去年、購入してすぐに読了しました。
正直なところ、読む前から大衆向けの本とバカにしてかかっていましたし
読んだ後も、女子マネージャーだから「マネジメント」って無理があるだろとか
小説としての稚拙さなどから、軽い本だという程度の印象しか持ちませんでした。
今回は、前回よりは表面的なイメージを取り除いて読めたと思います。
「野球部とは何か」という問をたて
それに対し「野球をする組織である」というありきたりの答えではなく
野球部の定義を考え出す件は感心してしまいました。
が、やはり、女子マネージャーが考えることとしては、どう考えても無理があります。
また、「マネジメント」の内容を野球部の運営の結びつけるたびに
そういう答えもあるかもしれないけど自然ではないと感じました。
ところで、小説の本質はメッセージを伝えることです。
物語のストーリーではなく、その中に織り込まれた作者のメッセージが本質です。
メッセージを伝えるには、その必然性
つまり、そう考えるのが自然であると感じさせることが重要です。
「もしドラ」には、その自然さが欠けていたため
うまく伝わらなかったのではないかと思います。
以上の点に加え
ドラッカーさんの本が特別読みづらいなどということもないので
マネジメントを知りたければ「マネジメント」を読むのがよろしいかと思います。

¥1,680
Amazon.co.jp
私が本を読む時は
どういう情報が欲しいからその本を読むのか
どういう仮説を検証したいからその本を読むのかということが明確になっており
しかも、その情報やら仮説の検証やらの必要性は
得られずにはいられないくらいに高まっています。
つまり、ある本を読むか否かの選択は
目的に対する手段として適切であるか否かに基づいており
決して流行に流されているわけではありません。
ということを主張したくなるほどの流行の本を読みました。
もとはと言えば、仕事ができるようになるにはどうすればよいか
ということで読んだ「プロフェッショナルの条件」
プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか (はじめて読むドラッカー (自己実現編))/P・F. ドラッカー

¥1,890
Amazon.co.jp
が、ドラッカーさんとの出会いでした。
「プロフェッショナルの条件」には、これからの社会のあり方に基づいて
個々人が組織の中でどのように成果を上げるかということが書かれており
読み進める中で、これからの社会のあり方に興味を持つようになりました。
で、「イノベーションと企業家精神」「ポスト資本主義社会」などなど購入したのですが(積ん読のまま・・・)
本流の(?)マネジメントについてはノータッチでした。
自分はマネジメント層ではないし、そういう権限があるわけでもないから
必要性が感じられませんでした。
が、よくよく思い出してみれば「プロフェッショナルの条件」に
これからのプロフェッショナルの持つべき素養の一つとして
マネジメント能力が挙げられていたような気がします。
(もしかしたら上田惇生さんの「ドラッカー入門」だったかも。)
どういうことかというと、今後、知識労働者の専門分化はますます進み
全体の中で自分の専門がどのような役割を果たすか知る必要がある、というのです。
専門家になるつもりでいる私にも「マネジメント」を読む必要性があるわけです。
専門家になると言っても、まだ専門家ではないし、ちゃちゃっと読んだろ・・・
と、発売間もない去年の今頃、書店で「もしドラ」を見かけた時に
考えたのかもしれません。
理由なんて、後付ですから(爆)
去年、購入してすぐに読了しました。
正直なところ、読む前から大衆向けの本とバカにしてかかっていましたし
読んだ後も、女子マネージャーだから「マネジメント」って無理があるだろとか
小説としての稚拙さなどから、軽い本だという程度の印象しか持ちませんでした。
今回は、前回よりは表面的なイメージを取り除いて読めたと思います。
「野球部とは何か」という問をたて
それに対し「野球をする組織である」というありきたりの答えではなく
野球部の定義を考え出す件は感心してしまいました。
が、やはり、女子マネージャーが考えることとしては、どう考えても無理があります。
また、「マネジメント」の内容を野球部の運営の結びつけるたびに
そういう答えもあるかもしれないけど自然ではないと感じました。
ところで、小説の本質はメッセージを伝えることです。
物語のストーリーではなく、その中に織り込まれた作者のメッセージが本質です。
メッセージを伝えるには、その必然性
つまり、そう考えるのが自然であると感じさせることが重要です。
「もしドラ」には、その自然さが欠けていたため
うまく伝わらなかったのではないかと思います。
以上の点に加え
ドラッカーさんの本が特別読みづらいなどということもないので
マネジメントを知りたければ「マネジメント」を読むのがよろしいかと思います。
楽しく稼ぐ本 (だいわ文庫)/日垣 隆
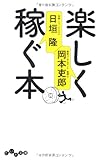
¥680
Amazon.co.jp
日垣隆さんと岡本吏郎さんという税理士の方の対談本です。
最近日垣さんのメルマガ購読をはじめたのですが
メルマガを読むのは、著作をひと通り読んでから、というのが筋ではなかろうかと思いつつも
メルマガは読みたいので、やっぱり購読し
同時に著作を大量購入することでよしとしました。
その時に購入したうちの一冊です。
突然ではありますが、人生はリソースを何に使うかという選択の積み重ねであり
それが一種の表現であるとも思っています。
リソースとは、時間とお金。
そのリソースの一つであるお金を得る方法を知りたくて読んだのですが
意外なおもしろさを持つ本でした。
この本では、中小企業経営者と
日垣さんのようなフリーランスで活動されている方を考察の対象としています。
単価を上げましょうという話から
最終的に、人間の性質について語ってしまいます。
たとえば岡本さんの言葉。
「もう間に合わないというところに来たときには、残念ながらもっと変化しない方に行くんですね。」
ピンチのときに思い出せたら強いですね。
そもそも、ピンチと認識するのが難しいのかもしれませんが。
それと日垣さんの言葉。
「一気に革命を起こさないと世の中は変わらないと思う人と、とにかくやれることをやって、
それが良ければみんながそれを見て結果的にマネするだろうと思う人の違いなんです。」
地に足をつけて、焦らないことですね。
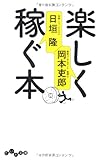
¥680
Amazon.co.jp
日垣隆さんと岡本吏郎さんという税理士の方の対談本です。
最近日垣さんのメルマガ購読をはじめたのですが
メルマガを読むのは、著作をひと通り読んでから、というのが筋ではなかろうかと思いつつも
メルマガは読みたいので、やっぱり購読し
同時に著作を大量購入することでよしとしました。
その時に購入したうちの一冊です。
突然ではありますが、人生はリソースを何に使うかという選択の積み重ねであり
それが一種の表現であるとも思っています。
リソースとは、時間とお金。
そのリソースの一つであるお金を得る方法を知りたくて読んだのですが
意外なおもしろさを持つ本でした。
この本では、中小企業経営者と
日垣さんのようなフリーランスで活動されている方を考察の対象としています。
単価を上げましょうという話から
最終的に、人間の性質について語ってしまいます。
たとえば岡本さんの言葉。
「もう間に合わないというところに来たときには、残念ながらもっと変化しない方に行くんですね。」
ピンチのときに思い出せたら強いですね。
そもそも、ピンチと認識するのが難しいのかもしれませんが。
それと日垣さんの言葉。
「一気に革命を起こさないと世の中は変わらないと思う人と、とにかくやれることをやって、
それが良ければみんながそれを見て結果的にマネするだろうと思う人の違いなんです。」
地に足をつけて、焦らないことですね。