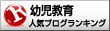12月に数検3級に合格した息子。
小学生に数学を教えたという私の体験を今回はご紹介したいと思います。
◼️5級で新しく出会うもの
5級で新しく出会うもの。
それは、アルファベットやπ、そして負の数(−)です。
「x、yやπを使って数式が作れること」
「負の数の計算ができること」
このふたつを5級のメインテーマに据えました。
他の分野については中学受験の塾の勉強やそれまで好きで読んでいた数学の漫画で得た知識で十分対応できると思ったからです。
まず、文字式やπを使った式については思わぬラッキーがありました。
いま、息子達の世代は、小学校の算数で◯や⬜︎を使って一次方程式を学習しています。
そのおかげで文字式や円周率をπとおき計算を進めることには違和感がない様子で、思っていたより早く⬜︎の代わりにx、3.14の代わりにπを使えるようになりました。
この分野は小学算数から中学数学への接続がいいと感じました。
数検5級のもうひとつのテーマである負の数の計算はひとつひとつスモールステップで問題を解きながら習得していきました。
2-3=-1からはじまり、負の数のあるかけ算(-1)×(-3)=3や指数(-2)^2=4、そして分数の計算(2x-3)/5-(3x+1)/2=(-9x-11)/10まで。
少しずつ難しくなるように符号や数字を変えて取り組みました。
よく言われる「マイナス×マイナス=プラスってなに?問題」についても、たとえばたくさんある飴の中から毎日2個ずつ飴を食べるとして3日前は今よりいくつ多かったか?と具体的に考えてみたり、数直線上の移動として話をしたりしました。
息子はその中から「マイナスの方向に向かってマイナス分だけ進む」イメージを気に入っていました。
また、正×正=正で、正×負=負のとき、負×負=正となることの「つじつまが合う感じ」を面白がっていました。
負の数の計算はパターンを暗記してしまえば正しくできますし、最終的には計算なので機械的に行えばいいもの。
でも、その学習の始まりにはいくつかの見方を通して、自分なりのイメージを持ってほしいなと思って取り組みました。
◼️4級の壁
算数検定6級から数学検定5級へ進むとき、名称が算数から数学に変わることもあって身構える方も多いと思います。
でも、実際に力を入れてやらなければいけないのは5級から4級にあがるときだと私は思います。
5級で学習した文字式がその後の数学でも使えるくらいまでぐいっとレベルアップするのが4級。
そして、関数を扱うのも4級からです。
5級はこれから学んでいく数学の準備をする級で、4級は数学の始まりの級ととらえてもいいのではないかなと思います。
そんな4級なのでテキストは「要点整理」の前に「ステップアップ問題集」に取り組んで、慎重に進めました。
息子は案外そのやり方が合っていたようで、この頃になると「数検の勉強やろうか?」と言うと喜んでテーブルに着くようになりました。
やっぱりわかるものは楽しいし、できるようになると嬉しいものですね。
それは幼児も小学生も変わらないなと思いました。
◼️ボリュームアップする3級
中学数学の最終級、3級はとにかくボリューム満点!
・平方根(√)
・式の展開
・二次方程式(因数分解・解の公式)
・二次関数
・確率
などなど
これまでの学習をベースにさらにたくさんの高度なテーマに取り組みます。
(ただ、安心していただきたいのは図形分野は3級でも中学受験の勉強をしている子にとっては難しくないと思います。)
3級の最大のテーマは「式の展開」と「二次方程式」。
とはいえ、この段階では数検5級で数学の知識の準備ができていて、4級の学習を通して数学の学び方も経験しています。
3級になって一気に増えた学習範囲。手元に集中しすぎると自分が今何をやっているのか見失ってしまうことはよくある話です。
そんな迷子にならないようにまず全体を見てから細かな解放を見ていくように、学習の順番に気を使いました。
「式の展開はどんどん式をバラバラに分解していく感じ。そして二次方程式はその逆に、どんどんくっついて繋がっていくようだね。」と、私の主観も交えつつ、ふたつの数式の違いや、それぞれにできることを話して、それらが展開していくところを見せて、その後、息子も自分でやってみて…
まさに「やってみせ、言ってきかせて、させてみせ…」のスタイルです。
全体とその位置をおさらいしながら、細かな部分を見ていく、この繰り返しが3級のボリュームに対応するのによかったなと思います。
小学生であろうとも、理解と演習を積みかさていけばきちんと進むことができる。
今回のチャレンジは「数学は積み重ねの学問」という言葉を実感する機会となりました。
皆さんもそれぞれのペースで数学の面白さを味わいながら学習を進めてほしいなと思います。
◼️数検3級に合格するということ
数検3級の合格証が息子あてに届いて、私が思ったこと。
それは「これでこの子はもう一人で数学の勉強を進めていける。」ということでした。
3級まで学習すると、平方根や方程式の意味を知っているし、正しく式を理解し、展開することができます。
これから新しく出てくる、例えば三角関数や対数であっても、その説明をもう自分で読むことができる。
3級に合格するということの意味はそういうことだと思います。
もちろん中学受験が終わってからまた息子が「数検受けようかな」とゴロゴロ暇そうに言ってきたら、私は喜んで一緒にテーブルに並んで準2級のテキストを開くのですが。
ずいぶん一緒に歩いてきました。
3級合格おめでとう。