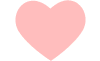蛍の舞う頃となりました。
七十二候では、この時期を
腐草為蛍(ふそう 蛍となる)
といいます。
小さい頃、夕涼みがてら
有栖川公園まで
ホタルをよく見に行きました。
ほのかな光は
涼を感じさせ、
幼い私は
なんともいえない不思議な色の
とりこになっていました。
「源氏物語」には
玉鬘(たまかずら)という
美しい姫君が登場します。
光源氏がいたずらに放った蛍。
その光によって
映し出された
姫の美しい横顔。
それを見た兵部卿の宮は
恋に落ち…
姫に歌を贈ります。
鳴く声も 聞こえぬ虫の 思ひだに
人の消つには きえるものかは (※1)
玉鬘はすぐに
声はせで 身をのみ焦がす 蛍こそ
言うよりまさる 思いなるらめ (※2)
と、上手に言い寄る相手をかわしてしまいます。
蛍は…
残念ながら
今の東京では、
なかなか見ることがかないません。
そんなとき
興津早生(温州みかん)が
ハウスの中で色づきはじめたと
生産者の方から
メールをいただきました。

実の下のほうが色づいています。
これを専門用語で
「ほたる尻」と呼ぶのだそうです。
これから
夏の光をたくさん浴びて
太陽のような
美しい色に
染まっていくことでしょう。
思いがけず
昼間の光にも負けない
元気な蛍を見ることができました![]()
(※1)部卿の宮の詠んだ歌の意訳
蛍の思いは 鳴く声が伝わらないからこそ
人が消そうとしても 消えぬものなのです
(※2)玉鬘の返歌の意訳
声に出さず身を焦がしている蛍のほうが
言葉で伝えるあなたよりも
もっと深い思いをもっていることでしょう