ここ数ヶ月ほど自分の今の仕事にいまいち情熱を持つことができず、自分のキャリアというものについて、就職活動以来改めて深く考えるということをしている。まだまだ自分なりの答えが出たわけではないのだけど、その中で参考になった本と話を紹介しておく。
ノマドと社畜 ~ポスト3・11の働き方を真剣に考える/朝日出版社
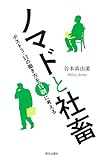
¥924
Amazon.co.jp
谷本真由美氏は@May_RomaのTwitterアカウントで著名な人物である。『ノマドと社畜』では、3.11以後の日本におけるいわゆる「ノマドブーム」の現状を捉え、その問題点を指摘している。その上で、グローバルな観点から「ノマド」に求められる資質について語っている。本書において著者が徹頭徹尾強調しているのは、「ノマド」には確たるプロ意識と専門性が求められるという点である。
一方で、日本企業に見られる「ゼネラリスト」(何でも屋さん)を、「自分独自の専門性や個性を「売り」にすることができない」と批判している。今後は雇用環境が激変することによって企業が正社員を減らし「外人部隊」的な「ノマド」を増やす可能性があると言及している。
この本を読んでいて考えたのは、「ノマド」それ自体は常に自分の生きる市場における自己の価値を高め続け無くてはならず、それを怠ればあっという間に仕事も収入も失うということである。日本のサラリーマン(本書で言うところの「社畜」)のように、一度会社に入ってしまえばある程度の仕事と収入が保証されるというスタイルとは大きく異る。少なくとも現在までのところ、「社畜」の方が「ノマド」よりも、仕事と収入を失うリスクははるかに低かった。
しかしながら、本書でも指摘されている通り、今後日本企業が従来のように正社員(=「社畜」)を重視するとは限らない。とすれば、これまで仕事と収入において比較的リスクの低かった「社畜」もまた、「ノマド」同様に仕事と収入を失うリスクが高まるわけである。しかも、「ノマド」とは異なり確たるプロ意識も専門性もないままに、である。
こう考えてみると、たとえ「社畜」であったとしてもいずれ来るであろうリスクに備えて、「ノマド」が備えているプロ意識や専門性というものを身に付けておく必要がある。ここで私が重視したいと思うのが、"Rice Work"という概念である。
この"Rice Work"という言葉を初めて耳にしたのはつい先日参加した勉強会の席においてである。ネットで調べてみると、"Rice Work"という言葉自体はそれほど新しい言葉ではないらしい。勉強会で聴いた話から"Rice Work"という言葉を考えると、要するに「メシを食える仕事」である。災害や戦争、テロ、企業の倒産といった不測の事態が起こった際に、生き延びるために必要な能力を身に付けておく必要があるということである。
この能力を身につける上では、今後「役に立つ」と思われる能力や知識、技術を新たに修得する必要があるだろう。しかしながら同時に、これまでの仕事や人生において身に付けてきた能力や知識、技術のうち、最も自分にとって強みとなるものを「メシを食える」ように変換することも必要となるだろう。
この"Rice Work"という発想を意識しつつ『ノマドと社畜』の話に戻ろう。著者は、「ノマドになれるのはスーパーワーカーだけ」とも述べている。企業で言えば「バリューチェーン」を全て一人でこなせる「スーパーワーカー」でなければ「ノマド」にはなれないのである。すなわち、営業、事務処理(会計、税務、法務、総務など)、対人関係の全てができなければ「ノマド」になることは難しい。(人を雇う余裕があるのであれば、これらを分散すればよい)。
逆に言うと、本書でもふれられている通り、自分で調べもせずに人に「教えてくれ、助けてくれ」というような「クレクレ」の発想(本書では「自分勝手でずるい人」と言い換えられている)では、「ノマド」としては大成しないということであろう。
自分自身が「ノマド」として生きるかどうかは別として、今後の日本という国と日本企業を考えると、かつてのように「ゆりかごから墓場まで」の面倒を見てくれるというのは幻想であろう。とすれば、自分自身もまた"Rice Work"を身につける必要があるだろう。新たに何を身につけるか、これまで身に付けた能力、知識、技術が何であるかをじっくりと考えてみる必要がありそうだ。
ノマドと社畜 ~ポスト3・11の働き方を真剣に考える/朝日出版社
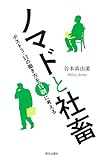
¥924
Amazon.co.jp
谷本真由美氏は@May_RomaのTwitterアカウントで著名な人物である。『ノマドと社畜』では、3.11以後の日本におけるいわゆる「ノマドブーム」の現状を捉え、その問題点を指摘している。その上で、グローバルな観点から「ノマド」に求められる資質について語っている。本書において著者が徹頭徹尾強調しているのは、「ノマド」には確たるプロ意識と専門性が求められるという点である。
一方で、日本企業に見られる「ゼネラリスト」(何でも屋さん)を、「自分独自の専門性や個性を「売り」にすることができない」と批判している。今後は雇用環境が激変することによって企業が正社員を減らし「外人部隊」的な「ノマド」を増やす可能性があると言及している。
この本を読んでいて考えたのは、「ノマド」それ自体は常に自分の生きる市場における自己の価値を高め続け無くてはならず、それを怠ればあっという間に仕事も収入も失うということである。日本のサラリーマン(本書で言うところの「社畜」)のように、一度会社に入ってしまえばある程度の仕事と収入が保証されるというスタイルとは大きく異る。少なくとも現在までのところ、「社畜」の方が「ノマド」よりも、仕事と収入を失うリスクははるかに低かった。
しかしながら、本書でも指摘されている通り、今後日本企業が従来のように正社員(=「社畜」)を重視するとは限らない。とすれば、これまで仕事と収入において比較的リスクの低かった「社畜」もまた、「ノマド」同様に仕事と収入を失うリスクが高まるわけである。しかも、「ノマド」とは異なり確たるプロ意識も専門性もないままに、である。
こう考えてみると、たとえ「社畜」であったとしてもいずれ来るであろうリスクに備えて、「ノマド」が備えているプロ意識や専門性というものを身に付けておく必要がある。ここで私が重視したいと思うのが、"Rice Work"という概念である。
この"Rice Work"という言葉を初めて耳にしたのはつい先日参加した勉強会の席においてである。ネットで調べてみると、"Rice Work"という言葉自体はそれほど新しい言葉ではないらしい。勉強会で聴いた話から"Rice Work"という言葉を考えると、要するに「メシを食える仕事」である。災害や戦争、テロ、企業の倒産といった不測の事態が起こった際に、生き延びるために必要な能力を身に付けておく必要があるということである。
この能力を身につける上では、今後「役に立つ」と思われる能力や知識、技術を新たに修得する必要があるだろう。しかしながら同時に、これまでの仕事や人生において身に付けてきた能力や知識、技術のうち、最も自分にとって強みとなるものを「メシを食える」ように変換することも必要となるだろう。
この"Rice Work"という発想を意識しつつ『ノマドと社畜』の話に戻ろう。著者は、「ノマドになれるのはスーパーワーカーだけ」とも述べている。企業で言えば「バリューチェーン」を全て一人でこなせる「スーパーワーカー」でなければ「ノマド」にはなれないのである。すなわち、営業、事務処理(会計、税務、法務、総務など)、対人関係の全てができなければ「ノマド」になることは難しい。(人を雇う余裕があるのであれば、これらを分散すればよい)。
逆に言うと、本書でもふれられている通り、自分で調べもせずに人に「教えてくれ、助けてくれ」というような「クレクレ」の発想(本書では「自分勝手でずるい人」と言い換えられている)では、「ノマド」としては大成しないということであろう。
自分自身が「ノマド」として生きるかどうかは別として、今後の日本という国と日本企業を考えると、かつてのように「ゆりかごから墓場まで」の面倒を見てくれるというのは幻想であろう。とすれば、自分自身もまた"Rice Work"を身につける必要があるだろう。新たに何を身につけるか、これまで身に付けた能力、知識、技術が何であるかをじっくりと考えてみる必要がありそうだ。