現在、私の大学では学生と教員の質的向上を目指しハッピーを共有しようという、
ふざけたプロジェクトが進行中である。
文部科学省の認証評価制度
というものが原因らしく、
このままでは、大学側が文部科学省の評価に耐えうるものにならない
と判断したための苦肉の策だと思われる。
これは、学生側の授業態度、教員側の教育方法、
そして設備などの環境改善を目指しているらしい。
どうやら、大学側は学生の学力低下を懸念しているらしいのだ。
まぁ、そんなことはどうでもいいのだ!
そもそも大学とは研究機関のはずで、教育機関ではない。
つまり、大学に教育を望むのは間違っているのではないか。
それに、もともと勉強が嫌いとか勉強に興味がない人に
「授業で眠るな!携帯電話を使うな!私語を慎め!」などと言っても無駄な話である。
人間、眠いときは眠るし、話したいときは話すものだ。
そして人間は、興味のあること好きなことには全精力を傾ける。
そういうことには熱心だし真剣でもある。
就職活動を見ていれば一目瞭然だろう。
自分の将来がかかっていることに真剣にならない者は、あまりいない。
授業環境を改善したいなどというのは、
学生の真剣さを生かせない大学側や教員の自分勝手な言い分なのではないか。
従来の注入主義では、限界に来ているのかもしれない。
だが、ゆとり教育とやらも頓挫している状況で、どうしたらいいのだろうか?
状況主義の徹底
メンター制度の導入
e-Lerningの効果的な使用
学習支援のための相談室の開設
などを安易に企画し、大学改革を推し進めても失敗することは目に見えている。
なぜなら、費用・設備・人材・成績評価・権力争いなど、
大学には非常に多くのしがらみや制約があり、
改革をするにも膨大な労力と時間を要するからである。
多くの教育関係の研究者が声高に大学改革を叫ぶ一方で、
誰も具体的な策を提出しないのには、このような理由がある。
結局のところ、大学改革は難しいという結論に至る。
無力な私は、いつも途方に暮れるのである。
[今回の参考文献]
- 状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加/ジーン レイヴ

- ¥2,520
- Amazon.co.jp
- 「学び」を問いつづけて―授業改革の原点/佐伯 胖
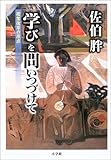
- ¥2,100
- Amazon.co.jp
- 認知心理学者 新しい学びを語る/森 敏昭

- ¥2,625
- Amazon.co.jp
- 認知的道具のデザイン/加藤 浩

- ¥4,410
- Amazon.co.jp