薺が緩やかな坂道を登っていく。
待ち遠しい。
心が騒ぎ、揺れている。
神の御心に触れたあの日。
気がついたら…
手の中に文があった。
その約束の日に、この坂を登っている。
目の前に人影が見える。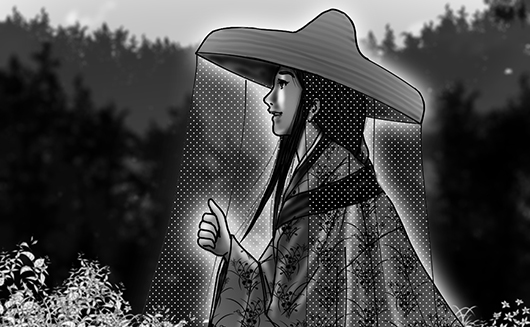
「ああ…」
薺の瞳から光が落ちる。
「こんな日が来るなんて…」
薺はこの時に、感謝していた。
「来たようだな…」
一度、繋いだ波動。
真魚が、その波動を感じている。
「薺…様…なの?」
明慧が、それを疑っている。
「よく分かったな…」
真魚が笑っている。
その明慧の姿を慧鎮が見ている。
姿はまだ見えない。
以前とは違う薺の波動。
大いなる神の御心に、触れたからだ。
「母上と似ています…」
明慧はそう答えた。
「なるほどな…」
その答えを聞いた真魚が、感心していた。
「薺様が…耀いています」
明慧はそう感じた。
薺の感動の波動が、明慧には見えている。
その耀きを感じている。
人はそれぞれに目的を持つ。
生きている意味…
そう言ってしまえば、簡単かも知れない。
人は、その目的に近づくほど耀きを放つ。
薺は今、それを確かなものとして感じている。
耀きを放つ意味を、心に刻み込んでいた。
その心という器に閉じ込められた想い。
人はその器を揺らし、耀きを得る。
だが、それを感じ取れる者は少ない。
そして、その器を揺らすのは…
人霊そのものなのだ。
「私も…心が揺れています…」
明慧がそう言った。
自らの心の動きは、薺の耀きに無縁ではない。
明慧はそれを感じ取っていた。
「大したものだ…」
真魚が笑っていた。
薺の姿がはっきりと見える。
目の見えない明慧が、それを観じている。
「薺様…」
揺れる心のままに…
明慧は薺の元に歩き出した。
「明慧!」
薺はその姿に溜まらず走り出した。
市女笠を捨てた。
付き人の少女が、それを拾っている。
明慧が笑っている。
薺の波動を感じている。
「明慧!」
薺が膝をつき、明慧を抱きしめた。
そして、泣いた。
涙が、明慧の着物を濡らしている。
「泣かないでください…薺様…」
明慧が、薺を抱きしめた。
「こんなに…こんなに大きくなって…」
薺は明慧の生命を感じている。
その感動が広がっていく。
「あれっ…」
明慧がそれに気付いた。
「これは…」
薺が驚いていた。
「母上…」
二人を柔らかく包み込む光。
明慧がその波動を感じていた。
「姉上…」
明慧を抱きしめながら、薺が泣いていた。
「もう、いいのですよ…」
桔梗の波動が聞こえる。
その苦しみの全てを、桔梗が摘み取っていた。
「姉上…」
薺の涙は止まらなかった。
「これでいい…」
真魚がそう言って、笑みを浮かべた。
「ありがとうございます…」
慧鎮の目から、涙が溢れていた。

続く…
-この物語はフィクションであり、史実とは異なります。
実在の人物・団体とは一切関係ありません-