嵐が放った波動が通り抜けた。
その波動の主を確認するかのようにその方向を見た。
颯太だけが蚊帳の外だ。
「これは…」
鈴鹿御前が考え込んだ。
そして、ゆっくりと立ち上がった。
「姉御、俺が行く…」
飛炎が鈴鹿御前を制して出ようとした。
「客人を迎えるのは主人の役目じゃ…」
鈴鹿御前が飛炎を睨んだ。
「姉御…」
その鬼のような目に飛炎が怯んだ。
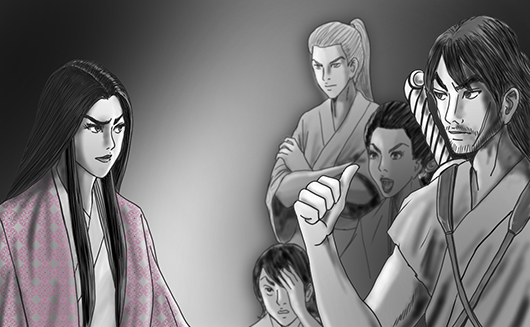
「うそ…」
凪はその姿に驚きを隠せない。
今までこの屋敷を見て帰ったものはいない。
この場所が知られていないのは、それが理由だ。
「客人…」
凪の開いた口が塞がらない。
「それもいい…」
柱に背を預けて疾風が笑みを浮かべている。
「俺では勝てぬと言うのか!」
飛炎が鈴鹿御前に詰め寄る。
「お主はあの波動をどう捉えるのじゃ?」
鈴鹿御前が飛炎を睨み付ける。
「…」
飛炎は黙り込んだ。
「大切なものを失うわけには行かぬ…」
鈴鹿御前はそう言って背を向けた。
「姉御…」
飛炎はその言葉に動けなかった。
初めて聞く鈴鹿御前の言葉。
その言葉に自分の浅はかさを悔いた。
「うそ…」
凪は信じられなかった。
先ほどまで颯太の目玉で遊んでいたのだ。
その御前からあのような言葉が出るとは想像付かない。
凪はその言葉に御前の心を感じていた。
自分の中に生まれる何かを感じていた。
真魚と嵐は門の前まで来た。
ぎぃぃ…
きしむ音をたてながら、門が開いた。
「嵐の波動を感じたか…」
だが、誰もいない。
「俺の波動がどうかしたのか?」
嵐に戦略など無い。
ただ単にしたことがこのような結果に繋がっただけだ。
「ある程度は受け入れたか…」
真魚はそう捉えていた。
「ある程度とは何だ!俺は神だぞ!」
嵐が機嫌を損ねている。
庭は広い。
池がありその上に反橋がかけられている。
寝殿まで行くにはその反橋を越えなければならない。
気がつくと、その反橋の上に一人の女が立っていた。
女はゆっくりとこちらに近づいてきた。
あでやかな十二単を纏い、袴をはいている。
着物が地面に擦れている。
汚れることは気にしていないようだ。
「ほう」
真魚は声を上げた。
遠くからでもその美しさが目にとまる。
そして、その波動を感じていた。
女が止まった。
まだ距離がある。
歩数にして二十。
この距離がこの女にとっての間の様である。
『気をつけろ…』
美しい声が真魚の心に届く。
「この波動を感じて気は抜けぬ」
真魚はそう言った。
「真魚、奴は人間か?」
嵐はそう感じていた。
人にしては大きすぎる。
それはある意味、人ではないと言うことかも知れない。
「おい、真魚!」
嵐が瓢箪を見つけた。
その女の手にいつの間にか握られている。
「私共のものが粗相をしでかしたようで…」
女がそう言うと手の上の瓢箪が消えた。
次の瞬間真魚の目の前に現れた。
真魚はそれを左手で受け取った。
「ほう」
真魚の口元に笑みが浮かんだ。
「宙を操る力か…」
その女は先に手の内を見せてきたのだ。
「どうなっているのだ、真魚!」
嵐が驚いている。
「これが帰って来ればいい」
真魚はそう言って腰に瓢箪の紐を結んだ。
だが、これはただの儀礼に過ぎない。
この女にとっては自分の懐にあるも同じ。
意のままにどこにでも移動できるのだ。
真魚にわざとその事を伝えている。
「だが、何でもというわけではあるまい…」
「どういうことだ?」
嵐は真魚の言った言葉が気になった。
「嵐、お前ならどうする?」
「お、俺か!」
そう言いながら嵐は考え込んだ。
「何を話しておるのじゃ…」
鈴鹿御前が二人に声を掛けてきた。
「この瓢箪の中身が無事かどうかと…」
そう言いながら真魚が瓢箪を振った。
その瞬間、瓢箪が真魚の手から消えた。
「見た目は同じだな…」
真魚が笑っている。
少し離れた場所で嵐が瓢箪を咥えて立っていた。
「面白い…」
鈴鹿御前は笑っている。
だが、嵐はものすごい速さで移動しただけだ。
見た目は同じでも根本的に違う。
「人は私を鈴鹿御前…そう呼ぶ」
その美しさが一際輝く。
「お主…名は何という?」
鈴鹿御前が聞いた。
「佐伯真魚だ!」
真魚が答えた。
「佐伯真魚…もしや…」
その時、鈴鹿御前の顔色が変わった。

続く…
-この物語はフィクションであり、史実とは異なります。
実在の人物・団体とは一切関係ありません-