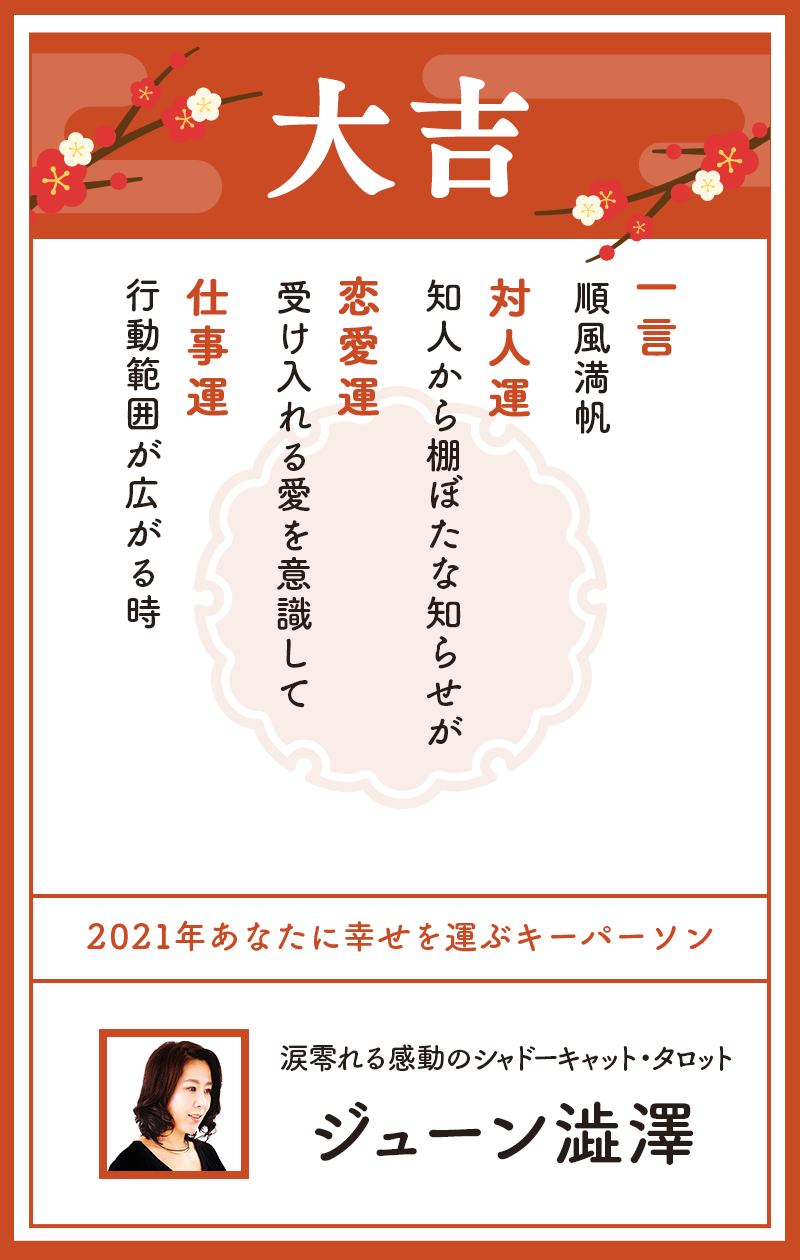プッチーニの「ラ・ボエーム」、第一幕では臨時収入が入ったショナールがボルドーワインを買って帰り、みんなで乾杯する場面がある。Bordò はボルドーワインに間違いない。ドニゼッティの「愛の妙薬」の正体もこれであった。
さて、第二幕でカフェ・モミュスでメニューを見ながらショナールとコルリーネがギャルソンに立て続けに注文する場面である。ショナールが Vin del Reno、間髪入れずにコルリーネが Vin da Tavola と言う。

直訳すれば前者がラインのワイン、後者がテーブルワインとなる。後者は後のイタリアの法律でも産地やブドウ品種、年号などのこだわりのない安価な日常用ワインとして定められている。フランスでも Vin de Table が全く同じ意味である。恐らく当時も普通のワインという意味で用いられていた言葉で、日本の居酒屋で「ハウスワインください」という感じであろう。
ここで問題にする「ラインのワイン」、フランス語に直訳すれば Vin du Rhin となる。フランス東部のアルザス地方はライン川の西岸に位置し、現在でも Haut Rhin(上ライン)県と Bas Rhin(下ライン)県からなる。その両県を実際に旅行してみると県境はあまり意識できないのだが、いずれの県も高品質なワインを生産している。したがって、現在のフランス人がこの(外国人が書いた)リブレットを見れば、アルザスのワインのことを言っていると思うに違いない(実際にはアルザスワインのことを Vin du Rhin と呼ぶことはないが)。
アルザスワインはごく一部を除いて白ワインが殆どである。実はパリの庶民は基本的に赤ワインしか飲まないので、これを注文することに(そもそも庶民的なカフェのリストにあることにも)かなりの違和感を感じていた。更には、この時期にアルザス地方はドイツ領になっていたので、高級レストランであったとしてもアルザスワインの入手は現在に比べて遥かに困難であったと考えられる。現在でもパリで普通にワイン漬けの生活をしている人間がドイツワインを見掛けることはあり得ないのである。
ショナールが Vin del Reno と言うなりすぐにコルリーネが Vin da Tavola と普通の注文をしていることから、ショナールの言葉は実際に注文しようとしたのではなく、ふざけて言った言葉なのであろう。彼らの会話には、頻繁に教養をひけらかした言葉が見られるから、その類ではなかろうか。色々考えてみたところ、この Vin del Reno は、実はゲーテの戯曲「ファウスト」に出て来るものであるに違いない。
悲劇の第一部、ライプツィヒの酒場で学生たちが酒を選ぶ場面、Frosch が出身地の Rheinwein を飲むと言う。

これをイタリア語にするとこうなる。
つまり、彼はカフェに集まった自分達の状況を、ファウストに出て来る学生たちが酒場に集まった光景に重ねて洒落ているのである。
こう考えると、注文を取りに来たギャルソン役の俳優は、Vin del Reno と言われて一瞬怪訝そうな顔をし、Vin da Tavola で頷くのが適切な演技ということになる。
ちなみに現在の日本でラインワインと言えばライン川右岸のドイツワインを指す。昔はどこのワイン売り場にもずらりと並んでいたが、近年はほとんど見かけなくなってしまった。大きなスーパーなどでよく探すと、リープフラウミルヒ Liebfraumilch という聖母マリアの絵が描いてある茶色くて細長い瓶のワインが千円程度で売られていることがある。これは一応ちゃんとしたラインワイン(のほぼ最低ライン)である。やや甘口・低アルコールで、よく冷やして飲んだら美味しいと思うが、ファウストの時代、あるいはラ・ボエームの時代のラインワインがこのような味であったのか否かは保証の限りではない。一方フランスのアルザスワインは本格的な辛口ワインで、それなりの値段がする。