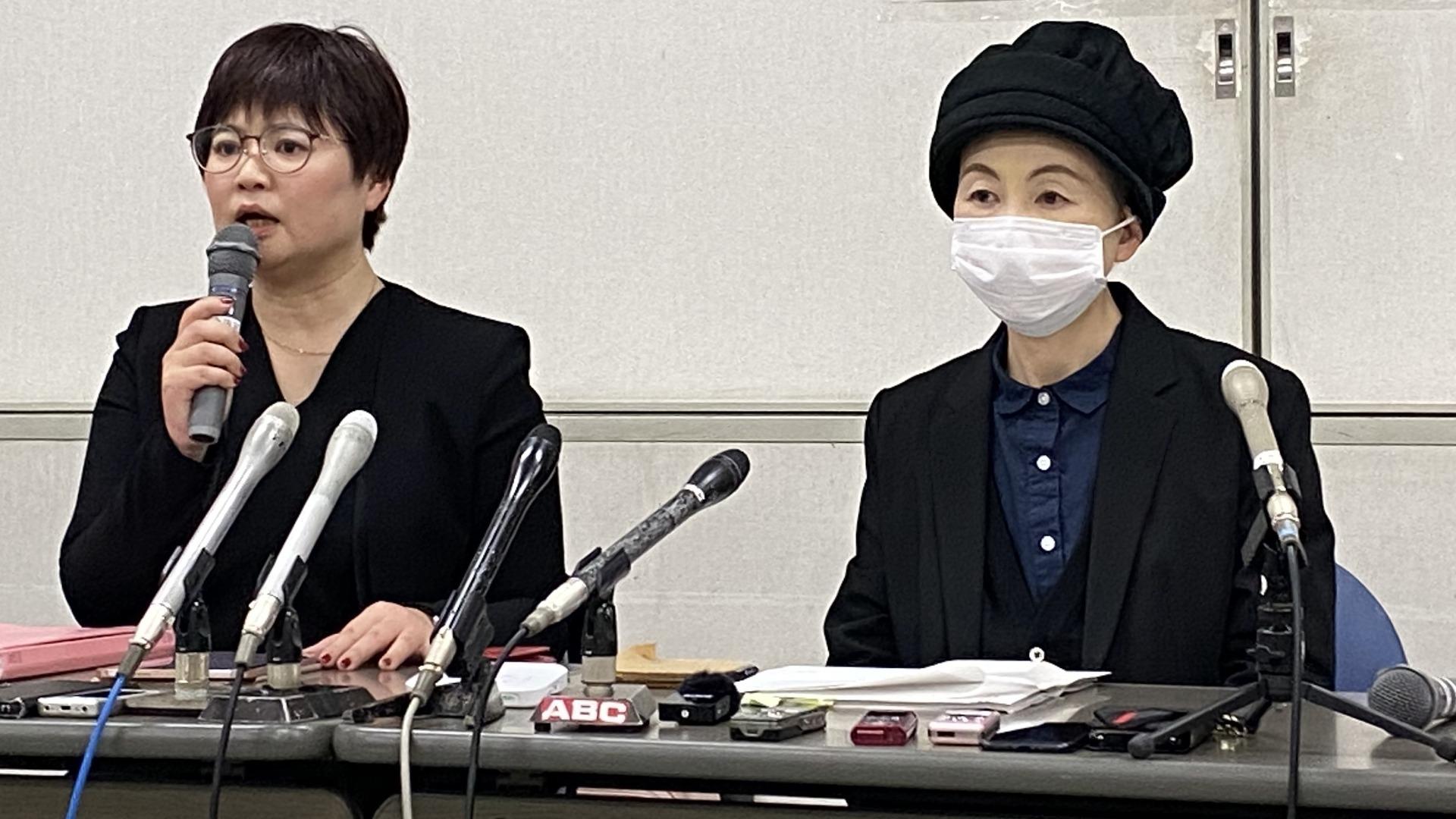読んで字の如く寺院住職のための情報誌。住職以外にも最近は読者が多いらしいですが。
2024年4月号「寺院住職実務情報誌 月刊住職」興山舎より。
一般読者もいるとはいえ、基本的には寺院住職のための専門誌をなぜ紹介するかというとこれ👇
大谷由香さんによる論考「ジェンダーレスの現代に女性差別的仏典をどう理解するべきなのか」嬉しいことに「第一回」となってますね。つまり連載ということ😆
仏教に限らず「性」は宗教にとって大事な問題であります。それは良い面ももちろんありますが👇
もともと原始仏典などにはしばしば女性差別的な文言が見られることは知られていました。
しかも最近はSNSなどで、それらの文言をいわば典拠にして、差別的な発言をする "仏教学者" まであらわれる始末😓
しかしそれは正しい仏典の読み方といえるのかというのが前述の論考といえそう。
もともと葬儀屋さんの服装(ヒールの👠着用)への問いかけから始まった#kutooから話を始め、いよいよ原始仏典の内容へ。
本来のインド哲学では人間に男女の差はなく、人が欲望にまみれるようになって初めて性差が生まれたとするそう。
だから欲望から解脱した仏陀は男性でも女性でもないはず。それが当時の社会の性差別を外部から取り入れる形で、仏陀は男性形をとるようになったと🥺
しかしそれで仏教の本質が全てねじ曲がったわけでもなく、仏教の歴史は、性差別とそれを克服する動きの両方の側面を持ちながら発展していったそう。
現代の仏教者は世俗社会が要請するジェンダーレスの動きを柔軟に受け入れながら、かつ先人が格闘した宗教と性の問題に真摯に向き合うことが大事だと指摘されています。
もし仏教界がそうできるのなら、その姿勢は世俗社会に対しても良い影響を与えるだろうとも🥹
今号の「月刊住職」、他の特集はやはり葬儀の問題が多かったですね。
葬送が多様化するいま、安易に商業化の道に走るのではなく、しかし広く門戸を開き他の業種とコラボしていくことが新しい葬送を形作っていくだろうという感じでした🙏

本・書籍ランキング