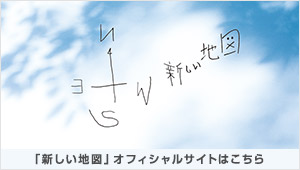無残に色褪せた花びらが
床に広げた雑誌の上に数枚
堕ちている事に気付き
ふ、と溜息
しばらく使っていなかった
部屋はそれでも微かに
あの日の匂いがする気がして
眩暈を誘う
思い出すと夢のようで
だけど夢ではなくて
確かに残る
眼差しに
追い詰められたのは
果たして
どちらなのだろう
逃げ出したい程の
胸を静かに焦がす
焔を
灯したのは
消してしまえと誰かが命じる
消してはいけないと誰かが祈る
ならば従わずに自らを
投じてしまえばいい
花を入れ換える
これは布告
次は涸れる前に
逢えるように
もうすぐ
夏がくる。