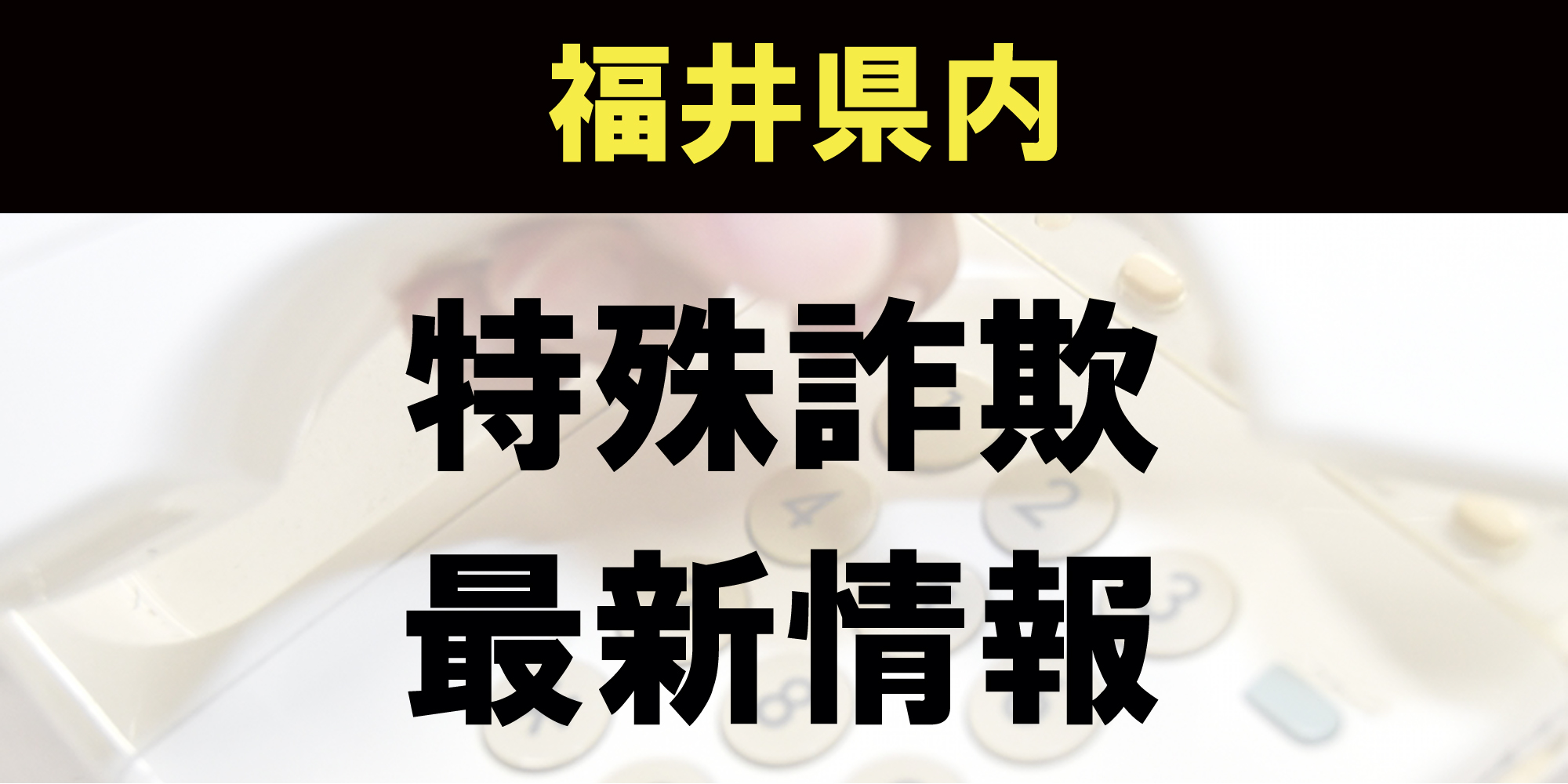狙われるリスクを減らす対策
全国各地で相次いだ広域強盗事件。中には被害者の命が奪われたケースもある。福井県内では2021年、住民がいる民家に男が侵入し、現金などが盗まれる事件が発生するなど、在宅中に押し入られる犯罪は都会に限った話ではない。自分や家族の命、財産をどう守ったらよいのか。全国で防犯セミナーなどを行う一般社団法人「日本防犯学校」(神奈川県)副学長で防犯アナリストの桜井礼子さん(60)は「防犯意識の高い暮らし方をすることが重要だ」と対策の必要性を訴えている。
■地方ほど無施錠
強盗事件が多発する理由について桜井さんは「ガラスを破ったりドアをこじ開けたりする技術が不要で、手っ取り早く金品が手に入るからではないか」と推測する。人がいると分かって押し入るため「危害を加えることをいとわない、開き直りに近い心理だ」と危険性を指摘する。
一戸建てが多い福井で不審者に押し入られるリスクを減らすため、桜井さんはインターホンが鳴ってすぐにドアを開ける行為を「絶対に避けて」と強調。「訪問者とのやりとりを対面でする時代ではない」といい、例えば宅配便は▽玄関先や宅配ボックスに置いてもらう▽コンビニや宅配ロッカーで受け取る▽ドアガードやチェーンをかけたままやりとりする−ことを心がけてほしいとする。
防犯対策の基本は玄関や窓の鍵かけだが、地方ほど無施錠の家が増える傾向にあると桜井さん。「近所の人が野菜を置いてくれるから」などが理由だが「むしろご近所さんと顔を合わせたら、『鍵をかけてきたか』と確認し合う習慣をつけてほしい」と助言する。
さらに▽通りから目に付く部屋は夜間も明かりをつけておく▽インターホンを門柱に移設し、敷地内に人を立ち入らせない▽センサーライトやカメラの設置▽防犯ガラス、フィルムの導入−なども有効という。
■侵入者には従う
万が一、在宅中に侵入者と出くわしたらどうしたらよいのか。桜井さんは「逆らわず相手に従って。襲われる危険性が高く、命を守ることを最優先に考えて」と強調する。金品のありかや金額などを把握した上で犯行に及んでいる可能性があるため、うそをつかず、ためらわずに渡すべきという。1人暮らしの高齢者などは、ペンダント型の緊急通報装置を常にぶら下げておくと安心感が高まるという。
合わせて桜井さんは「私たちの個人情報はある程度漏れていると考えた方がいい」と指摘。実在の放送局や番組名をかたり、アンケート名目で▽家族構成▽年代▽現金が家にいくらあるか▽預金先−などを聞き出そうとした事例もある。情報屋と呼ばれる業者から個人情報のリストを入手し、利用している犯罪者もいるという。
犯行を未然に防ぐ上で重要なのが、住民の目撃情報。桜井さんは「犯人は必ず下見をする」といい、他地域ナンバーの車やレンタカー、見知らぬ人が同じ場所を回っているなど違和感のある行動を認識したら、すぐに110番か警察相談専用電話「#9110」へ連絡してほしいと呼びかける。「自分の目を信じて、ちゅうちょせず連絡することが犯罪の阻止につながる」と話していた。
名古屋市緑区の70代の女性が、介護施設の職員を名乗る男らに現金約4400万円をだまし取られました。
警察によりますと去年8月ごろ、緑区に住む70代の女性に介護施設の斡旋業者を名乗る男から「老人ホームに入りたい人のため、名義を貸してほしい」などと電話がありました。
女性が承諾すると、その後、介護施設の職員や弁護士を名乗る男らから、電話で「名義を貸すことは犯罪となる」「口座が使えなくなるので、預金を他の口座へ移さなければならない」などと説明を受け、女性は去年9月から10月にかけて5回にわたり、現金合わせて約4400万円を指示された口座に振り込んだということです。
女性はネットバンキングの預金500万円分も別の口座に振り替えていて、警察は、この金もだまし取られた可能性があるとみて調べています。
山梨県内で昨年、電話詐欺被害に77人が遭い、過去5年で最多だったことがわかった。県警が24日発表した。被害者のほとんどは「遭わない自信があった」と県警のアンケートに回答した。県警は「電話でお金の話が出てきたら詐欺を疑って」と注意を呼びかけている。
県警が確認した昨年1年間の電話詐欺の被害者は77人に上る。前年より21人増えた。被害総額は約1億4484万円(前年比434万円減)で、11年連続で1億円を超えている。
被害者の9割近くが女性で、年代別では65歳以上が83%だった。県警生活安全企画課は「(女性も高齢者も)在宅率が高いのが大きく関係している」とみている。
一方、詐欺被害が未然に阻止されたケースは67件で前年より9件減った。資産状況などを聞き出そうとする犯罪の予兆電話「アポ電(アポイントメント電話)」は967件で23件増えた。
県警は被害者77人を対象に、アンケートを実施。詐欺に遭わない自信について問い、「あった」「とてもあった」と回答したのは合わせて71%に上った。電話詐欺の手口をテレビや新聞などで「知っていた」と回答した人は57%だった。
だが、電話を受けた時点で、詐欺の可能性を考えた人はわずか14%だった。同課は「非通知の着信は詐欺の可能性が大きい」と指摘。電話機に着信番号が表示されるナンバーディスプレー機能が付いていた人は33%にとどまっていたという。
家族で電話詐欺対策を立てていなかった人は78%に上った。電話先でお金に関する話題が出たら、家族が相談に乗るということを、前もって申し合わせておくことが詐欺被害防止の第一歩だという。
自宅の電話を常に留守電設定にし、不審電話を録音できるようにすることも効き目があるという。県警は、電話をかけてきた相手に警告メッセージを自動で流し、会話記録を残す対策機器の貸し出しを最寄りの警察署で受け付けている。
電話詐欺で多い手口には、息子や親類を装って現金を振り込ませるなどしてだまし取る「オレオレ詐欺」、自治体職員などと偽って保険料の払い戻しなどを持ちかける「還付金詐欺」がある。「詐欺の電話はどの家庭にもかかってくる」として県警はより一層の警戒を呼びかけている。(池田拓哉)
◇
■県警からの呼びかけ
・自宅の固定電話が鳴ったら警戒する
・息子や孫を名乗っても詐欺を疑う
・携帯電話をかけながらATMを操作しない
・電話でお金の要求や、還付金の手続きの話が出たら詐欺を疑う
・電話でお金の話が出たら、すぐに電話を切って家族や警察に相談する
・現金を他人に渡さない
◇
山梨市出身の芸人で俳優のマキタスポーツさん(53)が詐欺被害の防止に一役買っている。富士吉田署(富士吉田市)が昨年末から管内で掲示している啓発ポスターに登場している。
マキタさんは日川高、国士舘大の卒業生。高校と大学の同窓にあたる広川勉署長に「被害防止に役立ちたい」と申し出たという。
ポスターには大きく「ちょっと待キタ!」の文字。被害者が金融機関に振り込んだ現金をATMから引き出す犯罪グループの「出し子」にマキタさんが扮した。言葉や設定はマキタさんが考えたという。
ポスターには「振り込む前に、まず相談を」など警察からの呼びかけも入り、金融機関などに約30枚配られた。評判も上々で、金融機関からは「街中のATMにも貼り出したい」と追加注文が寄せられているという。
「『アダルトサイトを見て楽しんでいるあなたの動画を所有している。拡散されたくなければ暗号資産を送るように』とメールが届いた」との相談がありました。また、「アダルトサイトを見ていたら、いきなり購入成立に切り替わり、高額の請求を受けた」との相談が多くありました。
アダルトサイトに関する相談は減少傾向にありますが、本年度では50代と60代が特に多い状況です。ネット上で、登録完了画面等を表示することで契約が成立したと思わせ、サイト利用料等の名目で支払わせる手口をワンクリック請求と言います。
最近では、暗号資産や電子マネー、個人名義の口座への振り込みを求めるケースも多いようです。電子消費者契約法では、契約が成立する前の画面で契約内容を確認できるようになっていないなどの場合は、消費者が勘違いによる契約の取り消しを主張することができます。
サイトに接続しただけでは、個人を特定する情報が業者に知られることはありません。心当たりのない料金の請求を受けても業者に連絡をしない、また、慌ててお金を支払わないようにしましょう。
福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。