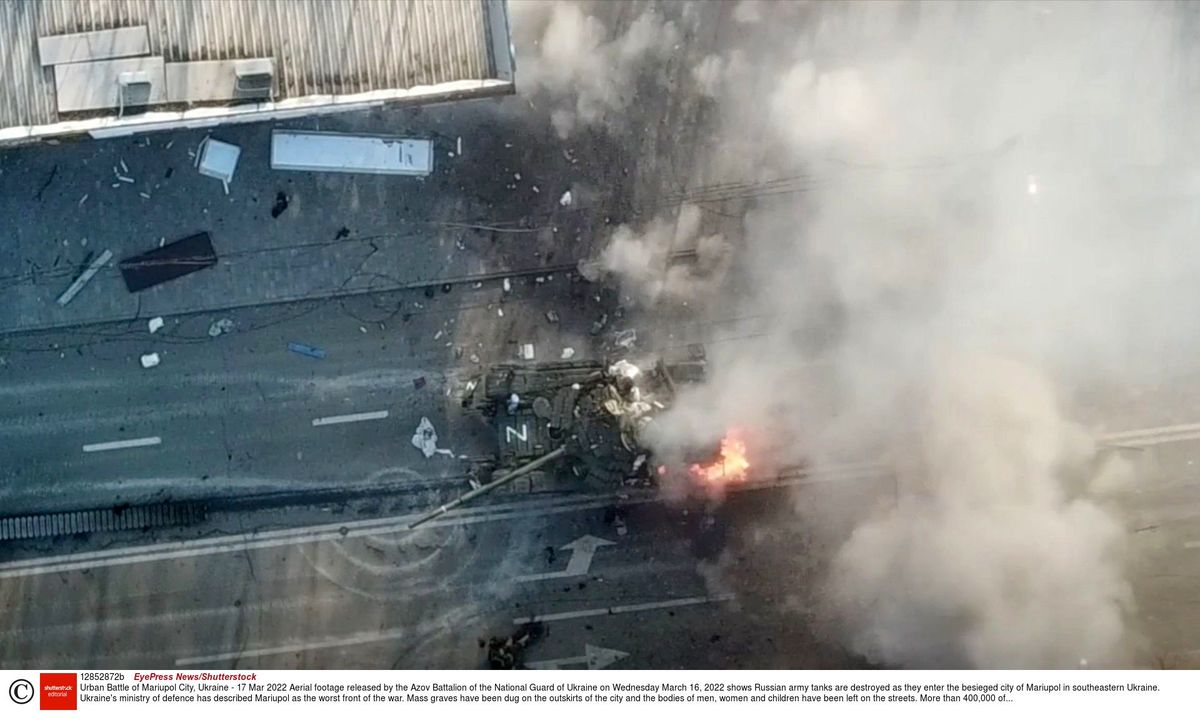松江市の宍道駅と広島県庄原市の備後落合駅を結ぶJR木次線。窓がない開放的な車内を爽やかな風が吹き抜け、新緑を間近に楽しめる観光トロッコ列車「奥出雲おろち号」は、利用が低迷する木次線で絶大な人気を誇る。4月下旬、1席だけ残っていたチケットを買って乗り込んだ。
おろち号は、1998年に運行を開始した。窓がないトロッコ車両と悪天候時のための控え車両、ディーゼル機関車の3両編成だ。春から秋にかけて土日祝日を中心に運行し、木次駅(雲南市木次町)―備後落合駅間の60・8キロ(一部は出雲市駅から運行)を1日1往復する。全国の鉄道ファンに愛されてきたが、JR西日本が老朽化を理由に2023年度での運行終了を決めている。
木次駅を出発すると、列車は険しい中国山地へと進んでいく。50分ほどで、松本清張の名作「砂の器」の舞台となった亀嵩(かめだけ)駅(奥出雲町)に到着した。
駅舎内の「扇屋そば」店主で、法被に駅長の帽子姿の杠(ゆずりは)哲也さん(59)がホームでお出迎え。名物のそば弁当(乗車当日午前10時までに要予約)を窓枠越しに、手渡してくれた。国産のそばの実を石臼でひき、奥出雲の天然水を使って手打ちで仕上げたというそばは、コシがあって風味豊か。長芋とろろと温泉卵が添えてある。心地よい風を感じ、田植え前の水が張られた田んぼや、芽吹いたばかりの若葉を眺めながらのんびりと味わうのは、ここでしか体験できないぜいたくだろう。
◇珍しい「三段式スイッチバック」
列車は出雲坂根駅(同町)での小休止を挟み、全国的にも珍しい「三段式スイッチバック」へと進む。次の三井(みい)野原駅(奥出雲町)は標高727メートルで、JR西管内では最も高い。直線距離では1・4キロしかなく、標高差162メートルの急勾配を上るため、車両の進行方向を2回、切り替えながら、ジグザグに上っていく。少し前に通ったばかりの線路や出雲坂根駅舎がはるか下方に見えるのが、なんとも不思議。鉄道ファンの聖地と言われるだけあって、乗客が熱心に動画を撮影していた。
列車はさらに上り、日本最大級の二重ループ橋「奥出雲おろちループ」(国道314号)を見渡せる地点へ。どこまでも連なる壮大な山々を背景に、赤いアーチがかかる三井野大橋が見えるポイントでは、速度を落として走行。乗客は息をのんで絶景に見とれていた。
山あいを縫うように走り、豊かな自然を間近に楽しめたおろち号の旅。途中、下校中の小学生らが列車に手を振り、出雲八代駅(同町)では保育園児が元気いっぱいの歌で迎えてくれた。沿線の人々の木次線やおろち号への愛情を改めて感じ、心が温かくなった。【松江支局・松原隼斗】
◇
JR西日本が今春、利用者数が減少し、路線維持が困難として公表したローカル線に中国4県の記者が乗り、列車や沿線の魅力を再発見する。
迷えるお遍路さん最強の「お供」 四国八十八カ所で試行中2022/05/03 07:30 毎日新聞
四国八十八カ所の札所を回る「お遍路さん」。札所の間の遍路道も歩くとなると、ガイドブックが荷物になりしんどい。一方、地元は若い世代にも自分の足で歩くお遍路の魅力に気づいてもらおうと、知恵を絞ってきた。今、お遍路を支援する最強の「お供」を準備しようという動きがあるという。一体どんな「お供」なのか。
四国遍路道の全長は歩くルートによって諸説あるが、1200〜1400キロとされる。弘法大師もかつて通った昔ながらの景観を感じられるのが魅力だ。徳島県のガイドグループ「加茂谷へんろ道の会」によると、年々、歩き遍路の人数は減ってリピーターは高齢化しているという。若い世代は仕事を長期間休めず、札所の間を車で移動することが多い。若者にいかに歩き遍路に興味を持ってもらうかが地元にとって課題となっている。
加茂谷へんろ道の会は4月20日、地元の阿南信用金庫(徳島県阿南市)の20代前半の新人職員ら14人に歩き遍路を体験してもらう新人研修を実施。四国最古の遍路道を含め、20番札所の「鶴林寺」(同県勝浦町)から21番札所の「太龍寺」(阿南市)までの4・5キロを歩いてもらった。6年前に車で「お遍路」をしたという同信金の田中舞さん(38)は「札所同士の間を歩くと、分岐点でどの方向に行けばいいのか気付くのが大変」と語った。
◇1000人の目で「電子マップ」試作
こうした課題を解決すると期待されるのが冒頭の「お供」だ。遍路道の世界遺産登録を目指して活動しているNPO法人「遍路とおもてなしのネットワーク」(高松市)が試作している電子マップ。スマートフォン上で地図をクリックすれば、路面の状況や大雨などで通行が難しい場合の迂回(うかい)路、道の歴史的意義などを瞬時に調べることができる。2月に参加者を募り、遍路道を一斉点検するなどして1000人以上の目で見たデータを蓄積した。
宍戸栄徳事務局長は「道路情報や迂回(うかい)路などをリアルタイムで把握できる電子マップはない。遍路道をよく知らない人にも関心を持ってもらい歩くことに役立ててほしい」と期待する。
ただ、課題もあるという。誰でも匿名で情報を書き込めるようにすると、短時間で多くの情報が寄せられて量的に充実するが、書き込まれた内容の正確さや真偽を担保しきれなくなる。「誰が書き込んだか、ある程度文責をはっきりさせることなどを検討しなければならない」と話す。
一方、札所でも最近はインターネットでの情報発信に力を入れている。徳島県上坂町の6番札所、安楽寺のホームページでは寺の歴史や施設の案内を写真やイラストをふんだんに使って紹介。写真共有アプリ「インスタグラム」のアカウントも開設し、2000人超のフォロワーがいる。
◇特別拝観でウクライナを支援
ロシアに侵攻されたウクライナを支援しようと、4月から停戦までをめどに、拝観料400円の全額を駐日ウクライナ大使館(東京)に寄付する特別拝観を開始。普段は宿坊での宿泊客しか入れない本堂奥の仏教体験部屋や性霊殿などに僧侶の案内で入れるようにし、募金箱も設置した。畠田裕峰副住職は「今回のような企画を周知するには、ネットでの発信が効果的。四国全行程の電子マップができたら寺の企画もリンクを貼ってもらうなりして連携するようにしたい」と話す。
遍路道を歩く場合、札所でのお勤めの時間、自分の食事時間、宿泊先への到着時間などを盛り込んで計画を立てるので時間に余裕がない。遍路道でスマホを使うことが主流になって時間に余裕ができ、新たな「歩きお遍路さん」のスタイルが生まれるかもしれない。【山本芳博】