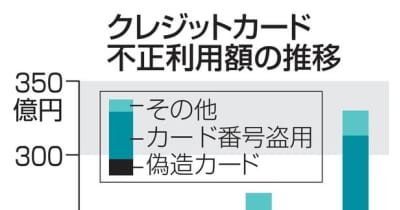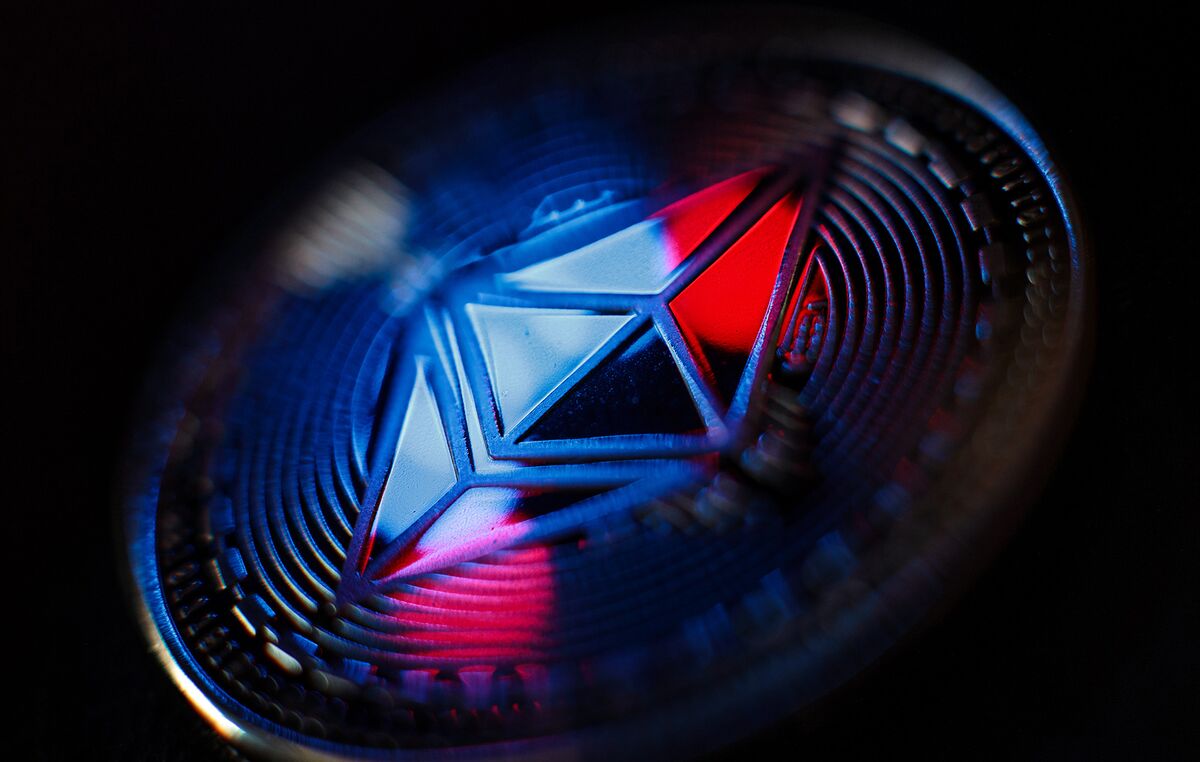■返金されず
市消費生活センターによると、相談を寄せた男性(24)は、中学時代の同級生から会員制交流サイト(SNS)で「もうかる」と誘われ、競馬の自動投票ソフト(77万円)を買うよう勧められた。「お金がない」と断ったが「自分も消費者金融で借りた」と同級生から借金を勧められ、投資分と合わせて100万円を借りた。
ソフトを試すと利益は出ず、契約解除できるクーリングオフ期間も過ぎ、借金返済に困った。同級生に相談すると「こういう方法もある」と、友人を紹介して契約できれば仲介料が入る会員勧誘を勧められた。男性は10人ほど誘ったが契約には至らず、結局、借金だけが残った。
「後出しマルチ」は、商品を買わせた後、投資を回収するために次の購入者を紹介して利益を得ることを告げる手法。一体的に見れば特定商取引法が規制する連鎖販売取引「マルチ商法」だが、初めはソフトなどの売買契約のため気付かない。
こうした手法による被害相談が県や市の消費生活センターに寄せられている。最近では、クーリングオフしても返金されないケースがある。
同じように友人に誘われ、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ソフト(77万円)を借金して買った男性(22)は、センターを介してクーリングオフできたが、半年たっても代金が戻らない。業者側は「順番で返金していて、プール金がない」と弁明しているという。
■違法性認定
業者側を訴えた人もいる。県弁護士会の消費問題対策委員会によると、県内では2019年から少なくとも12人が提訴。このうち10人が損害賠償を求め共同で訴えた訴訟の水戸地裁判決では、利益が出ないソフトを「もうかる」と言って売った行為が「事実不告知」「不実告知」に当たるなどとして、業者側の違法性を認めた。ただ、同委員会によると、判決は確定したものの実際に賠償されるかどうかは不明という。
狙われるのは、社会経験の乏しい若者ばかりだ。原告のほとんどは契約当時、20〜23歳。市が相談を受けたケースでは、20歳の誕生日当日に勧誘された人もいる。
4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられると、狙われる対象が広がる。未成年が保護者らの同意なしに行った契約は原則取り消せるが、4月から18、19歳には適用されない。市消費生活センターの田山知賀子センター長は「(高校生や大学生が)社会に出る前に債務者になってしまう」と心配する。
悪質な「マルチ商法」の特徴として、被害者が加害者に転じる危険性を指摘する声が上がる。同センターには「娘のマルチをやめさせたい」という親からの相談もあった。勧誘の多くは同世代の友人や同級生で、恨みを買うことにもなりかねない。県弁護士会も「築き上げた関係が壊れることになる」と注意を呼び掛けている。
岡山市内で発生した特殊詐欺事件を発端に、岡山県警が全国的な詐欺組織の壊滅へと迫っている。昨年夏頃から幹部を次々と摘発し、先月にはついに組織トップの逮捕に至った。県警は組織のメンバーの大半を逮捕したとみており、「全容解明に向け、今後も捜査を尽くす」としている。(上万俊弥)
発端は2020年3月、岡山市の高齢女性が電話で「あなたの口座から勝手に高額商品が購入された。口座を停止する手続きで必要」などと言われ、だまし取られたキャッシュカードから100万円を引き出された。通報を受けた県警は、カードを受け取った「受け子」役の広島市の少年を詐欺容疑で逮捕。この少年から組織上層部への「突き上げ捜査」を開始した。
組織末端の受け子や金を引き出す「出し子」などは逮捕されやすく、持っている情報は乏しい。しかし、捜査員は少年の交友関係やSNSのやりとりを徹底的に分析し、リクルーター役や受け子を束ねる元締役の男などを次々と摘発した。
捜査が新たな局面を迎えたのが、同年12月。元締役の男の関係先として浮上した東京都内のマンションの一室が、詐欺電話をかける「かけ場」であることを突き止め、「かけ子」の男3人を逮捕した。かけ子は取り調べで組織幹部とのやりとりを供述。この東京の拠点の摘発により、捜査は大きく進展した。
被害額1億円突破…2月末時点
詐欺組織の摘発が進む一方、県内では詐欺被害が相次いでいる。2月末時点で被害額が1億円を突破、昨年同期を上回っている。
県警生活安全企画課によると、今年の被害額は2月末までに41件約1億1160万円に達し、昨年同期の23件約7720万円より悪化している。発生のうち、介護保険料などが返ってくるとだまして金を振り込ませる還付金詐欺が19件と、約半分を占めた。
高額被害も発生している。昨年10〜12月、岡山市の70歳代女性宅に、証券会社社員を名乗る男から「外国通貨を優先的に購入する権利がある。購入しないなら他の人へ権利を譲ってほしい」と電話があった。
女性が承諾すると、後日、他の証券会社や金融機関の職員を名乗る男らから「あなたのやったことは名義貸しで犯罪だ」「示談するためにお金を振り込んで」などと言われた。12月下旬に相手側と連絡が取れなくなるまで、示談名目などで計約4200万円をだまし取られた。
様々な役職や人物を演じる「劇場型」と言われる手口で、被害者は自分が悪く、相手が親身になって相談に応じてくれていると思い込み、高額なお金を振り込んでしまうという。
同課は「『自分は大丈夫』と思っていても、だまされてしまう。お金の話が出たらすぐに警察や家族、近所の人に相談し、留守番電話機能も活用してほしい」と呼びかけている。