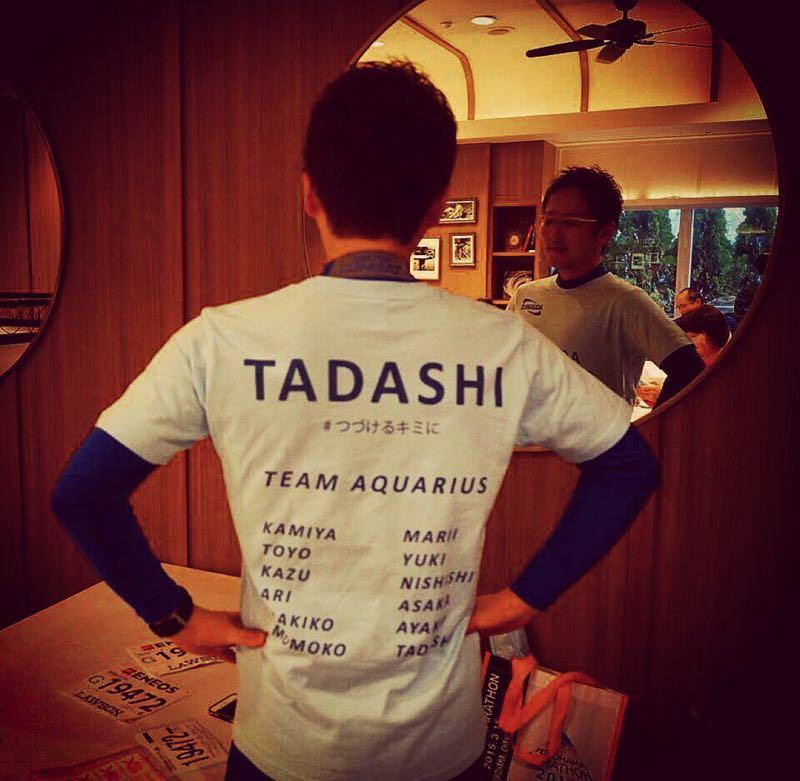コロナの経口治療薬が出ることになりそうです。
新薬ですね。
いっつも思うのは、ワクチンはダメで経口薬ならOKっていう考え方。
ワクチンの量はたかだか0.3ml×2回。
経口抗ウィルス薬となると、例えば現行で言えば抗インフルエンザのタミフルなんかは1日150mgを5日間投与、わりと身近なヘルペスに使うバラシクロビルなんかは1日1000mgもの量を数日間投与します。
もちろんモノも量も単位も違うけれど、抗ウィルス薬となるとこれだけの量の薬剤を身体に「入れる」ことになるわけです。
ましてやコロナ治療薬の新薬ともなれば、これまで人類が「入れた」経験のない未知のお薬ということになるわけです。
それは何故怖がらないのかね?
何故反対運動しないのかね??
僕らに医者に言わせれば、ワクチンの副作用よりも経口抗ウィルス薬の副作用の方がずっと恐いし重い。
なぜなら投与量が半端なく多いから。
そして絶対に忘れてはならないのは耐性ウィルス。
ただでさえデルタ株だとか急速に変異して生き残ろうとしてるウィルスです。
薬剤を投与すれば早々に学習して耐性化するのは目に見えてます。
みんなが気軽に経口薬を飲める世の中になったら何が起こるか、誰も言おうとしない。
治療薬の乱用が耐性化を引き起こし、そしてその結果、本当にこの薬での治療を必要とする重症患者さんが救えなくなる・・・
コロナの治療薬がタミフルみたいにならないように祈るばかりです。
児童心理の専門家らが子育て支援を行う「NPOふくおか子どものこころサポート研究所」(福岡市)には、子育てに悩む親からの相談が寄せられている。最近多いのは、「子どものゲームやユーチューブの視聴をやめさせるのが難しい」という相談。コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えたためとみられ、親子ともにイライラの原因となっている家庭が多いそうだ。
研究所の共同代表の山下雅子さん(47)は、「子どもたちはこれまで、運動会などの学校行事が中止や延期となり、やりたいことができずに、ストレスをためてきた。諦めてばかりだと、無気力につながる恐れがある」と指摘する。予定の変更が続いたことも、親子の心の負担を増やしているという。
子どもの心の健康を保つために心がけていきたいのが、「自分でできた」という体験を重ねることだ。例えば、〈クッキーを一緒に作る〉〈本を5分間読む〉〈近くの公園でお弁当を食べる〉など、身近なことでいい。具体的な計画を立てて実行することで自信が培われ、達成感を味わえる。親が「よくできたね」「ありがとう」などの肯定的な言葉をかけることも大切だ。
子どもがゲームなどをやめられない場合も、一方的に叱るのではなく、まず親子で話し合って「1日1時間まで」などルールを決めることから始める。それでも切り替えが難しい子には、5分前などに「そろそろよ」と声をかけるとスムーズ。決めた時間を紙に書き、目に付きやすい場所に貼っておくのもいい。山下さんは「子どもが『自分でやめられた』と思える方法を見つけて」と話す。
親も、ひと息つく時間を持ち、ストレスを減らそう。困りごとや不安があれば、誰かに相談すると心が落ち着く。対面で人と話せる機会がなくても、オンラインでの相談窓口も増えているので、利用するといい。
山下さんは「子どもへの関わり方を工夫することで、気持ちが楽になり、親子の笑顔も増えますよ」と呼びかける。
(このシリーズは堀美緒が担当しました)
親子の心の健康を保つために心がけるポイントの例
・絵を描く、本を読むなど、限られた場所でも楽しめる活動をする
・笑うことは不安やイライラをやわらげる。日常から笑顔になれるようなユーモアを持つ
・意見や感情を隠したり抑え込んだりせず、周囲の人と共有する
・電話やSNSなどで家族や友人とのつながりを保つ
・不安や怒りなど、ネガティブな感情に気付いたら、心を休ませる合図だと考えるようにする
(山下さんの話を基に作成)
外装リフォーム専門会社「ヤネカベ」の関口亮さんによれば、雨漏りの相談は通年あるが、特に増えるのが、台風シーズンだという。
「多い時は一日中電話が鳴りっぱなしで、相談数が60〜70件という日もあります」(関口さん)
関口さんは雨漏り診断士(民間資格)を有し、これまで2000件以上の雨漏りを診断。台風時に雨漏りの相談が増えるのは、雨水が外壁から漏れていても、防水シートのおかげで普段は雨漏りという目に見える形で現れにくいから。しかし台風による大雨で“許容量”を超えると、雨漏りが起こってしまう。
「雨漏りの量が少ないから平気だろうと考えていたら大間違いです。雨漏りがある場合、雨水がすでに家の内部を伝わっている。この状態が長く続くと、家の柱や梁が腐るばかりか、カビの繁殖につながりかねないのです」(関口さん)
カビで懸念されるのが、体への悪影響だ。複数の企業の産業医を務める「リバランス」代表の池井佑丞医師が言う。
「カビが引き起こす疾患として、まずは感染症が挙げられます。肺アスペルギルス症や肺クリプトコックス症などが知られますが、ただ、カビの感染症は免疫力が著しく低下した人に見られ、健康な人で発症することはまれ。一方、注意すべきはアレルギー疾患。カビは、アレルギー性鼻炎や喘息、蕁麻疹といったアレルギー疾患を悪化させる原因になるのです」
私たちの体には、異物が侵入してきた時、それらに対抗する「免疫」という仕組みが備わっている。
ところが、この免疫の仕組みが体に害を与えない物にも過剰に反応し、攻撃をしてしまうことがある。これがアレルギーで、その原因物質をアレルゲンという。
■カビ掃除には必ずマスクを着用する
カビは、花粉、ホコリ、ダニなどと並ぶ代表的なアレルゲンのひとつ。例えば、一般的な生活環境のどこでも繁殖するコウジカビは重症喘息の原因となる。雷雨の後に増加する傾向にあるクロカビは、若年の成人喘息の患者でクロカビにアレルギーを持っている場合、重症例が多いことが報告されている。高い湿度を好むススカビは喘息や鼻炎の原因となり、アレルギー性の副鼻腔炎も起こしやすい。
「ダニやホコリに気をつけている人は多いですが、カビは見落としがち。アレルギー性疾患がある人、特に雨の多い時期にひどくなるといった人は、カビとの関連も疑った方がいいでしょう」(池井さん)
カビが好むのは、気温20〜30度、湿度70〜80%の環境だ。現在の住環境は気密性が高く、暖房器具も用いるので、冬でもカビにとっては好環境。コロナ対策で加湿剤を用いていると、よりカビは季節を問わず繁殖しやすくなる。
「カビ対策の基本は、換気で室内の風通しを良くし、除湿剤で湿気がたまらないようにすること。浴室や洗面所などはもちろん、家具の裏、クローゼットや押し入れ、エアコンはカビが繁殖しやすい」(池井さん)
意外なカビの繁殖場所としては、靴の中。夏の間、ブーツをクローゼットの中に収納しておいた人もいるだろうが、「出してみたらカビがぎっしり」ということは、珍しくない。
「カビが繁殖している場合、その掃除にも気をつけてください。拭き取ったり消毒液を吹きかけた際にカビが舞い上がり、空気中に漂ってしまう。それを吸い込んで、アレルギー疾患を悪化させてしまうかもしれません」(池井さん)
必ずマスクをつけて対処するべきだ。
■雨漏りが起こる場所
「雨漏りが起こる場所は、私の経験値だと、外壁から9割、屋根から1割。雨漏りに気付いていない人もいますが、そういう場合は、ベランダの笠木の付け根やサッシ下に隙間がないかなど、それ以外でも施主自身が気付けることがよくある」(「ヤネカベ」の関口亮さん)
とりあえずチェックだ。
市教委によると、同日午前8時25分頃、学級担任がフッ化物を含んだ液体を紙コップに入れて児童に配布する際、誤って近くにあった手指消毒用アルコールを入れて配った。洗口後に担任が誤配布に気付き、児童24人全員がはき出した。
同小では週1回、フッ化物洗口を行っている。今後は、作業台に不必要なものを置かないことや、洗口前に液体のにおいを確認することなどの再発防止策を徹底するという。