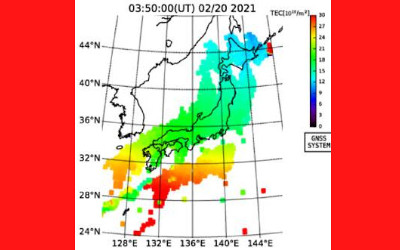東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島3県で整備された約3万戸の災害公営住宅(復興住宅)のうち、「戸建て型」が3割近くの約8000戸に達し、1戸当たりの整備費はマンション型より約550万円安かったことが、読売新聞の調査で分かった。多く早く造れるマンション型に比べ、戸建ては土地取得などに時間がかかるが、住民ニーズなどを踏まえて管内の全復興住宅が戸建ての自治体も18あった。
読売新聞は今年1〜2月、3県内で復興住宅を建設した56市町村と、岩手、福島両県の計58自治体に調査を実施。昨年末までに整備された計2万9649戸のうち、マンション型が2万1587戸(73%)、長屋を含む戸建て型が8062戸(27%)だった。
マンション型は1か所で多くの戸数を整備できるが、住宅内の様子が分かりにくく、孤独死などのリスクもある。一方、戸建て型はマンションより広い土地が必要で整備に時間がかかるが、住宅への出入り時などに住民同士が交流しやすい。
総務省の「住宅・土地統計調査」(2008年)によると、全住宅に占める戸建ての割合は全国平均の58%に対し、3県は70%。戸建てが多い土地柄だったこともあり、福島県楢葉町(158戸)や岩手県野田村(100戸)など18自治体は全戸を戸建てとした。町内の9割以上(453戸)を戸建てとした宮城県山元町の担当者は「住民の意向を重視した」と説明する。
これに対し、岩手県陸前高田市(895戸)や宮城県多賀城市(532戸)はすべてがマンション型。「スピードは重要だった」(陸前高田市)という。
土地代を除く1戸の整備費の平均額は、戸建て型が2141万円、マンション型は2686万円。マンション型はエレベーターや集会所などの施設整備や、耐震化コストがかかるため費用がかさんだとみられる。
1995年の阪神大震災では約2万5000戸の復興住宅が新たに整備されたが、ほぼすべてがマンション型だった。2004年の新潟県中越地震では、336戸のうち約2割の71戸が戸建てで造られた。
岩手大の麦倉哲教授(災害社会学)の話「戸建て型は地方の暮らしに合っているが、一方で都市的な密室性の高さを求める人もおり、マンション型も必要だ。ともに利点と欠点があり、自治体にとっては難しい判断だが、土地柄や居住者の生活様式を踏まえ、共助の関係を築ける環境の整備が求められている」
◆災害公営住宅(復興住宅)=災害で家を失った住民向けに自治体が安価な家賃で提供する住宅。形状は各自治体が決め、建設業者などに委託して建設する。県営の住宅も市町村と協議して整備方針が決まることが多い。東日本大震災では国が整備費の8分の7を補助。同震災では茨城など8県で計3万戸余りが整備され、うち99%を岩手、宮城、福島の3県が占める。