厄年の方をはじめ、厄年じゃない人でも今年1年の開運を願い、厄除けお守りを買う人は少なくありません。
そんな厄除けお守りは、どこにつけるのが最も効果的なのか、どこに置くのが正解なのか気になりますよね。せっかくのご利益を最大限高められるところに置きたいものです。
今回は、厄除けお守りの効果的な持ち方、身につけ方、置き場所などを紹介します。
厄除けのお守りを買ったはいいものの、どこにつけるか、どこに置くのが迷ってしまうこともありますよね。今回は、厄除けお守りの効果が高まる持ち方や置き場所などを紹介します。
厄除けお守りの効果的な持ち方・身につけ方
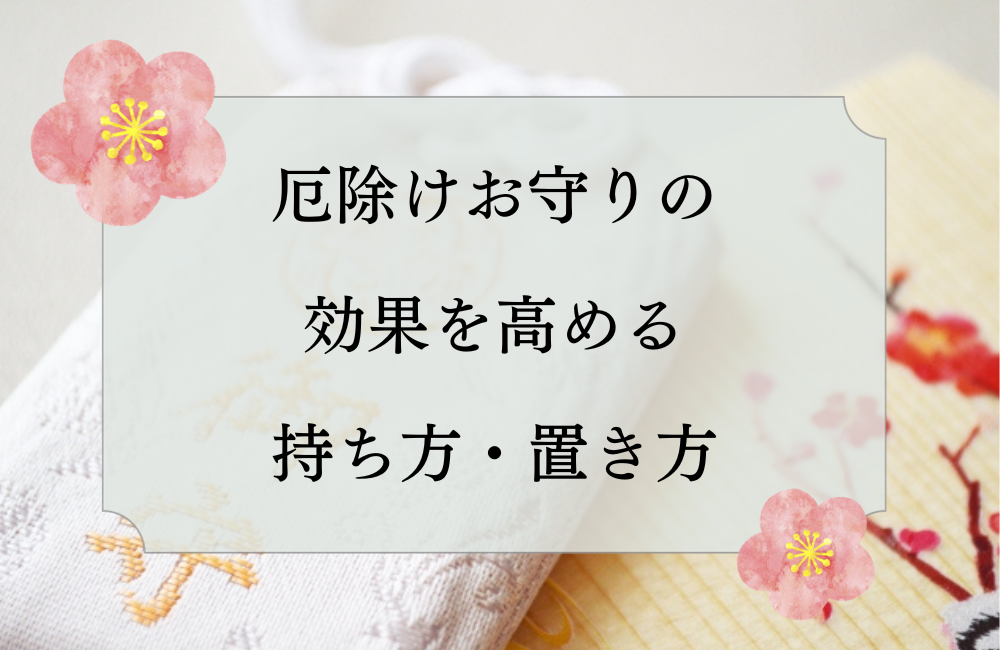
厄除けのお守りはどのように持ち歩くべきなのか、身につけるのには、どのようにしたらいいのか?初めてお守りを持つ人にとって、お守りの持ち方は分からないことが多いと思います。そこで、厄除けのお守りの持ち方と身につけ方をまとめたのでご参考にしてください。
1. 上着のポケットに入れる
会社などに着ていくスーツの内側のポケットか、ジャケットの内側のポケットに入れて持ち歩くのも効果が期待できます。心臓に近い部分になるので、清らかな心を常に意識することができ、普段以上に慎重になることもでき、一番効果が期待できるかもしれません。
この場合、スーツが汚れている場合や、内側のポケットに色々な物があるよりは、お守りだけを入れると良いでしょう。スーツやジャケットに入れっぱなしはよくないので、自宅に帰宅したらお守りを出し神棚に置くか、自分の目線より高い場所に置くと良いです。神様を見下すのではなく、神様は常に上へと意識してください。
2. お財布に入れる
毎日持ち歩くと良いお守りですが、バックを持ち歩かない人は、お財布にお守りを入れることをお勧めします。ただし、お財布をズボンのおしりのポケットに入れて持ち歩く人もいますが、この方法はお勧めしません。
お財布をお尻のポケットに入れる場合、お財布にお守りを入れないでください。お守りは、神様の依代(よりしろ)と言われています。依代とは、神様が降臨する時に宿る場所のことです。つまり、神様のお守りに宿るのに、お尻を向けているのと同じことで大変失礼なことなので、避けてください。
3. カバンに身につける
お守りは大切に保管するのではなく、普段使うカバンなどに入れて持ち歩くことをお勧めします。ただし、お守りは、神様が宿る場所でもあるので、カバンの中をキレイに整頓するようにしましょう。
ゴミが入っていたり、整理整頓されていないのは、神様が宿るお守りを身につけていても、ご利益を期待することはできません。むしろ、神様が宿るお守りに対して大変失礼なことをしているということになります。カバンに入れて身につける場合は、カバンの中をキレイにしましょう。
厄除けお守り・お札の置き場所と方角

お守りは基本、持ち歩くものなので、自宅でお守りを置く場所についてですが、神棚がある場合は神棚に置くと良いですね。ただし、神棚がないという方もいるので、その場合部屋の中で一番高い場所に置くようにしてください。
そして、置く場所は常に綺麗な環境に置くようにしましょう。埃まみれの掃除されていない環境にお守りを置くのはいけません。お守りには神様が宿るとされています。また、気になる方は、更に半紙の上などの置くのも良いでしょう。
それから、自宅でお守りを置く方角に決まりがあるか気にされる方もいますが、神棚があれば神棚の向いている方が東を向いていると思うので、特別変える必要はありません。日が昇る方向を向いて神様を置くのが良いので、神棚が無い場合は東の方向に向けてお守りを置くと良いでしょう。
厄除けのお守りは複数持っていてもいい?

お守りの種類は沢山あります。厄除けだけでなく、さまざまな効果が期待できるお守りがあります。そこで、お守りを複数持っていても良いのか?と疑問に思われる方もいますが、複数持つことがダメな理由はありません。
また、他の神社のお守りを持つことで神様が喧嘩するのでは?と心配される方もいますが、それもありません。
暦のうえで「神無月」とありますよね。出雲だけ「神在月」となりますが、この時、全国から神様が出雲に集まり、会議を行います。
つまり、神様はとても協力的で人間のように妬んだり、嫉妬したり、争いなどは好みません。厄除けのお守りは複数持っていても構わないということです。寧ろ、持ち方に注意をした方が良いということです。
厄除けのお守りの処分方法・返納方法3個

厄除けのお守りを処分したいけど、処分するのに決まりはあるの?そもそも処分していいのか?返納はどこにするものか?どのようにすればいいのか?返納するのにお金はどのくらいかかるのか?
お守りを手放そうとするとき、神様が宿るお守りをどのようにすれば良いのか、間違った方法をする前に、押さえておきたい厄除けのお守りの処分方法と返納方法をまとめたので、確認しておいてくださいね。
1. 古神札納所へ返納する
ご自身のお守りを購入した神社かお寺に返納するのが一般的です。神社は神社に返納し、お寺はお寺に返納するとされていますが、貰ったお守りなどは、どこで購入されたのか不明な場合や、知っていても遠方で行くことが困難な場合は、年末年始などに、神社もお寺も「古神札納所」という一角を設けられており、そちらに返納すると良いでしょう。
もちろん、期間限定ではなく「古神札納所」を365日設けている神社やお寺があります。不明な場合は、近隣の神社かお寺に問い合わせてみると教えてくれます。
ただし、返納する際に感謝の気持ちを持ち、お守りと同等の金額を収めるか、お気持ちの代金(高額でなくても大丈夫)と一緒に返納しましょう。
2. どんど焼きで処分する
そもそも処分って聞こえが悪いように感じますよね。基本的に、神様が宿るお守りを燃やす行為は良くありません。ただし、どんど焼きは、神様に感謝を伝え返納する行為なので、どんど焼きだけは良いとされています。
この時、お守りだけでなく、お札や飾り物なども一緒に燃やします。中には、人形やぬいぐるみなどをどんど焼きで処分する人もいます。
その時、感謝の気持ちを持ち返納しましょう。そして、燃やすのに手間もかかるので、お気持ちと言われる金額やお守りと同金額くらいの代金をお支払いするのがマナーだと思ってください。
3. 神社へ郵送する
遠方の神社などで購入したお守りを返納する際、遠くて行けないなどの理由で、購入した神社に返納することが難しい人もいるでしょう。その際、近隣の氏神様に返納することも可能ですが、気になる方は、購入した神社に問い合わせをすると、封筒に「お焚き上げ」と記載して郵送を受け付けてくれる場合もあります。受け付けてくれるかどうかは、神社の方針もあると思うので、確認をしてから行うようにしてください。
ただし、こちらの神社へ郵送する方法は、上記の2点のように、お気持ちをお支払いする機会がありません。神社やお寺でどのようにお気持ちを受け付けてくれるかを確認しておくと良いでしょう。
厄除けのお守りはプレゼントしても大丈夫?

もちろん大丈夫です。家族などの身内をはじめ、親しい友人などにもプレゼントすると良いですね。お守りを購入するお金がなかった時は、手作りのお守りをプレゼントしていたという時代もあるので、プレゼントをするのに下手に気を使わなくても大丈夫です。
お守りをプレゼントしたいと思うのは、それだけ、相手の幸福を望んでいるという気持ちのあらわれでもあります。お守りは自分で購入しないと意味がないというものではありません。
また、お守りを代理購入されることは大丈夫なのかと気にされる方もいるでしょう。そちらも、購入に行くことができない人もいますし、ダメだというもお守りの効果はないということはありません。むしろ、代理で購入してくれる人もまた、幸せを願っているという温かい気持ちからの行動です。近年では、男女別でお守りをプレゼントするのに、人気のお守りなどもあります。
まとめ
事故やトラブル、何をやってもうまくいかないなどの状況が続いたとき、ふと思うと厄年?なんてこともあるでしょう。そんな時、厄払いを意識してお守りを身に付けると、災いから身を守ることができるかもしれません。もちろん、科学的な根拠はありませんので、ご自身の気持ちが落ち着く方法のひとつとして取り入れてみるのも良いかもしれません。