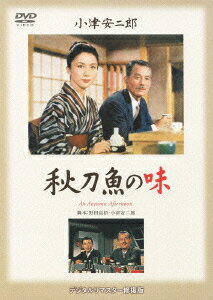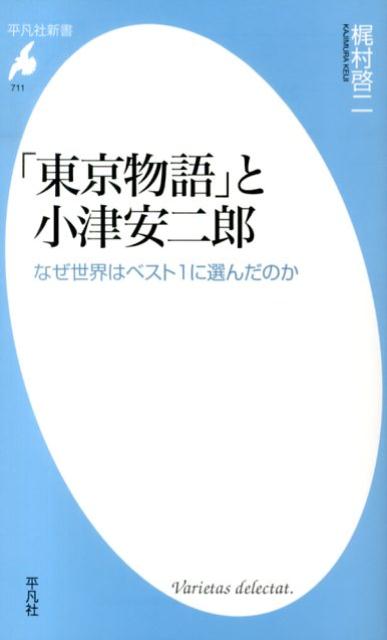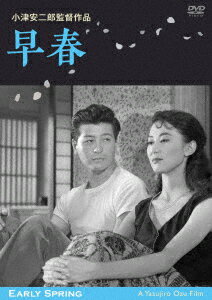『東京の女』1933,小津安二郎
ここのところUNEXTで小津の戦前サイレント作品をいくつか鑑賞している。どの作品もキャメラポジションが決まっていて、いわゆる小津調がすでに確立しているように思う。しかしよく考えてみれば、そもそも小津に限らずサイレント期において、キャメラの可動域は極めて限定的で、また画面のブレやピントのボケや逆光などに対して、それらを許容できる共通コード(映画のお約束ごと)のなかった時代だった。だから洋の東西を問わず、サイレント映画のほとんどは、全て“小津調”と言えなくもない。サイレント映画は、頻度や濃淡はあってもキャメラが固定されたままであり、演者や乗り物などが動くことで構図を流動化させている。要するに当時の映画撮影の不自由な制約が最終的に小津調を作り上げたということではないだろうか。ただし小津が極めて特異な作家として異彩を放つのはトーキー以降クレーン撮影などキャメラの可動域が飛躍的に広がったにもかかわらず頑なにキャメラをローアングルに固定させ、サイレント映画的な“小津調”を守り通し続けたことなのではないのか。ただしこれ全て私見であり、仮説です。
さて、本作について語りたい。サイレントはキャメラが固定されていると言ったばかりなのにファーストショットがいきなりぼんやりと移動し始めて度肝を抜かれる。ただセカンドショット以降は人物の歩くシーンを除けばきっちりフィックスされている。最初の動くショットの意図がよくわからない。導入部だからか?もう一つびっくりしてしまったのは劇中ルビッチの作品が挿入される映画館のシーンだ。この挿入されたルビッチが“小津調”の真逆のような華麗なキャメラワークで画面狭しと動きまくっている。あまりのことにクラクラ眩暈を覚える衝撃波。
別の作品の撮影の合間、9日間を使って製作されたらしいのですが、やっぱ、小津安二郎はタダモンじゃあないですね。もう一つ特筆すべきは、サイレント特有のゆったりしたリズムに逆らうかのように姉と弟の諍いのシークエンス。極めて短いショットを繋ぐダイアローグが緊張感のあるサスペンスを作り上げている。キャメラは固定されてはいるけれど短いショットの繋ぎ編集でその制約を解消させるラディカルさ。サイレント期の小津安二郎、過激です。凄すぎる!
作品データ
※以下出典根拠映画ドットコム
原作/エルンスト・シュワルツ
監督/小津安二郎
脚色/野田高梧
撮影/茂原英雄
キャスト/岡田嘉子、江川宇礼雄、田中絹代、奈良真養
製作年/1933年
製作国/日本
配給/松竹
上映時間/47分