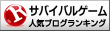公式サイト![]()
“2012年シリアで殉職した隻眼の戦争ジャーナリスト、メリー・コルビン。女性でありながら誰よりもタフに、戦地を駆け回り真実を世界に伝えた彼女の姿とは。一人の女性の生きざまと戦地の凄惨さに圧倒される衝撃の実話。”
(アマゾンの本作解説より転載)
アマゾンプライムビデオで観られるようになった![]() のを機に再見。
のを機に再見。
一年二か月ぶりに再見しましたが、
再見するまでもなく結論(けつろん)。
「お客さんっ!![]() それ違いますからっ!!」
それ違いますからっ!!」
「それ結論ケツに![]() がついたローンですからっ!!!」(ノ∀`)アチャー
がついたローンですからっ!!!」(ノ∀`)アチャー
(デビットカード普及委員会より![]() )
)
ケツローン結論。
「観ろ![]() 」
」
それ観ろミロです。(ノ∀`)アチャー
(骨🦴は一生の友🤝 🦴大事。)
「ミロ観ろ![]() 」
」
(当記事投稿日現在、プライム会員なら絶賛無料視聴可![]() )
)
(以下、ネタバレあり![]() )
)
「ラッカは静かに虐殺されている」![]()
で高い評価![]() を受けたマシュー・ハイネマン監督が
を受けたマシュー・ハイネマン監督が![]()
管理人がアウトローで![]()
その存在を知りチェックを入れ出したロザムンド・パイクを![]()
主演に迎え、実在の戦場記者メリー・キャサリン・コルヴィン![]()
(2012年没)の後半生を描いた本作。
製作陣には国連平和大使の顔も持つ、あのシャーリーズ・セロンも![]()
名を連ねています。
(ノブレス・オブリージュですねぇ![]() )
)
似たようなテーマを扱った「おやすみなさいを言いたくて」![]()
の主人公レベッカはフォトグラファー![]() でしたが、
でしたが、
メリー・コルヴィンは現場を取材してハート![]() から湧き出る文章
から湧き出る文章![]() を“武器”に、
を“武器”に、
虐げられた🩸![]()
![]()
![]()
![]() 弱者の現実を世界
弱者の現実を世界![]() に訴える「文系」。
に訴える「文系」。
(映像📹・画像![]() が必要なときは現地で同伴者を募る(レジェンド記者であるメリーに憧れ、カメラマン役を買って出る🙋ジャーナリスト仲間には事欠かない様子))
が必要なときは現地で同伴者を募る(レジェンド記者であるメリーに憧れ、カメラマン役を買って出る🙋ジャーナリスト仲間には事欠かない様子))
同じく文章![]() メイン/写真
メイン/写真![]() サブで活動する管理人も、メリーにズッキュン
サブで活動する管理人も、メリーにズッキュン![]()
視聴開始後すぐ、アサド軍の砲撃で廃墟となったシリアのホムス県が俯瞰視点で映し出されます。
一軒のビルから始まって、街全体、観渡す限り・・・と視点の高度は上昇していく。
これが人のやったこと![]() その愚かさに暗澹とされられます。
その愚かさに暗澹とされられます。
事前知識が多少あって勘のいい![]() 方なら、
方なら、
この視点は砲撃で落命し“昇天”するメリーのものだとすぐ気付く![]() でしょう。
でしょう。
(この時点で気付かなくてもラストで気付く![]() )
)
管理人はすぐ気づいた![]() か
か![]() あなたの想像にまかす
あなたの想像にまかす![]()
落命の11年前、スリランカ政府に立ち向かうタミル・イーラム解放のトラ(劇中では国連援助物資の搬入を政府が妨害と主張)の取材で、メリーは政府軍の砲撃により左目を失明します。
人前では勤めて陽気に![]() 振る舞うメリーですが、周りに誰も居なくなった夜
振る舞うメリーですが、周りに誰も居なくなった夜![]() は、
は、
目(というより、女としての美貌)を失った顔を鏡![]() に映し、一人涙する
に映し、一人涙する![]()
元兵士で作家のパートナーとの間にも溝ができる。
高名を馳せることになった度重なる危険な取材でPTSDも発症し![]()
日常生活でも悪夢と幻覚に悩まされ![]()
“頭![]() の中の声”を止めるため
の中の声”を止めるため![]() に溺れ
に溺れ![]()
(恐らくは飲み過ぎ![]()
![]()
![]() と吸い過ぎ
と吸い過ぎ![]()
![]()
![]() に拠る歯茎の炎症とストレスで)🦷🩸も抜ける
に拠る歯茎の炎症とストレスで)🦷🩸も抜ける![]()
それでもなお、大嫌いだという戦場に足を運び続け![]()
虐げられた🩸![]()
![]()
![]()
![]() 弱者の現実を世界
弱者の現実を世界![]() に訴え続けるメリー
に訴え続けるメリー![]()
未だ人知の及ばないマクロ視点・グランドデザインの観点から読み解けば![]()
メリーがスリランカの戦場で片目(の機能)を失ったのは、劇中でも描かれて![]() いるように、
いるように、
現場を「見て伝えなければならない![]() 」。でも「見たくない
」。でも「見たくない![]() 」。
」。
彼女のそのアンビバレントな想いが、量子フィールドに乗り顕現(現実化)したのかもしれません。しらんけど。
メリーが落命する2012年シリアの取材に、彼女は失明後のアイコンであった海賊![]() 風の黒アイパッチを外し、「両目」で臨みます。
風の黒アイパッチを外し、「両目」で臨みます。
これは同取材中に自身が独白しているように、
「自分にはこの道しかない(見る![]() しかない)」
しかない)」
と腹を括ったことのメタファーだと管理人は解釈しています。
アサド軍の砲撃でメリーが落命するシーンは、一緒に行動していたジャーナリスト仲間やカメラマンとの間に、今わの際の感動的な言葉も何ひとつ交わされることなく、
じつにいきなり、あっさりと描写![]() される。
される。
現実もこんなものか、もっと酷いでしょう( つω;`)ウッ
『戦場ではね、誰にも等しく弾が飛んでくるんだよ。
日頃、どんなに善い心がけをしていようとも、全く関係なくね。』
(池田武邦:建築家、実業家】
誰かがやらねばならないその苦難に満ちた仕事を、
運命に“割り振られた(才能![]() や情熱
や情熱![]() を持った)”者は、決して多くはない。
を持った)”者は、決して多くはない。
類まれなる、人の心![]() を動かす文才
を動かす文才![]() と情熱
と情熱![]() を併せ持った“担当者”である、メリー・コルヴィンの「遺志」を受け継ぎ世に送り出された本作。
を併せ持った“担当者”である、メリー・コルヴィンの「遺志」を受け継ぎ世に送り出された本作。
(本当は劇場で観たかったんですが、管理人の住む地域では上映されなかった![]() )
)
これ以上は語りません🔇
「観ろ![]() 」
」
(当記事投稿日現在、プライム会員なら絶賛無料視聴可![]() )
)
いたくこの映画![]() (というかメリー・コルヴィンの生き様)に勇気づけられた管理人。
(というかメリー・コルヴィンの生き様)に勇気づけられた管理人。
(スピンオフ記事“それ、どうでもいい(わけない)”を作成してしまうほど)
この映画![]() に出会えたことに心から感謝
に出会えたことに心から感謝![]()
百年先とは言わないまでも、いつか![]() 人の幼い
人の幼い![]() 意識がもっと進化し、、
意識がもっと進化し、、
戦争や紛争という行為を辞められる
(戦争や紛争以上に合理的で実効的な非暴力![]()
![]() 手段を創造する)
手段を創造する)
日が来ることへの管理人なりの祈り![]() として、ここに小さな種(レビュー)をひとつぶ蒔きます。
として、ここに小さな種(レビュー)をひとつぶ蒔きます。
(種が芽吹き🌱生い茂る🌳栄誉![]() を、あなたの
を、あなたの![]() に。)
に。)
↓↓↓