本日の紹介はこちらです。
↓↓↓
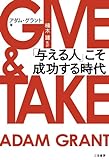
|
三笠書房
発売日 : 2014-01-10
|
【出会い】
帯広図書館で出会いました。
【本書紹介のねらい】
~本書抜粋より~
本書は単に「人間関係をよくしましょう」という話をしているのではない、ギバーになるということは、「仕事とは、いったい何のためにするのか」ということを、突きつめるということだ。
本書の目的は、ホーニックのようなギバーの成功がいかに過小評価されているか、それを知ってもらうことである、「与えること」が一般に考えられているよりも、どれほど素晴らしいものになりうるか、驚くべき研究結果とエピソードを紹介していきたい。
~Amazonより~
全米トップ・ビジネススクール「ウォートン校」の史上最年少終身教授でもあり、
気鋭の組織心理学者が教えるビジネスの成功の秘訣。
「ギバー(人に惜しみなく与える人)」
「テイカー(真っ先に自分の利益を優先させる人)」
「マッチャー(損得のバランスを考える人)」
もっとも成功するのは誰だろう。
他人に優しくしていたら、厳しい競争を勝ち抜けない?――それは大きな誤解だ。
これからは、他者志向の思いやりの発想とコミュニケーションが、あなたの仕事に大きな成功をもたらす。
リーダーシップ、営業、交渉、事業の立ち上げ、昇進まで……ありとあらゆるシーンで
この考え方が役に立つだろう。
一橋大学大学院教授・楠木建(『ストーリーとしての競争戦略』『経営センスの論理』)の
監訳と解説で、日本初デビュー!
「世の“凡百のビジネス書”とは一線を画す一冊だ!」
経営者のあなたへ。これから成功したい! と考えているあなたへ。
【響いた抜粋と学び】
著者のアダム・グラントさんはペンシルベニア大学ウォートン校教授。組織心理学者。同大学史上最年少の終身教授。『フォーチュン』誌の「世界でもっとも優秀な40歳以下の教授40人」、『ビジネスウィーク』誌の「Favorite Professors」に選ばれるなど、受賞歴多数。「グーグル」「IBM」「ゴールドマンサックス」などの一流企業や組織で、コンサルティングおよび講演活動も精力的に行ないます(執筆当時)。
この方、僕と同い年みたいです。分析力半端ないですよ。読み応え十分の書籍で、久々に付箋が19枚でした。
※ いつもは10枚前後なんです。
僕は元々バスケットが好きでNBAもよく見ていました。本書の事例の中でNBAのドラフトが挙げられていたので非常に興味深かったです。
「速効性」や「確実性」を求めている人は、ギバーにはなれない、「与える人が成功する」というロジックは、現象として起きるまでに非常に時間がかかる。
大きな成功を収める人びとには三つの共通点がある、それは「やる気」「能力」「チャンス」だ、成功とは、勤勉で、才能があり、かつ幸運な人びとによって達成されるものである。
仕事においては、ギバーかテイカーかにはっきりと分かれることはほとんどなく、たいていの人が第三のタイプになる、それが、与えることと受けとることのバランスをとろうとする「マッチャー」だ。
どの職種をとっても、ギバーはとても思いやりがあり、人を疑わず、相手の利益のためなら自分の利益を犠牲にすることもいとわないようだ、ほかにも、ギバーはテイカーに比べて収入が平均14%低く、犯罪の被害者になるリスクは2倍、人への影響力も22%劣ることがわかっている。
本書の中で、ギバー、テイカー、マッチャーの3タイプが出ます。ギバーは与える人。テイカーはギブをすることもあるが、基本は自分中心で自分の利益を得る手段としてのみ、相手にギブをします。マッチャーというのが与えることと受けとることのバランスを取るタイプです。マッチャーは常に”公平”という観点にもとづいて行動します。
結論から言うと、ギバーが一番いいんだけど、最後の抜粋にあるように犯罪の被害者になるリスクが高かったり、影響力が低かったり、など完璧ではない、ということですね。
「誰よりも勤勉で度胸もある。厳しい意見をいうだけじゃなく、協力も惜しまない。それにレスポンスが驚くほど早い。これは投資家にもっとも必要な脂質の一つだね」。
人を思いやることが、成功と相容れない場合もあるだろう、一方が得をすれば他方が損をするというゼロサムゲームや、どちらか一方が勝つか負けるかという関係では、与えることが利益をもたらすことはまずない。
職場は食うか食われるかの場所だと考える人は、テイカーになる傾向が強い、順位づけを義務づけている企業や、同じ顧客を奪い合っている同業者たち、あるいは相対評価で成績を決め、必要以上の成果を求める学校かどうかで、ギバーよりもテイカーになる人が多いかどうかがすぐにわかる。
「自分にまったく利益をもたらさない人間をどうあつかうかで、その人がどんな人間かがはっきりわかる」(サミュエル・ジョンソン)。
このあたりの抜粋はギバーやテイカーに限定したものではありません。一つ目の抜粋はまさに”デキる”経営者ですね。4つめの抜粋についてはなるほど! と思いました。
リフキンの真の目的は「どのようにネットワークをつくり、そしてネットワークから得をするのは誰か」ということに関して、人びとが抱いている考えを根っこから変えることなのだ。ギバーは頼り合うことが弱さだとは考えない、それよりも、頼り合うことは強さの源であり、多くの人びとのスキルをより大きな利益のために活用する手段だと考えている。
非常に才能のある人は他人に嫉妬されやすく、嫌われたり、うらまれたり、仲間はずれにされたり、陰で中傷されたりすることを発見した、ただし、これがギバーであれば、もはや攻撃されることはない、それよりむしろ、ギバーはグループに貢献するので感謝される。
うまくいかないときは自分が責任を負い、うまくいっているときは、すぐにほかの人を褒めるのである。
訓練兵がミスをしても、小隊長はそれを能力が低いせいだとは思わず、学びのいい機会だととらえた、小隊長の協力的な態度によって、訓練兵は自信と能力を高め、より高い功績を達成できるようになったのだ。
2つめの抜粋はよくありがちですね。ギバーは周囲に自分の才能を分け与えるため反発が少ないようですね。
3つめの抜粋は短いながら響きます。ついついうまくいっているときは自分のおかげ、うまくいかないときは他人のせいにしてしまいがちですね。
今日では、関心の度合いのほうが、才能をいかに発揮させるかより「優先される」ことを示す、説得力のある証拠がある、人が才能を伸ばすきっかけになるのは、「やる気」であることがわかったのだ。
ギバーは才能を見抜き、それを伸ばすことに長けているだけでなく、予想が外れたときでも、自分の立場にこだわることなく、まえに進んでいけるのだ。
強気のコミュニケーションはその場かぎりの面接では効果的だが、チームワークやサービス関係では、チームのメンバーの尊敬や賞賛を失う要因となる。
成功するギバーの多くが、人はみな善人だという信念から出発するが、同時に、周囲の状況を注意深く観察して潜在的なテイカーを割り出す。
関心の度合いですね。子供の成長も確か関係していて両親が子供に関心を持っているほうが才能を発揮しやすいというのを読んだことがありますね。
ギバーは人間観察が上手な感じがしますね。相手をよく見て、自分をよく知ることが大切なのかな。
こちらは僕のメルマガです。
↓↓↓
「介護業界のウラのうら」
ブログでは書きづらかった内容を配信します。
介護業界の秘密、認定調査の裏ワザ、資格取得についてなど、現場の職員だから書けることをお伝えします。気軽にご登録してくださいませ。登録した日を0日として一日目、三日目、五日目と奇数日に配信されますよ!
『介護業界ウラのうら』
登録ページはこちらです。
↓↓↓
http://cttform.jp/Qm/fr/kai5/kaigo5
【編集後記】
本日は担当者会議1件です。あとは書類整理です。
昨日は次男と動物園に行く予定でしたが、午前中近所の友達の家に次男一人で遊びに行った結果昼食もそこで食べてきて帰ってきたのが17時半! 大人になったなぁ……。僕は家にこもってました。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
コメントは自由制です。一見さんも読者も大歓迎です。
返信は24時間以内にいたします。
※心無い非難・誹謗・中傷等は削除させていただきます。
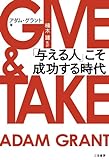
|
三笠書房
発売日 : 2014-01-10
|