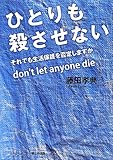昼の紹介はこちらです。
↓↓↓
【出会い】
幕別町図書館札内分館で出会いました。
【本書紹介のねらい】
~本書抜粋より~
もうこれ以上、貧困によって人を殺させないために、どうすればいいのか、ほんとうの意味で、貧困から自立できるようにするために、どのような考え方が、しくみが必要なのか、わたしが10年間の支援のなかで考え、取り組んできたことを、この本をつうじて、少しでも多くの人にお伝えできればと思います。
生活保護受給者と関わりがある社会福祉士、介護支援専門員のあなた、生活保護課、福祉事務所などで働くあなたに、生活保護についてより深く考察していただければ、と思います。
【気になった抜粋】
厚労省の調査によると、2010年の生活保護利用世帯数は195万2063でした、生活保護費総額は3兆3296億円です、このうち、不正受給件数はどれくらいでしょう、2万5355件です、これは全体の1,8%となります、金額にして、128億7425万円であり、全体の0,38%です。
路上生活をしている方に「なぜ生活保護が嫌なのですか」と聞くと、「施設に入ったことがあるけれど生活保護はもうこりごりだ」と口にされます、多くの方が無料定額宿泊所で自立を妨げられ、そこに滞留してしまったり、そこから抜け出して保護や支援を受けることを毛嫌いする。
生活保護の福祉事務所の査察指導員・ケースワーカーは社会福祉主事でなければならないと規定されているにもかかわらず、実際にはこの資格の保有率は75%程度です、4分の1ほどが無資格で社会福祉法に違反しながら、支援をしているということになります。
なぜ生活保護を受けても生きることができないのだろう、そこまで支援して、わたしたちとの関係もある程度構築できていたのに、結局、その人は心を許してくれなかったのか、心を許してくれていたとしても、生きる意欲を見出したり、この先の生活に展望を感じることができなかったのではないか、そういうことまで見据えて支援を組み立てなおさないと、やっぱりダメなんです。
ようやく生活保護が受給出来ても、そのあとはお金が有効に使えないので、支援がない場合、家賃滞納をしてアパートを追い出されてしまうでしょう。
要支援者たちが就労を継続することは、まず不可能です、そして、協調しておかなければならないことは、「まずは働け」、「何でもいいから働け」は禁句だということです、ある程度の仕事上の満足感ややりがいがなければ、離職してしまうリスクがあります。
日本の生活保護費がGDPに占める比率は、先進諸国でも極端な低さです、しかし、生活保護制度に関する予算を取ることに、そもそも多くの人が納得しない状況があります、社会保障費や社会福祉費は、今も低いにもかかわらず、まだ下げろという論調です、また、「自力で生きていけない人たちを国や政府は助けるべきとは思わない」と回答する人が38%いるという状況です。
奨学金についても「もらえる」お金はほとんどなく、大抵は未来の借金となります、利子も低いものではありません、教育を受けるのは権利であるはずなのに、なぜ働かなくてはいけなかったり、債務を抱えなければいけないのでしょうか、そもそも、学費は高すぎるのではないでしょうか、こうした矛盾を身近なところで感じられるはずです。
【響いた抜粋と学び】
わたしも、もともとは頑張ればなんとかなるはず、と考えていました、努力をすれば報われるという高度経済成長を経験してきた両親に育てられたわたしも、以前はそうした昔ながらの会社人間の考え方をもってきました、ちゃんと企業に入って、きつい仕事も我慢して張りついて、企業のために一生懸命し働いてさえすれば、たとえうつになろうが、多少のつまずきがあっても、その見返りとして自分の生活も、社会もよくなっていくんだ、というある種の幻想です。
努力すれば何とかなるという非現実的な言葉は、貧困に対する認識があまりに甘いために出てくるのだと思います、努力するための土台が崩れていることへの想像力、共感力のないケースワーカーが現場には多く見られるのです、そういう能力を鍛える努力が、ケースワーカーに必要なのではないかと思います。
戦後の日本復興において、もし、努力してもどうにもならない、という考えが広まっていたら現在の日本はどうだっただろうか? きっと今のような経済大国であり、衣食住が完備された豊かな国は実現されなかったでしょう。
国民全員ではないにしろ、大多数の人が日本復興を信じて努力してくれたことで豊かさが実現しました。
現代はどうでしょうか? 努力せずとも衣食住が完備され、治安の良い、豊かな国で生活できるのです。昔のように企業戦士となって働くことが幸せなのか? という疑問が湧いてくるのも当然です。
本書にもありましたが、努力の仕方がわからなかったり、なぜやらなきゃいけないのか、という状態の方が保護を受けていたとして、相談相手は役場で働くための受験戦争を勝ち抜いたエリートたち。努力できないこと、挫折することを共感してもらえない、という状況のようです。う~む。
路上に戻ることをわたしたちは「再路上化」と呼ぶのですが、こうしたことはあちこちの支援の現場で繰り返されています、路上にしか居場所がないという人も実際にはいます、だから、路上での生活を肯定的にとらえることが、まったく駄目だとは思いません、でも、路上しかその人の居場所がない状態が続くのはよくないだろうと考えています。
ホームレスの人たちの存在を認めてもらいたい、それは、どんな人間だって尊いんだという、それだけのことなのですが、その視点がいまの社会には欠けています。
もともと人類は狩猟民族であり、食べ物を求めて移住しながら生活していたはずです。そこに農耕文化が出てきて、移住せずとも暮らしていける、定住型が定着したわけです。本来の人間は同じ場所にい続けるのではなく、移住していくDNAが組み込まれているのではないか、と解釈しています。
そこにきて、さらに日本では家を持つことが当然、という文化が確立しています。
世界に目をやれば、きっといまだに遊牧民族がいるはずです。
日本に置いては遊牧民は認められない、ということでしょうか。
「がんの治療費を払い、彼女のこれからの生活の面倒も見るなんて、そんなことはできない」、妹さんはこれまで精神的には支えとなってくれていたのに、多額の金銭的な支えの話を切り出したことで、その絆は断たれてしまいました。
「なぜ家族が扶養できないの」という質問は、あらゆるところで繰り返されます、しかし、こうした質問をなさる方の多くは、おそらく恵まれた家族関係にある人でしょう、わたしたちのところに相談に来られる方は、家族から虐待を受けていたり、金銭的な搾取を受けています、家族関係の中でお互いを扶養するような温かい関係性を築くのが、とても難しい状態にあります。
子育てをしていて、子どもを養うのだって簡単なことではない、そんな状況に置いて、年を重ねた家族を扶養できるのか? と聴かれたら多くの方はできない、と答えるでしょう。経済面でそこまで余裕を持って生活している人は限られているでしょう。
また、生活保護を受ける、と相談に来る方は、扶養してもらえるのだったら、来ていないでしょう。高齢者介護の現場でも生活保護を受けていながら、人間関係が良好、という方はなかなかいないと感じます。
医療扶助を悪用して過度に診断したり、医薬品を購入させることで診療報酬がつき、医師にも利益があります、医師が過度な診断をするのは、多くの出した医薬品が転売されることを見こしつつも、自分たちの利益になるので、むしろそれを推進していることにほかなりません。
転売までは帯広であるのかどうかはわかりませんが、パチンコ屋に近い病院に適当に受診して(医療費タダ、タクシー代も受給される)、受診後にパチンコをしている生活保護受給者がいるというのは聴いたことがあります。
もしこれで薬の転売までしているとなると……。
ギャンブルやアルコールに生活保護費を使ってしまうことも「不正受給」であるかのように言われています、まず理解すべき重要な点は、こうした使途は不適切であったとしても、違法ではないということです、生活保護費の使途は自由ですから、ギャンブルに使おうが、アルコールに使おうが、法的には何ら問題はありません。
アルコールやギャンブルは、日常生活の苦悩など対処しきれない現実を一時でも忘れさせる手っ取り早いストレス解消方法です、社会福祉では、そのような相談者の状況は、ストレス対処能力を習得できていない状態だと考えます。
ギャンブル、ゲーム、アルコール、タバコ、スナック菓子、ジュース、砂糖、これらはすべて中毒性があります。
病気にならない女性は「カタカナ食」を食べない──人生が好転し始める「1食100円」の美的メンテナンス48 /幕内秀夫
こちらでも紹介されています。
人間は本来弱いです。ちょっとしたことでも辛いな、と思えば現実逃避したくなるものです。そこで立ち向かえる人はおそらく2割程度でしょう。多くの人は困難に立ち向かえず、タバコやお酒、ギャンブル、ゲーム、お菓子、ジュース、砂糖などで一時的にストレスを解消してりうだけです。これらはすべて即効性があり、成果を得やすいです。
相談者に限らず、相談に来ていない多くの人がこれらを活用して生きていると感じています。
現代の日本において、誰であれ人の死は、もう少し尊いものとして迎えられると思っていたんです、わたしの祖母は、家族みんなに看取られて、家の中で亡くなりました、人の死は、家族みんなから感謝されて、「よくがんばったね」と声をかけられて、そうやって迎えるものだと思っていたんです。
「餓死や孤立死というのは、自分でそういう死を選んでいるのではないか」「本人が自由に死ぬ権利もあるんじゃないか」と平気で口にされる方がいます、本当は貧困状態だったり、孤立していたのではないか、そんな可能性を想像する力が乏しすぎます、結局、亡くなる人たちに対しても、「自己責任」のような、「本人が選んでそうしている」という見方がされています、誰にもつながらなくていいかのようにしてしまっている社会の側に問題があると思います。
その人が死んだ後も、生前の思い出を話せる人がいて、手を合わせる人が一人でも二人でもいて、その人にまつわる品が棺桶に入る、これが、「健康で文化的な最低限度の死」だと思います。
生活保護の受給者が、生活保護から抜け出す一番の理由をみなさんはご存知ですか、統計を調べると、「廃止事由」が分かります、そのほとんどは「死亡」なんです。
生活保護と死についてです。豊かな日本おいて「死」についても一人、誰にも知られず死んでいた、ミイラ化している、というのは標準ではないと僕も思います。
自殺についても同じですが、一人一人が支えあっていければ、そんな社会ができていれば、餓死や孤立死、自殺は減っていくのではないか、と思っています。
その第一歩は、僕たち専門職が現状を知ることではないでしょうか?
ここまでお読みいただきありがとうございます。
コメントは自由制です。一見さんも読者も大歓迎です。
返信は24時間以内にいたします。
※心無い非難・誹謗・中傷等は削除させていただきます。
帯広市内や近郊にお住まいの方で本書の購入を検討した方はぜひ「ザ・本屋さん」での購入をオススメします。
書店での書籍購入は本をもらうだけではなく帯広の書店存続……つまり「帯広市とその近郊、十勝」の文化・教養を高めることにつながります。
「ザ・本屋さん」ではご自宅や勤務先へ本を配達してくれます。
配達地域……帯広市内(大正、川西除く)、札内地区(全域)、音更地区(大通・木野・希望が丘・共栄台・桜が丘・新通・鈴蘭・住吉台・柏寿代・東通宝来・北明台・北陽台・緑が丘・元町・柳町・雄飛が丘・緑陽台)
雑誌、書籍、週刊誌の定期配達は無料で行います。
非定期配達は1000円以上で無料です。
配達区以外の場合は、郵パックで対応してます。
詳細はホームページでご確認くださいませ。
ザ本屋さんウェブサイト