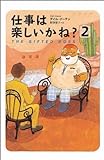おはようございます。岡本大輔です。
本日の紹介はこちらです。
↓↓↓
【出会い】
前作、「仕事は楽しいかね?/デイル・ドーテン
」を読んで続編も読みたくなったので帯広図書館で借りました。
【本書のテーマ】
上司のあり方、部下との関わり方。
【岡本大輔の視点】
自分のやりたいことは何?
【気になった抜粋】
ほんものの上司・・・”その人と一緒にいるときの自分がいちばん好きだ”。
「お役所的なところで働いているからといって、何も私までお役所的な考え方をすることはないんですね。」。
並みの上司・・・チームプレーヤーを探す、優れた上司・・・同志を探す。
きわめて優秀な部下は、決まって起業家タイプだ、新しいプロジェクトを次から次へと考え出さなければ、彼らの関心をつなぎとめておくことはできない。
【響いた抜粋と学び】
したいことをしてこそ人は成功する、それ以外に成功する道はない(マルコム・フォーブス)。
仕事の選び方の基本中の基本がここです。あなたのしたいことをしてください。「給料が高いから」、「休みが多いから」、これからは仕事を選ぶ条件の一つです。参考にはなるかもしれませんが、何年も続ける仕事を給料や休みだけで選ぶと、仕事をしている時間がただの苦痛になりえます。
あなたがやりたいことは何ですか?
並みの上司・・・他社に負けない給料や待遇を示して、「うちで働かないか」と誘いをかける、優れた上司・・・「きみ自身の才能を開花させるチャンスのある、素晴らしい環境で働かないか」と誘いをかける、自分の部下は皆がほしがる人材だとわかっているので、彼らを惹きつけておける職場をつくろうとする。
介護関係の仕事は給料や待遇が悪くて人材定着率が低いと聴きます。本書の話からすると、「給料が低いから」、「仕事がきついから」というのは本当の理由ではないと僕は感じました。
他の業界と比べる時に給料や待遇を示す・・・並みの上司、並みの社員しかいないがために人材が定着しないと考えられませんか?
優れた上司がいて、介護の仕事の素晴らしさ、介護の仕事を通して得られる経験、人生を伝えられる人材がいないことが介護業界の停滞を招いているのではないか?
と僕は感じました。
「辞めた人はまず非難され、それから忘れてしまうんだ。会社を去った人も、あとに残っている人たちのことなんか思い出すこともない。だけど、本当に優れた上司は本当に優れた部下のことを決して忘れないし、連絡も絶やさないものなんだ。」
辞めた当人としては自分はデキる人間だと勘違いしているので(はい、僕です。)、この部分を読んで現実を知りました。
辞めた社員は非難の対象になり、忘れられてしまう。以前の職場で辞めた後も素晴らしい社員だったと言われていた人は10人いたら1人くらいだったと振り返りました。
「勘違いする」だけでなく、「勘違い」が現実になるくらいの努力が必要だと感じました。
【編集後記】
本日は経営者モーニングセミナーに出席予定でしたが、我が家の長男が熱を出して寝込んでいるため、欠席します。
出勤前に長男の様子を見て、朝ごはんを用意してから出勤したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
コメントは自由制です。一見さんも読者も大歓迎です。
返信は24時間以内にいたします。
※心無い非難・誹謗・中傷等は削除させていただきます。