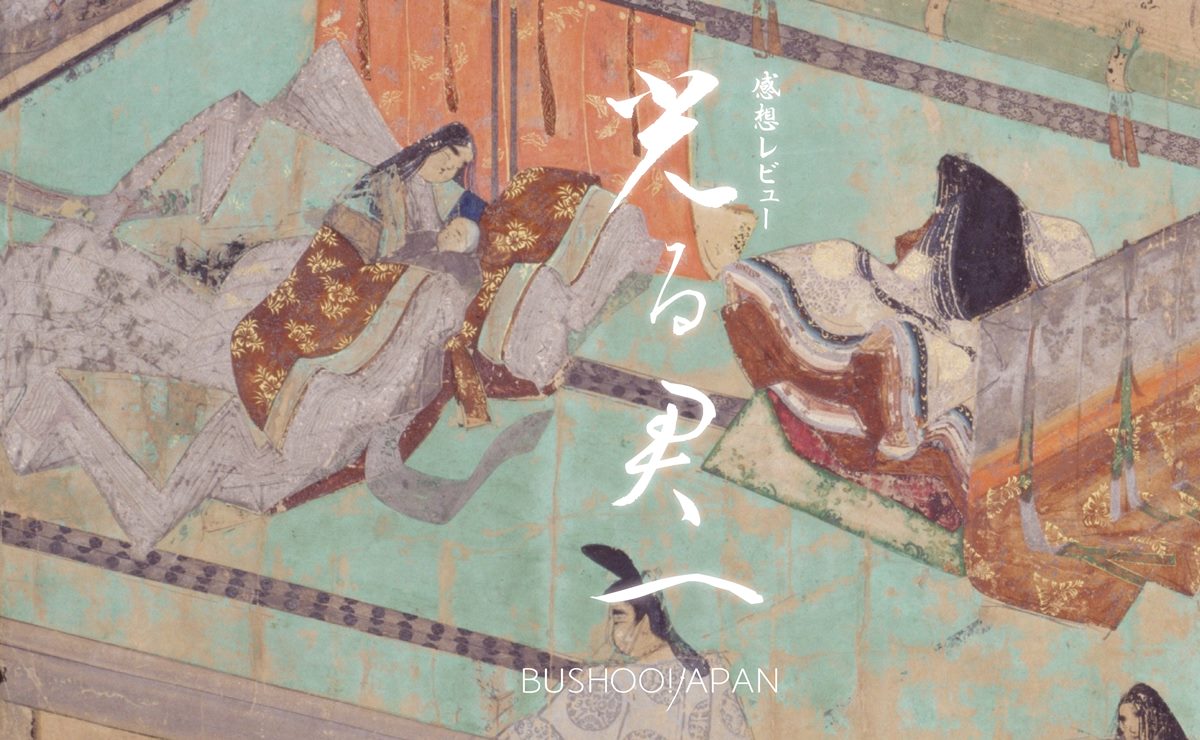後継者は
兼家が指名した
道隆になりました
そりゃそうだと
ほとんどの人は
思っていたでしょう
行成も
なるようになっただけ
と、冷静でした
当然自分が
後継者に
指名されると
どういうわけだか
勘違いしていた
道兼は
道隆が
後継者だと知り
逆上し、
兼家を罵倒し、
出仕も
しなくなりました
父が若い頃
舐めた辛酸を
思い出して
臥薪嘗胆するとか
そういう方向には
行かないわけで
ちょっと
我慢する
ができないのは
後々の伊周も
そうですが
短慮が過ぎると
思うのです
人間は
窮地に陥った時にこそ
その真価が問われる
まあ
あんな風だと
人心も離れる
というもの
公任や繁子が
見限るのも
当たり前といえば
当たり前
繁子が選んだ
新しい男が
兼家家司だった
平惟仲らしいので
いや〜〜〜
天皇の乳母って
利用価値
あるんだなぁ
って
妙なことに
感心しました
このあと
繁子は
道長に接近
叔母として
終生大切に
扱われたそうな
娘の尊子も
道兼の死後
一条天皇に入内
させた
といいますから
繁子は
政治家としても
手腕を発揮したと
言ってもいいでしょう
さすが
師輔の娘
兼家の妹
九条流の姫君は
詮子にしても
繁子にしても
したたかです
藤原兼家が亡くなった頃(990年頃)の登場人物の年齢(満年齢)
— RekiShock(レキショック)@日本史情報発信中 (@Reki_Shock_) April 7, 2024
まひろ(紫式部)20歳前後
藤原道長 24歳
倫子 26歳
定子 13歳
ききょう(清少納言) 24歳前後
藤原伊周 16歳
明子 25歳
藤原行成 18歳
藤原実資 33歳
藤原道兼 29歳
藤原道隆 37歳
詮子 28歳
藤原兼家 61歳 #光る君へ pic.twitter.com/TfUDuopiYG
伊周って
行成と二つしか
違わないのかぁ
行成の
あの達観した感じ
すごすぎるわぁ
早くに
父親を亡くした
行成は
母方の祖父である
源保光に
政治家としての
ノウハウを
叩き込まれて
育ったので
道兼や伊周とは
入っている筋金が
違っています
【光る君へ】第14回「星落ちてなお」回想 兼家と寧子「輝かしき日々」を描いた『蜻蛉日記』 『拾遺和歌集』に花山院の存在 ききょうの「信条告白」にしびれる
↑
兼家と寧子の
青春時代に
光が当たりましたね
兼家は寧子のことも
大切に思っていたのだと
そう思いたいですね
蜻蛉夫人も
立派に妻だったので
妾ではない
ということです
でなければ
二人の間に生まれた
息子の名前に
「道」の字を
あてたりしませんよ
道長の兄弟は
「道」という字が
通字に
なっています
通字は
「つうじ」
または
「とおりじ」
と訓みます
兄弟の結束を
固めるために
用いられる方法です
道綱だって
父親に
愛されていたんですよ
きっと
寧子さま
ほんとうに
よかったですね
道綱は、よく
辛抱したと思います
さすが
寧子さまに育てられた
だけのことはあります
実資には、日記で
「道綱は字も書けない」
やら
言われていましたが
道綱は道綱なりに
精一杯頑張ります
最初から
何もかも
与えられている
幸せいっぱいな
若君とは違って
苦労した若君は
我慢して努力する
もののようです
そしてそれが
実を結ぶ日も
来るのですが
打たれ弱い
貴公子たちは
身を持ち崩すことに
なるのでした