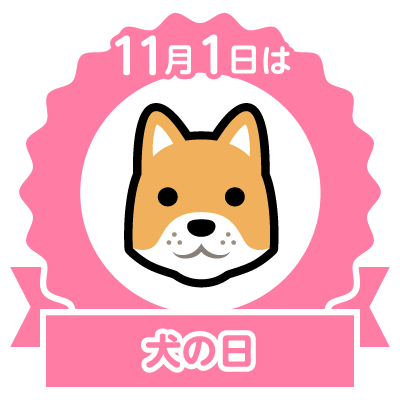かわいいは正義!わんこの写真拝ませて!
▼本日限定!ブログスタンプ
掌編小説・『犬』
冷たい雨が、コートを湿らせて、どんどん体熱を奪っていく。
自分が隠花植物にでも変化したような、限りなく陰鬱な時間がじりじりと過ぎていく。
もう二十分も一人ぼっちの寒々しい道行を強いられている。
路程は林の中に入って、風景の暗さがどんどん増していく。苔色の針葉樹林。鉛色の天蓋。
心細いが、一本道なので道には迷わない。…筈だ。
被っているフードは赤色で、傍から見たらまるっきり「赤頭巾ちゃん」である。
が、目的地は「おばあさんのうち」ではなくて、「狼のねぐら」だった。
「狼」は比喩であり、つまり、女に飢えた若いケダモノのような男のうちに、私は向かっている。パートタイムラヴァー。コールガール。どんなケダモノが待ち構えているかは分からないが、一度足を踏み入れたら私には相手の要求を拒む権利はない。…
男は、私を犬のように扱った。
四つん這いにさせて、屈辱的な喘ぎを貪った。
私の華奢な身体は男の膂力で折れそうに撓った。
何度もオルガスムスを迎えて、私は身も心も完全に犬になり果てていた。奴隷になる喜びに翻弄され、その喜悦だけが全身に横溢していた。
「お前は犬だ」男は分厚い唇を歪めて嗤った。
そうしてそれは比喩ではなくて、気が付くと私は本当に黄色い尨毛の、綺麗な毛並みの、ゴールデンレトリバーの雌犬になっていた。犬になった全身は軽快で、尻尾を振るたびに痺れるような快感が総身を貫いた。
「ウオン」と試しに哭いてみると、それは張りがあって音楽的な、美しい大型犬の鳴き声だった。
… …
「もしかしたら、もう人間には戻れないのではないか?」危惧していたが、男の元から離れ、家路につく頃には私はまた人間の女に戻っていた。
「犬になった」というのが単なる錯覚だったかどうかは最後まで判然としなかった。
だが多分、服従することに喜びを覚えているということへの葛藤が、不思議な心理作用となって現れて、そういう錯覚を呼び起こしたのだろう…帰る道すがらに私はそう結論付けた。
だが、一方で、「その刹那には本当に私は犬そのものに変身していた」と思う方がファンタジックで本来的な発想?真実の体験?
そういう気もするのだった…
<了>