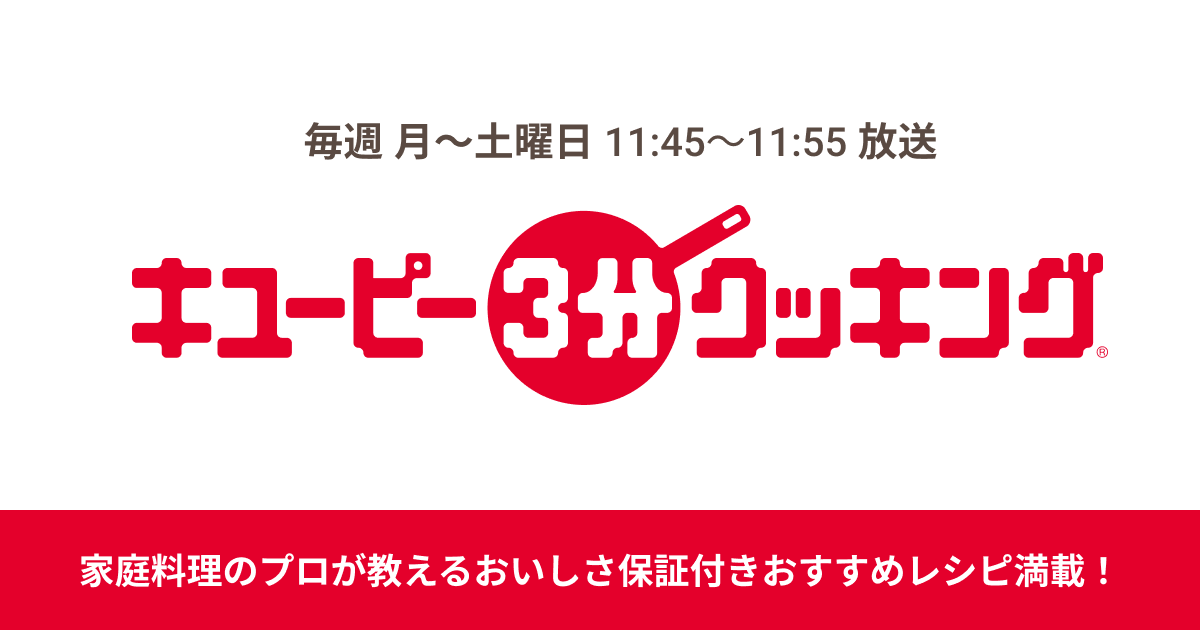6月30日には…
半年間の厄落とし、
夏越の祓え…
旧暦の6月に行われる神社の行事です。
6月の晦日である30日に行われる
「夏越の祓え」は、
12月の大晦日である31日に行われる
「年越の祓え」(としこしのはらえ)と
対になる神事です。

夏越の祓えと年越の祓えの
2つを合わせて
「大祓(おおはらえ)」と言います。
どちらも災厄を祓い清める儀式です。
自分の犯した罪や穢れ(けがれ)を
除き去ってくれる行事で、
元々は宮中行事だと言われています。
有名な京都の祇園祭や蘇民祭も、
元々は大祓のお祭りだったそうです。
茅の輪くぐりは、
12月の「年越の祓え」にも行っている
神社もあります。
新暦8月10日頃にあたりますが、
新暦6月頃に行う所も有る様ですね…
新暦6月30日は、
旧暦5月17日にあたります。
新暦&旧暦変換 リンク先…
今日は何の日 リンク先…
茅の輪くぐり1例…
茅の輪に御幣(白い紙、ごへい)が
下がってるので分かると思います。
神社によっては、
楕円形の茅の輪もあります。
大きな茅の輪(ちのわ)をくぐって
半年の厄落とし祈願します。
厄落としとは言え、
『厄年』とは関係無い様で、
喪中以外は誰が行っても良い様です。
近くの神社に
茅の輪が吊るされていたら、
茅の輪の前で一礼、
8の字を描く様に3度くぐって、
8の字を描く様に3度くぐって、
茅の輪をくぐる度に一礼して、
最後に御神殿に進み
残り半年の健康を祈ります。
残り半年の健康を祈ります。
最初に一礼、茅の輪をくぐる度に一礼…
合計4回一礼するワケです。
京都では「水無月」という、
ういろうに小豆が乗った
三角形のお菓子を食べる習慣が、
あるそうです。
茅の輪くぐり行わない神社でも、
半年間のお礼、お祓いと
祈祷に行くのも良いですよね。
ういろうに小豆が乗った
三角形のお菓子を食べる習慣が、
あるそうです。