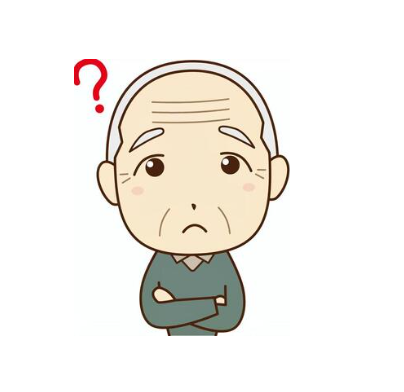前回投稿から2ヶ月経過した。
最初の投稿は昨年12月だったが以後投稿を重ねて来て、前回の5回目は期待していなかった実が付いたが熟すには間に合わないだろうという内容で、其処で一区切りとして終わった積りだった。ところがその後嬉しい誤算があったので、今回オマケの6回目投稿をする事にした。
前回までの項目番号に沿って栽培場所を記載すると、
② 農園お隣のMさんの枝で作った水耕根出しの鉢植え。1株
③ 2年目の株(黄色い実が成る種類)を剪定し露地植え。1株
④-1 農園お隣のMさんの枝で作った挿し芽の露地植え。2株
④₋2 農園お隣のMさんの枝で作った挿し芽の鉢植え。1株
夫々の経過は:
②鉢植え1株: 花が2輪咲き、実を付けた。
③露地植え1株: (前回は2輪を人工授粉した迄だったが、その後)追加で数輪花が咲いたが、全て着果せず落花した。
④₋1露地植え2株: 葉は濃い緑で勢いも旺盛だが、花が数輪咲いたものの何れも着果せず落花した。
④₋2鉢植え1株: (前回はピンポン玉くらいの実が一つ付き、追加で1輪花が咲いた処迄だったが、その後)更に1輪花が咲き、合計で3個の実が成った。その後緑色のまま落果している実を見付けた(10月5日)。
緑色で落果した実は食べられないと聞いて居たが、何となく勿体ないので試しにリンゴと一緒にポリ袋に入れて置いた。すると2日後の10月7日には赤みが差して来たので、此れはイケるかもと期待を持った。
(因みに一緒に袋に入っているのはミニトマト撤収時の緑色の実を追熟中のもの。合計60粒程が追熟して赤くなった。)
そして約3週間経過した10月25日には確り赤紫色になったので、ナイフを入れて数粒舌に乗せて味わうと、熟した甘酸っぱいパッションフルーツだった。
妻と二人で分けると僅かだが、それでもデザートは美味しいパッションフルーツヨーグルトになった。
鉢植えにぶら下っているのを含めるとアト4個楽しめそうだ。
苦節10カ月超、何度も諦めかけたパッションフルーツだったが、最後に少しだけご褒美が待っていた。
まとめ:10カ月のパッションフルーツ栽培チャレンジを通じて体験出来た事や、今後へのヒント。
1) 水耕根出しは不可能ではないが歩留まりが低く、20本中ポット苗までは行ったのが2本だが何れも定植には至らず。
2) 挿し木の方が成功確率は高く、15本中ポット苗まで行ったのが7株で、その内5株は定植まで行った(確率33%)。
3) 支柱を立て5月10日に定植しネットに絡めたが強風で多くの葉が損傷し株が弱り、ざっと1ヵ月程度のタイムロスとなった。定植後暫くは防風の囲いを高く設置する必要がありそうだ。
4) 鉢植えは挿し木1年目でも、葉の色が薄くても(所々黄緑色)実は付く。
5) 逆に露地植えでは、濃い緑の葉が元気に繁っても花が咲くのは遅くて、咲いても落果したがこの理由は良く判らない。
(教科書的には窒素過多によるツルボケの可能性も指摘されるのだが、此処の畝は枯葉・籾殻・竹炭・米糠を漉き込んだだけで、一般の肥料は入れてないので窒素過多の可能性は低い筈なんだがと、???が消えない)
6) 黄色い実を付ける種類は一般的に実が付き難いと言われるが、矢張り1年目(昨年)は鉢植えで花は咲いたが落花し、2年目は露地植えしたが同じく花が咲いただけで落花した。
7) 実が付いた時は緑色で落果しても諦めずに、リンゴと一緒にポリ袋に入れて置けば追熟して美味しく食べられた。
得られた知見を活かしつつ、次回は庭の株から枝を取って育てる事にしよう。