このたび、高山俊吉弁護士が書かれた「入門 交通行政処分への対処法」という本が現代人文社から出版され、高山弁護士からご献本いただきました。ありがとうございました。
この「交通行政処分への対処」は私も非常に興味のある分野です。
交通事故を起こすと、刑事処分(懲役、罰金など)とともに、行政処分(運転免許の取消、停止など)が行われます。この2つの手続は全く別の手続なので、それぞれ独立に進められます。
不注意で事故を起こしてしまえば、刑事処分が科されるとともに、行政処分も科されます。これはルールなので致し方ないところです。しかし、刑事処分と違い、行政処分は、これまでほとんど専門家からの援助を受けることなく、都道府県公安委員会からの処分が下されてきました。
交通事故と言っても千差万別。
例えば、車の死角から自転車が飛び込んできて衝突してしまったとか、夜中路上に酔っ払っていた人が寝ていてそれに気づかずに轢いてしまったというような事故もあります。
このような事故の場合、刑事処分については運転者に過失があると言えるかどうか、弁護人をつけて争うことが多いでしょう。中には、死亡事故でも過失があったと言えるどうか微妙だという理由で検察官が不起訴にする例もあります。
ところが、検察官が不起訴にしたケースでも、公安委員会から免許の取消処分が下されることがあるのです。
この公安委員会による免許の取消処分は、一応「意見聴取・聴聞」という手続が取られます。一応です。
公安委員会から呼び出され、各地の公安委員会にある「聴聞室」のようなところで運転手の言い分を聞きます。
この手続に、弁護士などが「補佐人」として出頭し、運転手の意見を代弁したり、「過失がない」ことを法的に整理して意見を述べたりすることができます。しかし、弁護士などの専門家が補佐人としてこの手続に出頭することはほとんど行われておらず、実際は形式上運転手の意見を聞くだけ聞いて、そのまま処分が下される例が多いのが実情です。
こうして不当に運転免許取消処分がなされた場合は、あとは裁判所で「運転免許取消処分取消訴訟」という行政訴訟を起こさなければならず、これには多大な労力と時間を要します。
不当な免許取消処分などの交通行政処分が下されないためには、この聴聞手続に専門家がきちんと関与することが重要であると私は常々思っていました。
私が刑事弁護を担当することになった交通事故事件で免許取消処分が科されそうになった場合には、私は可能な限りこの手続に補佐人として参加しています。(それでも不当に免許が取り消されてしまったケースももちろんありますが・・・)。
そして、もう一つ。
この「補佐人」制度は、決して弁護士資格を持っている人に限定されません。
ということは、例えばロースクールの学生が補佐人になることも可能です。弁護士が学生とともに補佐人となって、聴聞手続で専門家として意見を述べること、ロースクール生自身が意見を述べることも可能です。
これは、実務教育の極めて貴重な機会です。
私たちがロースクール生だった頃、クラスメートが補佐人として弁護士とともに意見を述べたことがありました。また、私が弁護士になってからもロースクール生とともに補佐人になって意見を述べたことがあります。
このような交通行政処分への対処方法、弁護活動は非常に重要ですが、これまでこのことを扱った本は私が知る限り一冊もありませんでした。
このたび、交通事故弁護の第一人者である高山俊吉弁護士の手によってこの本が出されたことはとてもすばらしいことだと思います。
ぜひ、多くの弁護士(そして、ロースクール生も)が、交通行政処分に専門家として関わり、意見を述べ、正しい処分に導くことができればと私も思います。
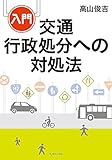 |
入門 交通行政処分への対処法
Amazon |