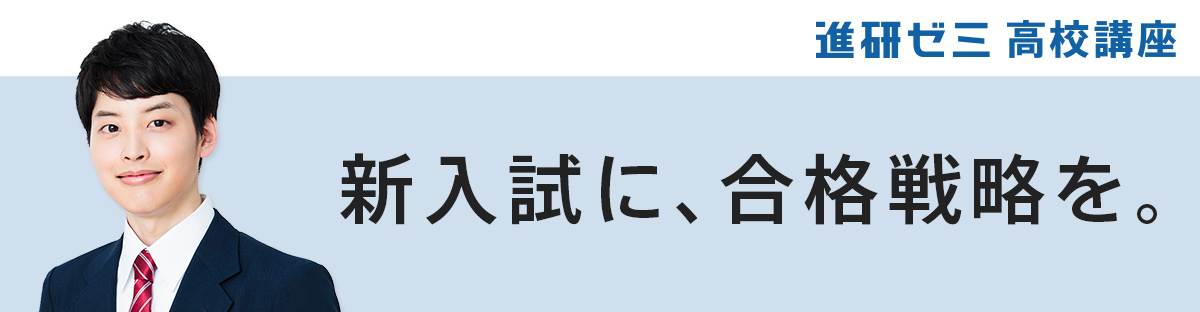【概要】
この記事では、0歳児の「おすわり」と「バランス感覚」の関係について、海外の最新研究や日本国内の研究をもとに詳しく説明していきます。おすわりができるようになると視野が広がり、赤ちゃん自身の世界も一気に変わってきますよね。けれど「いつ頃おすわりができるようになるの?」「バランス感覚ってどう育つの?」と疑問を持っている方も多いはず。この記事では、具体的な数値やデータを引用しながら、赤ちゃんのおすわりにまつわる運動発達のポイントを一緒に学んでいきましょう。
■■■おすわりとは■■■
赤ちゃんの「おすわり」は、背筋や腹筋といった体幹の筋力が発達し、自分で上半身を支えられるようになった状態を指します。寝返りや首すわりを経たあとに、いよいよ背骨を伸ばして上体を起こせるようになる時期です。最初は手を前について少し前傾姿勢になる「三角座り」のような形が多いですが、その後、背筋がさらに鍛えられてくると姿勢が安定し、手を使わずに腰を伸ばして座れるようになります。
おすわりは、赤ちゃんの視野や手足の使い方を大きく変える重要な節目のひとつです。
■■■WHOの研究が示すおすわりの時期■■■
赤ちゃんの運動発達に関して世界的に参照される研究のひとつが、世界保健機関(WHO)の「Multicentre Growth Reference Study」です。この研究では、世界各国の乳幼児を対象に、主要な運動発達(座る・立つ・歩く など)のマイルストーンが達成される平均月齢や範囲を大規模に調査しています。
この報告(下記URL参照)によると、
・「Sitting without support(支えなしで座る)」を達成する月齢は、平均(中央値)で約6.0か月前後
・早い子は4.3か月頃から座れ始め、遅めの子は8.2か月頃になってやっと安定する
という幅広い結果が示されています。研究対象が多国籍であるため、ある程度の個人差や文化的・環境的な違いも含まれていますが、ざっくりとした目安として「生後4〜8か月におすわりが始まる子が多い」と理解することができます。
出典:
WHO Multicentre Growth Reference Study Group (2006). WHO Motor Development Study: Windows of achievement for six gross motor development milestones. Acta Paediatrica, 95(S450), 86-95.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16817682
■■■CDCのマイルストーンとおすわり■■■
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は「Learn the Signs. Act Early.」というプログラムを通じて、乳幼児の発達段階ごとのチェックリストを保護者向けに提供しています。6か月頃の発達目安(下記URL参照)として、以下のようなポイントが挙げられています。
・首や上半身をしっかり支えられるようになる
・短い時間なら支えなし、あるいは軽く支えてもらうだけで座れるようになる
おすわりが安定するまでは個人差があるものの、6〜7か月頃で「一瞬でも自力で座れる」状態が見られ始める子が増えると言われています。
出典:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2022). Important Milestones: Your Baby By Six Months.
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-6mo.html
■■■日本の育児指針との比較■■■
日本国内でも、厚生労働省が発行する「乳幼児健康診査マニュアル(改訂版)」(下記URL参照)などを通じて、6〜7か月健診の際に赤ちゃんのおすわりの様子がチェックされることがあります。「そろそろおすわりが安定してきたかな?」というのが一つの目安にはなりますが、
あくまでも個人差が大きいため、多少早かったり遅かったりしても赤ちゃんのペースを尊重することが大切とされています。「まったく座る気配がない」「背中を伸ばすのが極端に苦手」など、極端なケース以外は心配しすぎなくてもいい、と多くの保健師や医師がアドバイスしています。
出典:
厚生労働省「乳幼児健康診査マニュアル(改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenko_iryo_shisaku/dl/nyuyoji_guide.pdf
■■■おすわりとバランス感覚の関係■■■
では、なぜおすわりができるようになるとバランス感覚と結びつくのでしょうか。海外の発達心理学・運動学研究では、赤ちゃんの姿勢制御や感覚統合がどのように進むかについて多角的に分析されています。
たとえば、Lobo & Galloway (2008)の研究(下記URL参照)では、生後2か月の赤ちゃんにサポートを与えながら座る練習を行うことで、運動発達が促進される可能性が示唆されました。これは「背中や腰を適度に支えられた状態で姿勢を確立すると、視覚や前庭感覚(バランス感覚)への刺激が増え、興味や自発的な動きが活性化する」というものです。
出典:
Lobo, M. A., & Galloway, J. C. (2008). Postural support for 2-month-old infants: A key element in early learning? Physical Therapy, 88(9), 1049-1059.
https://doi.org/10.2522/ptj.20070167
おすわりの姿勢が安定してくると、赤ちゃんは両手が自由に使えるようになり、さらに自分の体重バランスを調整するトレーニングを自然に行えるわけです。
■■■おすわりがもたらす実践的なメリット■■■
●視覚の広がりと探究心
寝転がっていた頃とは違って、視点が高くなるため周りの景色が広く見えます。テーブルの上や人の顔を見やすくなることで、赤ちゃんの好奇心がいっそう刺激されます。
●両手が自由になる
上体を支えられるようになると、手でおもちゃを持ち替えたり握ったり、さらに別の物を取ったりといった行動もスムーズになります。こうした体験は、後のハイハイやつかまり立ちにもつながる重要なステップと言われています。
●バランス感覚のトレーニング
おすわりをしているとき、赤ちゃんはちょっと体が揺れたら手をついて支えたり、お尻でバランスを取ろうとしたりしながら無意識に調整していきます。これがバランス感覚や体幹の強化につながり、将来の運動発達全般(寝返り・ハイハイ・立位など)を支える基礎になると考えられています。
■■■おすわりをサポートする方法■■■
赤ちゃんがおすわりを始める頃に「どうやってサポートしてあげればいいのだろう?」と迷うこともありますよね。以下のような方法が、赤ちゃんのバランス感覚を育てながら無理なくおすわりを練習する手助けになるとされています。
●適度なクッションや抱っこ
最初から床に座らせるのではなく、ソファやクッションにもたれかからせる、膝の上で軽く背中を支えるなど、少しずつ慣れさせてあげると赤ちゃんも安心して座る感覚をつかみやすいです。
●左右や背後をしっかりサポート
まだ背筋が弱い頃は、少しの揺れで後ろにひっくり返ってしまうかもしれません。転倒を防ぐために、周囲にクッションを置いたりパパやママが近くで両手を広げて待機したりして、安全を確保してあげましょう。
●赤ちゃんが興味を持つおもちゃを前に置く
おすわりの状態で、赤ちゃんが興味を持ちやすいおもちゃを少し前方に置いてみるのも効果的。これによって前屈みになったり体勢を少し変えたりする練習にもなり、バランス感覚が養われます。
■■■おすわりの「早い・遅い」に対する考え方■■■
海外と日本のデータを見てもわかるように、おすわりが始まる時期には4か月〜8か月程度の幅があることが普通とされています。さらに、それより早い子もいれば、遅い子もいるのが現実です。
赤ちゃんの発達速度は本当に十人十色で、どこかが早ければ別の部分がゆっくりだったり、歩き始めが早い子がいたりとさまざまです。
●他の子と比べすぎない
「周りの赤ちゃんはもうしっかり座れているのに、うちの子はまだ…」と不安を感じるかもしれません。でも、個々の発達リズムに大きな差があるというのは、WHOの研究からも示唆されていることです。特におすわりの開始時期が少し遅くても、総合的に健康であればあまり神経質にならないほうがよいでしょう。
●気になる症状があれば専門家に相談
一方で、極端に体幹が弱い、筋力の発達に不安があるように感じる場合は、かかりつけ医や保健センターなどで相談してみるのもいいかもしれません。大きな病気や障害のサインであることはごく稀ですが、早めに確認しておくと安心です。
■■■楽しみ方■■■
育児を頑張っている親の立場から見ると、おすわりの時期は写真やビデオに残したくなる可愛らしい瞬間の連続ですよね。背筋をピンと伸ばして頑張っている様子や、ぐらっとなって転びそうになる姿も、愛おしくてたまりません。ぜひ心がけたい楽しみ方を挙げてみます。
●赤ちゃんと目線を合わせて声かけ
おすわりできるようになると、自然と顔の高さも変わってきます。パパが赤ちゃんと同じ目線になり、にこにこしながら「すごいね、上手に座ってるね!」と声をかけてあげるだけで、赤ちゃんも安心してバランスを取ろうとします。
●家族との触れ合いを増やす
おすわりが安定してきたら、パパの膝の上にちょこんと座らせて、一緒に絵本を読んでみるのはいかがでしょう。背中を支える必要はありますが、赤ちゃんにとってはパパと一緒にいる安心感と、新しい視野で見る絵本の面白さが同時に味わえます。
●おすわり記念日に一言メッセージ
「おすわり1日目」みたいに記録をつけると、後から振り返ったときに成長の過程がよくわかります。パパならではのユニークなコメントをそえておくと、大きくなった子どもが見返したときに喜ぶかもしれません。
■■■まとめ■■■
0歳児の「おすわり」は、ただ座るだけでなく、背筋・腹筋などの体幹の筋肉と視覚や前庭感覚などの感覚刺激が相互に影響しあって成立していると考えられています。WHOの研究によると支えなしで座る平均月齢は6か月前後、CDCのマイルストーンでも6か月健診の時期におすわりをチェックすることが推奨されています。日本国内でも、6〜7か月頃に「そろそろ座れるかな?」と見る場面が多いですね。
それでも、赤ちゃんによっては4か月で座り始める子もいれば、8か月ごろになってようやく安定する子もいます。この幅はまったく珍しいことではありません。大事なのは、赤ちゃんが安全におすわりの感覚をつかんでいける環境を整え、転倒やケガを防ぎつつ、赤ちゃんが自発的に「座りたい」「バランスを取りたい」という意欲を引き出せるようサポートすることです。ついつい「早くできるようになってほしい!」と急ぎがちですが、赤ちゃんにはそれぞれのペースがあるもの。おすわりが始まると、さらにハイハイやつかまり立ちへと発達が進んでいくため、
今のうちにしっかりと赤ちゃんのバランス感覚を育んであげることが、後の活発な動きや探究心を支える土台になる
と言えるでしょう。ぜひ、一瞬一瞬の可愛い姿を楽しみつつ、適度なサポートと安全対策を心がけてみてくださいね。赤ちゃんが一緒に成長を楽しめるよう、これからも応援しています!