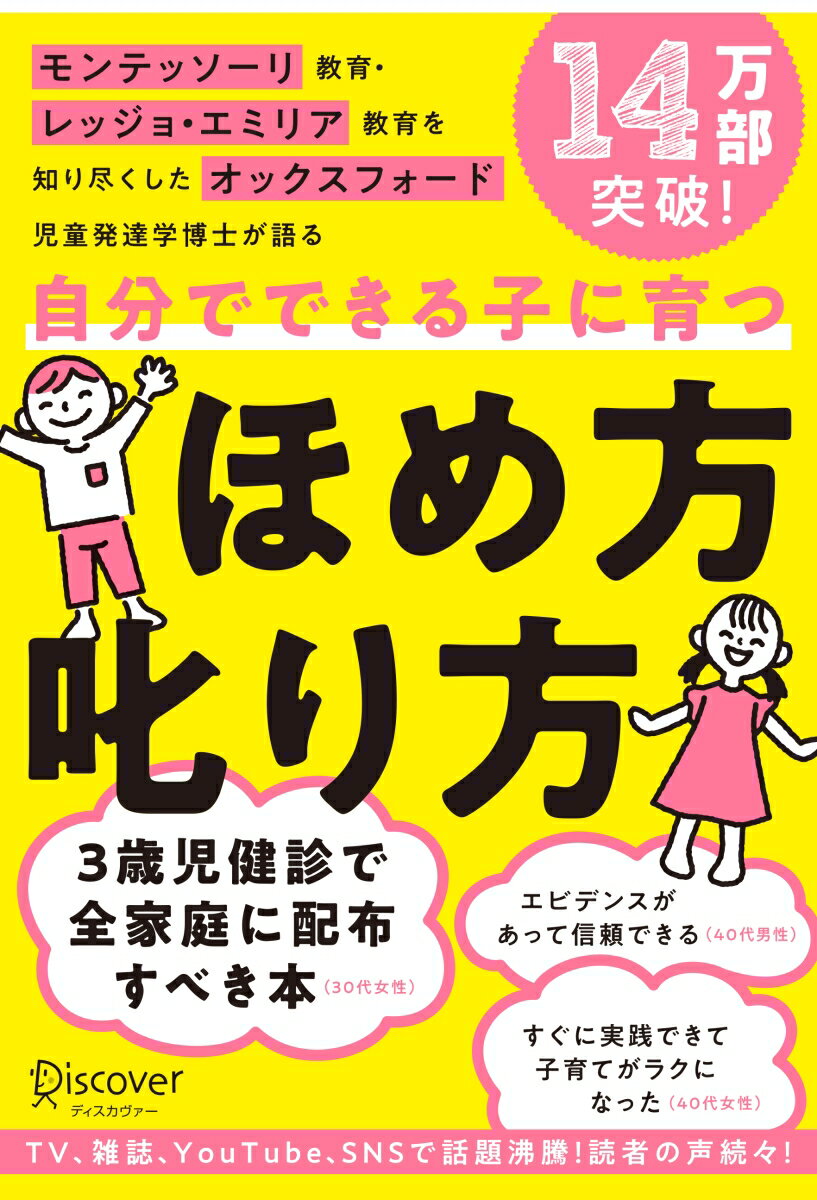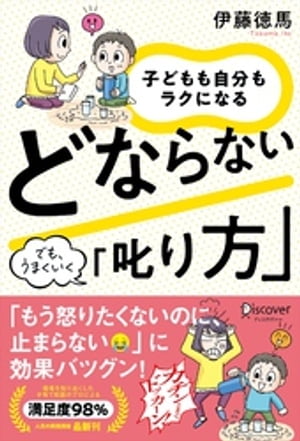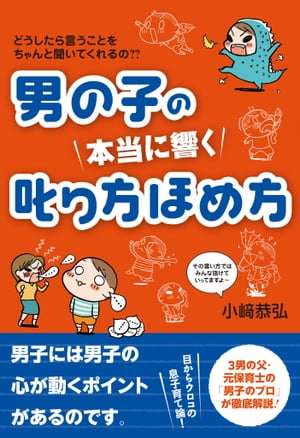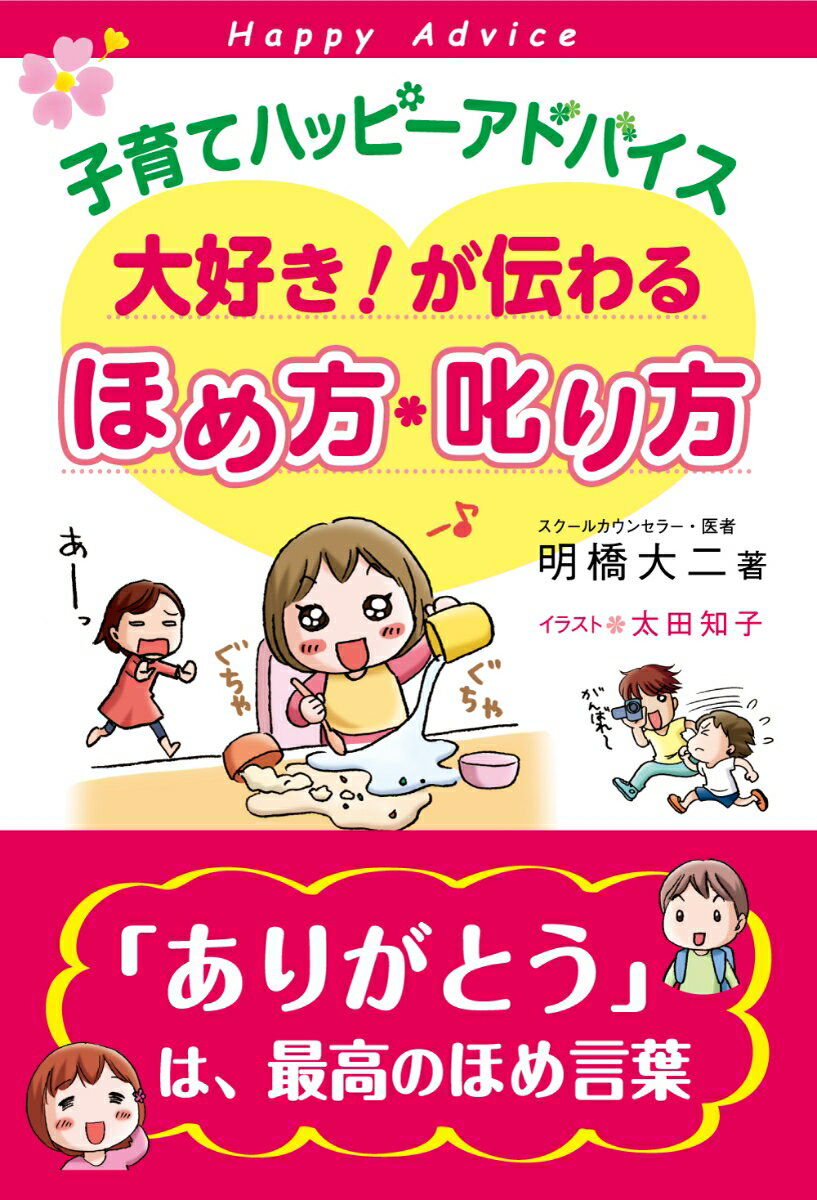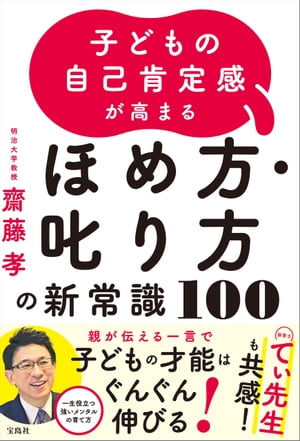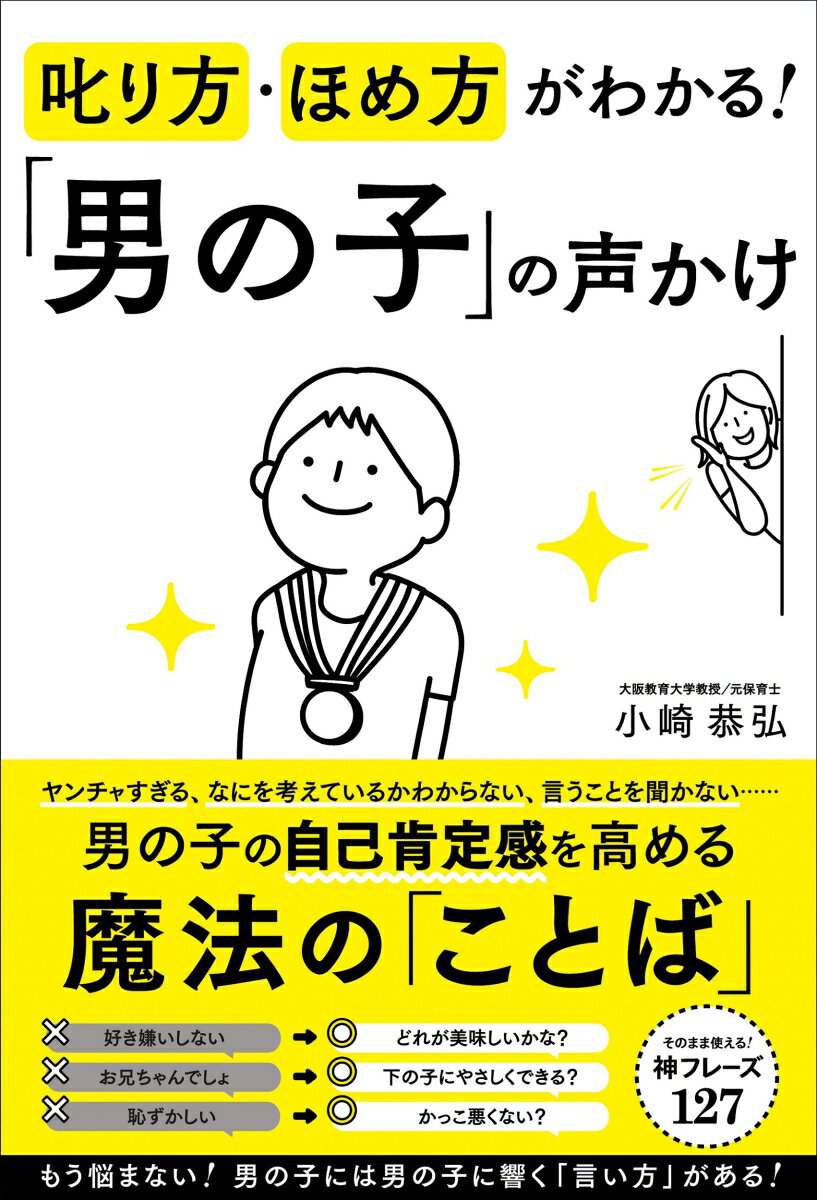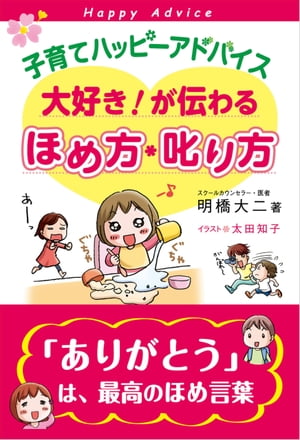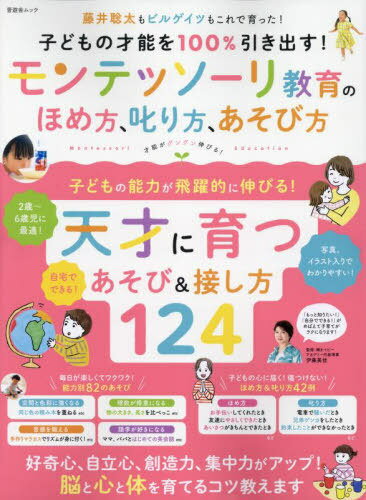【概要】
子どもを叱る行為は、ただ間違いを指摘するだけでなく、社会性や自制心を身につけるための教育的役割を果たします。しかし、一方的で激しい叱り方は子どもの精神面や発達にマイナスの影響を及ぼす危険が指摘されています。海外や日本の研究では、子どもの年齢や性格に合わせた適切な叱り方が重要だと示唆されており、その実践ポイントや注意点が注目されるようになりました。本記事では、具体的な研究データを紹介しつつ、子どもの成長を促す叱り方について考えます。
はじめに
子育てにおいて、「叱る」という行為は欠かせない要素の一つです。子どもに規範を伝え、自分や他者を守るためのルールを理解させるには、ある程度の注意や指導が必要です。とはいえ、ただ大声で怒鳴ったり、一方的に責め続けたりするやり方は、逆に子どもの心を傷つけてしまったり、発達面で悪影響をもたらす恐れがあります。
近年は、海外でも日本でも子どもへの「厳しすぎる叱責」と「適切な叱り方」についての研究が増え、親子関係や社会性の発達にどのような差が出るのかが検証されるようになりました。具体的な研究データから、子どもを上手に叱るために押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
子どもを叱ることの意味と難しさ
子どもを叱る目的は、「本人や周囲が安全・安心に過ごすためのルールや価値観を学ばせる」ことにあります。ただし、子ども自身はまだ言語能力や認知機能が未熟であり、発達段階によって理解できる内容や伝え方が異なるため、年齢や性格に合わせた方法を選ぶ必要があります。
一方で、親側も仕事や家事で疲れているときや、ストレスが溜まっているときに子どもの行動を見て感情的に叱ってしまうことがあるでしょう。その結果、子どもが何をどう改善すればいいのかを理解できず、ただ怖がるだけで終わってしまう場合もあります。'''適切な叱り方'''とは、子どもが「自分が何をすればよかったのか」を学べるように導くことを目的とするものです。
海外の研究例
厳しすぎる叱り方がもたらす悪影響
アメリカの研究者Gershoffらのメタ分析(Gershoff, 2016)では、身体罰を含む激しい叱責(いわゆる高圧的・攻撃的な叱り方)が子どもの攻撃性や不安症状を増幅させる傾向があると報告されています。'''この研究では、約160,000人を対象とした複数の研究データを総合した結果、過度な叱責は子どもの情緒不安定や反抗的態度を助長する可能性が示唆されました。'''
Gershoff ET. “Should Parents Spank Their Children? The evidence for and against physical punishment.” Child Development Perspectives. 2016;10(3):133-137.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27667850/
また、このメタ分析では身体的な暴力だけでなく、言葉による過剰な脅しや罵声なども同様のリスクを伴うと指摘しています。
積極的な子育てとの比較
アメリカ心理学会(APA)が公表したガイドライン(American Psychological Association, 2019)によると、子どもの行動を改善する際には、肯定的な行動を見つけて褒める「ポジティブ・ディシプリン」や、明確なルール設定と結果を一貫して伝える「コンサイス・ディシプリン」を取り入れた方が効果的だとされています。'''叱るだけではなく、良い行動を強化するアプローチが子どもの社会性や自尊心を育むうえで重要'''と述べられています。
日本の研究例
厚生労働省の子ども家庭総合研究
厚生労働省が「児童虐待や体罰などの影響」に関して行った子ども家庭総合研究(2020年公表)では、'''家庭内で頻繁に大声で叱られたり、身体的な罰を伴う叱責を受けたりした子どもは、学齢期以降に不登校や友人関係のトラブルを起こす率が約1.5倍高い'''という統計が示されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198321.html
研究チームは、叱責自体が悪いわけではなく、子どもが自分の行動を理解・修正できる方法で叱られるケースと、ただ恐怖や痛みに訴えるケースでは、その後の発達や対人関係の形成に大きな差が出ることを指摘しています。
認知行動療法を活用した指導法
一部の日本の教育心理学の実践報告によれば、認知行動療法(CBT)の考え方を取り入れた「子どもの言動の背景を探り、冷静に説明し、再度チャンスを与える」という叱り方を実践することで、'''児童の問題行動が約30%減少し、教室での落ち着き度が高まった'''というデータが得られています。教師や保育士が、叱る際に感情的になりすぎず、行動改善のゴールを具体的に示すことがポイントとされています。
望ましい叱り方のポイント
-
行動と結果を一貫して結びつける
- 「○○をしたからこうなった」という因果関係を明確に伝える。
- 子どもが具体的に「何がいけなかったのか」を理解できるようにする。
-
行動を否定しても人格は否定しない
- 「あなたはダメな子!」という言い方ではなく、「その行動は危ないからやめようね」と行動を分けて指摘する。
- 子ども自身の存在を否定されると、自尊心や自己肯定感が傷つきやすい。
-
短く、具体的に
- 長時間説教をすると、子どもは集中力を失い、結局何を指摘されているのか分からなくなる場合がある。
- できるだけ短い言葉で、どのように改善すべきかを明確に示す。
-
感情的になりすぎない
- 大声や怒鳴り声、脅しなどは子どもの恐怖や反発を呼び、学びが乏しくなるリスクが高い。
- 親自身がイライラしていると感じたら、落ち着いてから話をする方が効果的。
-
叱ったあとにフォローを入れる
- 「こうすればよかったね」「今度は一緒にやってみよう」と、改善策や次のステップを提案する。
- 気持ちを切り替えるきっかけを与え、愛情や安心感を再確認させると良い。
よくある疑問
Q1. まったく叱らないとどうなりますか?
A1. 子どもはルールや限度を学べないまま成長し、他者とのトラブルを起こしたり、自制心が育ちにくくなる可能性があります。研究でも、「しつけとしての叱り」が適切に行われない場合、'''思春期以降の問題行動が増加するリスク'''があると示唆されています。
Q2. 叱るのと褒めるの、どちらが大事ですか?
A2. 両方が必要です。'''褒める(肯定的に評価する)ことで良い行動を強化し、叱ることで危険行動や迷惑行為を抑制する'''のがしつけの基本です。ただし、叱る頻度や方法が不適切だと逆効果になるため、褒める・叱るのバランスが重要と言えます。
Q3. 何度言っても同じ失敗を繰り返すときはどうすれば?
A3. 同じ行動を繰り返す原因がどこにあるのかを探りましょう。環境が整っていない、具体的な代替策を学べていないなど、子ども側に理解や実践のハードルがあるケースも。'''冷静に「どうすれば次はうまくいくか」を一緒に考える時間'''を設け、成功体験を増やす工夫が求められます。
まとめ
子どものしつけにおいて「叱る」ことは欠かせない要素ですが、'''叱り方次第で子どもの発達には大きな差が生まれる'''と、海外・日本双方の研究から示唆されています。アメリカのGershoff(2016)のメタ分析では、過度に厳しい叱り方が子どもの攻撃性や情緒不安定を増幅させる可能性が報告され、厚生労働省の子ども家庭総合研究でも、大声や身体的暴力を伴う叱責が学齢期以降のトラブル率を約1.5倍高めるといったデータが見られました。
一方で、叱る際の言葉選びや感情コントロールを工夫することで、子どもに「何がいけなかったのか」「どのように直せばいいのか」を的確に伝え、発達をサポートすることができます。「行動は否定しても人格は否定しない」「短く、具体的に伝える」「叱ったあとのフォローを忘れない」などのポイントを押さえれば、子どもが安心感と学習意欲を保ちやすくなります。
また、研究では「叱る」だけでなく「褒める」ことが良い行動を強化するうえで重要という見解も強調されています。叱り方のバランスが崩れると、子どもの自尊心や自己肯定感を傷つける可能性があるため、適切なタイミングで褒めたり、成功体験を積ませるアプローチと併用するのが理想的です。
「まったく叱らない」「感情に任せて叱る」という両極端は避け、子どもが安心して自分の行動を振り返り、少しずつ成長していけるよう、親や保育者が穏やかに導くことが大切です。子どもの性格や発達段階を見極めながら、伝え方を工夫し、親子のコミュニケーションをより豊かにしていきましょう。
(本記事はGershoff (Child Development Perspectives, 2016)の分析や厚生労働省の子ども家庭総合研究、その他日本の教育心理学に関する実践報告を参考に執筆しています。子どもの叱り方や発達について不安がある場合は、自治体や専門家に相談することをおすすめします。)