サリーとチャリンコで散歩久々に史跡巡り
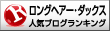
ロングヘアー・ダックスフンドランキングへ
最初は播磨塚と小野塚
現地の解説板(阿倍野区史跡顕彰会)によると、『播磨塚』は、南北朝の頃、住吉の合戦で南朝の忠臣楠正行と戦って敗れた播磨の太守、赤松円心の子貞範が、戦死した将兵の遺骨を納めて塚を築き、播磨塚と名付け部下の冥福を祈ったと伝えられている。
『小野塚』
古書『芦分船』には、小野小町の塚であると説明しているが、小野小町がこの地で死んだという記録はなく、小野小町の美貌や才能にあやかりたいとの念願から、信仰などの目的のため造られたものと思われる。
北畠顕家は『神皇正統記』を著した北畠親房の長男で、1330年(元徳2年)13歳で左中弁となり、15歳未満で弁官に任ぜられるという先例を開き、14歳で参議で左中将を兼ねるという空前の昇進を示した,
1333年(元弘3年)『建武の中興』が成立の時16歳で陸奥守に任ぜられ、義良親王を奉じて奥州に下り、鎮守府将軍に任じられている。
1336年(延元元年)足利尊氏が反逆すると、上洛して尊氏を九州に敗走させた。この功績により、顕家は権中納言、鎮守府将軍に任ぜられ、再び奥州に下っている。
3カ月後、尊氏が勢いを盛り返しため、1337年(延元2年)奥州より再度上洛。各地で転戦、翌年3月16日に当地、阿倍野での合戦後、『神皇正統記』などには顕家は1338年(延元3年)5月22日朝、1万8千の高師直軍と戦い、摂津国石津(現在の堺市西区浜寺石津町)で戦死したと伝えている。
顕家の墓は、現在の王子町北畠公園に所在する『大名塚』と呼ばれていた塚を、江戸時代の国学者並川誠所が墳墓と比定したことにより、当地周辺を顕家戦没ゆかりの地として顕彰したもので、現在の歴史観から見れば事実誤認があるようだが、園内の碑文などによると、大正・昭和と篤志家などの寄付により、墓地の整備などが図られ、現在に至っている。
近くの昔ながらの銭湯播磨湯
阿倍野区松崎町一帯には『阿部寺』『東阿部寺』などの字名が残っており、このあたりを本拠にしていたといゆう阿部氏の氏寺で阿部寺跡に推定されている。阿部寺は『阿部寺千軒』と呼ばれ広大な伽藍を有していたと伝えられる。第ニ次世界大戦直後には、建物の基壇跡ではないかといわれる小丘が残っていたが、現在ではそれも失われ、寺院の伽藍配置など詳しいことは不明である。昭和10年(1935)には、松長大明神の付近から塔心礎と考えられる礎石と布目瓦が出土しているほか、道路工事等に伴い、若千の河原が採集されている。その中には、複弁八葉蓮華文軒丸瓦や重狐文軒平瓦など、白鳳時代にさかのぼるものもある。礎石は、大阪府有形文化財に指定され、現在西成区の天下茶屋公園内に移設されている。
大阪教育委員会
ロングヘアー・ダックスフンドランキングへ





















