こんばんは。
今日は、大学の法学部での講義や、司法試験の基本書として比較的よく用いられている『憲法』芦部信喜著について、保守思想の立場から簡単ながら批判を加えてみたいと思います。
いわゆる一般的な「法律家」「法学者」といわれる人々がどのような法的概念を学び、駆使しているのかを憲法学について知り、そのどこが問題なのかを知ることで、『日本国憲法』の問題点も見えてきます。
今日は、憲法学の基本的な法理論である、おなじみの「憲法の定義」や「法の支配」などについて採り上げます。なお、引用やページは第四版のものです。
なお、文中においては敬称を省略させて頂きましたこと、何卒ご海容下さい。
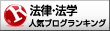
ランキングに参加しています。まず初めに何卒クリックをお願い致します。
1.保守思想とは
まず、ごく簡単に、そもそも保守思想とは何か、その概略を振り返っておきましょう。
保守思想とは、その国民が祖先から相続、継承してきた道徳や慣習、伝統、文化などという「法(不文の法)」を守ることで、その国民らしさ(国体)を守り、ひいてはその国民の自由をも守る、という思想です。
保守思想の特徴は、このような「法」と、その時代時代の為政者や議会の多数決などによって制定された「法律(または命令など)」を完全に区別することです。
法律は法に違反しない範囲で制定されねばならず、よって法律は法を成文化したものか、または法に反しない程度の新たな規範を創設する限度でのみ有効となります。法に反する法律は無効です。
この保守思想が憲法学において理論化されたものを、法の支配、または立憲主義といいます。憲法学においては、法(不文憲法)に反する法律(成文法)を無効と確認することを、違憲立法審査といいます。
保守思想については、こちらの「保守思想入門(1)」以降を参照下さい。
2.憲法の定義について
では、芦部信喜『憲法』が、憲法とは何か、について、どのように解説しているかを見てみます。まず、憲法の「実質的意味」を、「固有の意味」と「立憲的意味」に分けています。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーーーー
(1)固有の意味 ・・・(略)・・・この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。
(2)立憲的意味 ・・・(略)・・・自由主義に基づいて定められた国家の基本法である。・・・(略)・・・専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。・・・(略)・・・その最も重要なねらいは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。(注1)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーーー
ここで解説されているのは、憲法の定義というよりも、憲法の特徴、機能というべきです。これを読んだだけでは、憲法典には具体的にどのような事柄を条文化して盛り込むべきなのかが、ほとんど見えてきません。
憲法(憲法典)とは、国家の機関や権力の組織と作用および相互の関係を規律しているという理解は是認できますし、憲法(憲法典)が専断的な権力の行使を制限し、国民の権利を保障するものであるというのも、言葉を「正しく」解釈すれば正当です。しかし、これらはあくまで憲法典の機能の一面でしかありません。
そして、何よりも気をつけねばならないのは、ここで前提とされている「国民の権利」が、『権力を制限して人権を保障することにある』で分かるように、「基本的人権」と同義で用いられていることなのです。
従って、ここでいう「自由主義」もまた、保守思想での「(道徳に基づく正しい意味の)自由主義」とは対極にあるものなのです。
こうして、すでに出発点から、理性万能思想に基づく憲法観がはっきりと現れています。
正しくは、憲法典の定義とは、その国民が祖先から相続、継承してきた道徳や慣習、伝統、文化などという「法(不文の法)」を成文化したものというべきです。
そしてその主たる機能は、その国民らしさ(国体)を守り、ひいてはその国民の自由をも守ることにある、というべきです。
3.法の支配について
実は、この著書においても、「法の支配」の観念は登場してはいます。では、どのように書かれているのでしょうか。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本的原理である。それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。(注2)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
この記述は、ほぼ正当ですが、やはりこれも「法の支配」の定義というよりもその機能の一つであるというべきでしょう。しかも、その少し前には、このように書かれているのです。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わねばならない高次の法( higher law )があると考えられ、根本法 ( fundamental law )とも呼ばれた。この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。
もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へと発展するためには、ロック ( John Locke, 1632 - 1704 )やルソー ( Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 78)などの説いた近代自然法ないし自然権 ( natural rights ) の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。この思想によれば、①人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、②その自然権を確実なものにするために社会契約 ( social contract ) を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、③政府が権力を恣意的に行使して人民の権力を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。(注3)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
この箇所には、大変大きな問題があります。
そもそも、西洋中世における根本法(すなわち「法」)とは、この著書では一切触れられていませんが、我が国と同様、祖先から継承した道徳や慣習、伝統などの不文の法でした。
しかし、ここではご覧のように、それが「近代的な憲法へと発展するためには、ロック ( John Locke, 1632 - 1704 )やルソー ( Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 78)などの説いた近代自然法ないし自然権 ( natural rights ) の思想によって新たに基礎づけられる必要があった」というのです。
つまり、当初は封建的なものであった「法の支配」という概念が、近代合理主義思想の影響の下、「自然法」ないし「自然権」の要素を帯び、その系譜にある「基本的人権」の保護を意味するものへと変遷したというのです。
法というものは、一面、封建制度の維持をもその目的とします。なぜならば、封建制度の維持こそが、道徳や慣習に基づく「正しい自由」の擁護につながるからです。封建制度もまた、道徳や慣習、伝統を構成するものです。
しかるに、このくだりは「封建的性格」を、ごく一部の貴族だけを益する悪であるかのようにとらえています。これは保守思想の立場からは明らかに不当であり、やはり理性万能思想による捉え方です。
なお、封建制度と自由との関わりについては、こちらをご覧下さい。→ 「保守思想入門(6)法と自由」
そもそも、道徳や慣習や伝統などというものを一切捨象した、「生まれながらの」(つまり他者との関わりなく、己一個で成立する観念である)自然権とは、この「法」に根本的に対立し、これを否定するものです。
基本的人権も、「国」民の権利ではない、「人」の権利、すなわち祖先から継承してきた国家を否定することを前提とするものであり、この自然権の思想の系譜上にあるものです。
しかるに、このくだりは、「法」が、近代に下るにつれて、「自然権」「基本的人権」を意味するものに変遷していった、というのです。
つまり、中世においては「法の支配」とは一部の貴族だけの特権の保護のためのものであったが、近代に入り、「基本的人権の擁護」へと変遷した、というのです。
ある物事が、その本質を保ちつつ発展していくというならば、それを同じ名称で呼ぶのは構わないでしょう。
しかし、全く対極の概念、しかも互いを排斥、否定する概念に変遷するというのは、そもそも言葉の用い方として理解し難いところです。
何のことはない、これは、勝手に「基本的人権」のことを、「法」と言い換えているだけです。
「基本的人権の保護」を「法の支配」の意味で用いるのは、近代啓蒙思想、理性万能思想の中で登場してきた「自然権」「基本的人権」の観念が、あたかも本来の意味の「法の支配」と関わりがあるかのような錯覚を起こさせるのです。
「基本的人権」そのものを否定、排撃する「法の支配」を「基本的人権の保護」と読み替えるというのは、矛盾であり、完全な誤りであるという以外にありません。
正しくは、「法の支配」とは祖先から継承してきた道徳、慣習、伝統などの「法(不文の法)」を守ることによって、その国民の道徳に基づく「正しい」自由を守るもの、と定義せねばなりません。
また、②は「法の支配」概念と対極の「主権論」を前提とする「社会契約説」に基づくものであり、③はいわゆる「革命権」を肯定するものであって、こんなものは到底「法の支配」概念とは水と油の如く相容れないものですが、あたかも「法の支配」の要素をなすものであるかのように書かれているのです。
4.成文憲法(憲法典)について
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることもできるが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。(注4)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーー
ここでは、「成文法は慣習法に優る」、すなわち「不文の法」の存在そのものを否定する思想が説かれています。そしてそれはここにもあるように、「近代合理主義」、すなわち理性万能主義であり、保守思想の対極にあるものに他なりません。
こうして、この著書に現れている憲法理論とは、そもそもの初めの前提からして、保守思想というものの存在を無視、否定する理性万能思想に基づいていることがはっきりと読み取れます。
すなわち、ここに表現されているのは、「書かれていないものは存在していない」という人定法主義であり、法の支配(立憲主義)の対極にあるものです。
一方では『日本国憲法』には「法の支配」が存在するといいながら、このように、ここでは『日本国憲法』には「法の支配」を否定、排撃する「人定法主義」が存在すると言っているのです。一体どっちなのでしょうか。何が言いたいのでしょう。もう何のことやら分からなくなってしまいます(笑)。
そして、何よりも見逃してはならないのは、「国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要」というくだりです。
たとえば、我が国において、成文憲法が必要とされた背景には、十七条憲法(隋など大陸諸国との交流)、大日本帝国憲法(明治維新)のように、諸外国との交流などに伴い、それまで我々日本人の間だけならば「当たり前」だったこと(不文の法)を、成文化する必要があったからです。
すなわち、「当たり前」のことは、通常は成文化する必要はないのです。外来思想の流入などで、「あえて」これらを確認する必要があるときだけ、成文憲法が必要となるに過ぎないのです。
しかるに、このくだりにおいては、成文憲法が必要である理由をいわゆる「社会契約説」に求めています。
もしも、「自由な個人」などというものが存在し、彼らが「社会契約」などというものを結んで国家を作ったとなどという説が正しいのであれば、そのような「当たり前」のことは成文化して「文書の形にする必要」などあるはずがないではありませんか。
よって、このくだりは、図らずも「社会契約説」が妄説であることを明らかにしているのです。
(注1)『憲法』芦部信喜 著 高橋和之 補訂 (第四版) p.4 ~ p.5
(注2)同上 p.13 ~ p.14
(注3)同上 p.5 ~ p.6
(注4)同上 p.6
今日は、大学の法学部での講義や、司法試験の基本書として比較的よく用いられている『憲法』芦部信喜著について、保守思想の立場から簡単ながら批判を加えてみたいと思います。
いわゆる一般的な「法律家」「法学者」といわれる人々がどのような法的概念を学び、駆使しているのかを憲法学について知り、そのどこが問題なのかを知ることで、『日本国憲法』の問題点も見えてきます。
今日は、憲法学の基本的な法理論である、おなじみの「憲法の定義」や「法の支配」などについて採り上げます。なお、引用やページは第四版のものです。
なお、文中においては敬称を省略させて頂きましたこと、何卒ご海容下さい。
ランキングに参加しています。まず初めに何卒クリックをお願い致します。
1.保守思想とは
まず、ごく簡単に、そもそも保守思想とは何か、その概略を振り返っておきましょう。
保守思想とは、その国民が祖先から相続、継承してきた道徳や慣習、伝統、文化などという「法(不文の法)」を守ることで、その国民らしさ(国体)を守り、ひいてはその国民の自由をも守る、という思想です。
保守思想の特徴は、このような「法」と、その時代時代の為政者や議会の多数決などによって制定された「法律(または命令など)」を完全に区別することです。
法律は法に違反しない範囲で制定されねばならず、よって法律は法を成文化したものか、または法に反しない程度の新たな規範を創設する限度でのみ有効となります。法に反する法律は無効です。
この保守思想が憲法学において理論化されたものを、法の支配、または立憲主義といいます。憲法学においては、法(不文憲法)に反する法律(成文法)を無効と確認することを、違憲立法審査といいます。
保守思想については、こちらの「保守思想入門(1)」以降を参照下さい。
2.憲法の定義について
では、芦部信喜『憲法』が、憲法とは何か、について、どのように解説しているかを見てみます。まず、憲法の「実質的意味」を、「固有の意味」と「立憲的意味」に分けています。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーーーー
(1)固有の意味 ・・・(略)・・・この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。
(2)立憲的意味 ・・・(略)・・・自由主義に基づいて定められた国家の基本法である。・・・(略)・・・専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。・・・(略)・・・その最も重要なねらいは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。(注1)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーーー
ここで解説されているのは、憲法の定義というよりも、憲法の特徴、機能というべきです。これを読んだだけでは、憲法典には具体的にどのような事柄を条文化して盛り込むべきなのかが、ほとんど見えてきません。
憲法(憲法典)とは、国家の機関や権力の組織と作用および相互の関係を規律しているという理解は是認できますし、憲法(憲法典)が専断的な権力の行使を制限し、国民の権利を保障するものであるというのも、言葉を「正しく」解釈すれば正当です。しかし、これらはあくまで憲法典の機能の一面でしかありません。
そして、何よりも気をつけねばならないのは、ここで前提とされている「国民の権利」が、『権力を制限して人権を保障することにある』で分かるように、「基本的人権」と同義で用いられていることなのです。
従って、ここでいう「自由主義」もまた、保守思想での「(道徳に基づく正しい意味の)自由主義」とは対極にあるものなのです。
こうして、すでに出発点から、理性万能思想に基づく憲法観がはっきりと現れています。
正しくは、憲法典の定義とは、その国民が祖先から相続、継承してきた道徳や慣習、伝統、文化などという「法(不文の法)」を成文化したものというべきです。
そしてその主たる機能は、その国民らしさ(国体)を守り、ひいてはその国民の自由をも守ることにある、というべきです。
3.法の支配について
実は、この著書においても、「法の支配」の観念は登場してはいます。では、どのように書かれているのでしょうか。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本的原理である。それは、専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。(注2)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
この記述は、ほぼ正当ですが、やはりこれも「法の支配」の定義というよりもその機能の一つであるというべきでしょう。しかも、その少し前には、このように書かれているのです。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わねばならない高次の法( higher law )があると考えられ、根本法 ( fundamental law )とも呼ばれた。この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。
もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へと発展するためには、ロック ( John Locke, 1632 - 1704 )やルソー ( Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 78)などの説いた近代自然法ないし自然権 ( natural rights ) の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。この思想によれば、①人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、②その自然権を確実なものにするために社会契約 ( social contract ) を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、③政府が権力を恣意的に行使して人民の権力を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。(注3)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
この箇所には、大変大きな問題があります。
そもそも、西洋中世における根本法(すなわち「法」)とは、この著書では一切触れられていませんが、我が国と同様、祖先から継承した道徳や慣習、伝統などの不文の法でした。
しかし、ここではご覧のように、それが「近代的な憲法へと発展するためには、ロック ( John Locke, 1632 - 1704 )やルソー ( Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 78)などの説いた近代自然法ないし自然権 ( natural rights ) の思想によって新たに基礎づけられる必要があった」というのです。
つまり、当初は封建的なものであった「法の支配」という概念が、近代合理主義思想の影響の下、「自然法」ないし「自然権」の要素を帯び、その系譜にある「基本的人権」の保護を意味するものへと変遷したというのです。
法というものは、一面、封建制度の維持をもその目的とします。なぜならば、封建制度の維持こそが、道徳や慣習に基づく「正しい自由」の擁護につながるからです。封建制度もまた、道徳や慣習、伝統を構成するものです。
しかるに、このくだりは「封建的性格」を、ごく一部の貴族だけを益する悪であるかのようにとらえています。これは保守思想の立場からは明らかに不当であり、やはり理性万能思想による捉え方です。
なお、封建制度と自由との関わりについては、こちらをご覧下さい。→ 「保守思想入門(6)法と自由」
そもそも、道徳や慣習や伝統などというものを一切捨象した、「生まれながらの」(つまり他者との関わりなく、己一個で成立する観念である)自然権とは、この「法」に根本的に対立し、これを否定するものです。
基本的人権も、「国」民の権利ではない、「人」の権利、すなわち祖先から継承してきた国家を否定することを前提とするものであり、この自然権の思想の系譜上にあるものです。
しかるに、このくだりは、「法」が、近代に下るにつれて、「自然権」「基本的人権」を意味するものに変遷していった、というのです。
つまり、中世においては「法の支配」とは一部の貴族だけの特権の保護のためのものであったが、近代に入り、「基本的人権の擁護」へと変遷した、というのです。
ある物事が、その本質を保ちつつ発展していくというならば、それを同じ名称で呼ぶのは構わないでしょう。
しかし、全く対極の概念、しかも互いを排斥、否定する概念に変遷するというのは、そもそも言葉の用い方として理解し難いところです。
何のことはない、これは、勝手に「基本的人権」のことを、「法」と言い換えているだけです。
「基本的人権の保護」を「法の支配」の意味で用いるのは、近代啓蒙思想、理性万能思想の中で登場してきた「自然権」「基本的人権」の観念が、あたかも本来の意味の「法の支配」と関わりがあるかのような錯覚を起こさせるのです。
「基本的人権」そのものを否定、排撃する「法の支配」を「基本的人権の保護」と読み替えるというのは、矛盾であり、完全な誤りであるという以外にありません。
正しくは、「法の支配」とは祖先から継承してきた道徳、慣習、伝統などの「法(不文の法)」を守ることによって、その国民の道徳に基づく「正しい」自由を守るもの、と定義せねばなりません。
また、②は「法の支配」概念と対極の「主権論」を前提とする「社会契約説」に基づくものであり、③はいわゆる「革命権」を肯定するものであって、こんなものは到底「法の支配」概念とは水と油の如く相容れないものですが、あたかも「法の支配」の要素をなすものであるかのように書かれているのです。
4.成文憲法(憲法典)について
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることもできるが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。(注4)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーー
ここでは、「成文法は慣習法に優る」、すなわち「不文の法」の存在そのものを否定する思想が説かれています。そしてそれはここにもあるように、「近代合理主義」、すなわち理性万能主義であり、保守思想の対極にあるものに他なりません。
こうして、この著書に現れている憲法理論とは、そもそもの初めの前提からして、保守思想というものの存在を無視、否定する理性万能思想に基づいていることがはっきりと読み取れます。
すなわち、ここに表現されているのは、「書かれていないものは存在していない」という人定法主義であり、法の支配(立憲主義)の対極にあるものです。
一方では『日本国憲法』には「法の支配」が存在するといいながら、このように、ここでは『日本国憲法』には「法の支配」を否定、排撃する「人定法主義」が存在すると言っているのです。一体どっちなのでしょうか。何が言いたいのでしょう。もう何のことやら分からなくなってしまいます(笑)。
そして、何よりも見逃してはならないのは、「国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要」というくだりです。
たとえば、我が国において、成文憲法が必要とされた背景には、十七条憲法(隋など大陸諸国との交流)、大日本帝国憲法(明治維新)のように、諸外国との交流などに伴い、それまで我々日本人の間だけならば「当たり前」だったこと(不文の法)を、成文化する必要があったからです。
すなわち、「当たり前」のことは、通常は成文化する必要はないのです。外来思想の流入などで、「あえて」これらを確認する必要があるときだけ、成文憲法が必要となるに過ぎないのです。
しかるに、このくだりにおいては、成文憲法が必要である理由をいわゆる「社会契約説」に求めています。
もしも、「自由な個人」などというものが存在し、彼らが「社会契約」などというものを結んで国家を作ったとなどという説が正しいのであれば、そのような「当たり前」のことは成文化して「文書の形にする必要」などあるはずがないではありませんか。
よって、このくだりは、図らずも「社会契約説」が妄説であることを明らかにしているのです。
(注1)『憲法』芦部信喜 著 高橋和之 補訂 (第四版) p.4 ~ p.5
(注2)同上 p.13 ~ p.14
(注3)同上 p.5 ~ p.6
(注4)同上 p.6