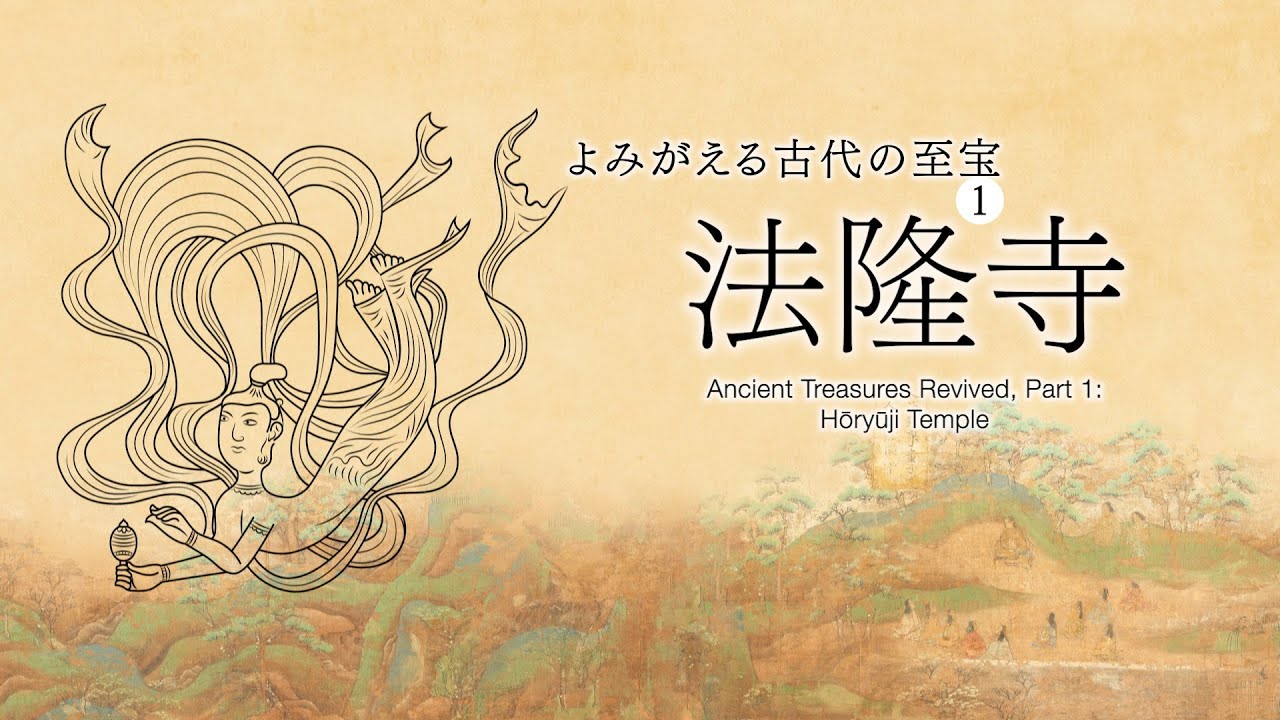開館30周年を迎える近つ飛鳥博物館を初訪問しました。変換しにくい名前![]() ですが、古事記に因む名前らしい。
ですが、古事記に因む名前らしい。
博物館の建物は安藤忠雄氏がデザインしたコンクリート打ちっぱなしの建物で、前方後円墳を意識したそうです。
本日のお目当ては6月16日まで開催中の「四天王寺と古代王権」の講演会。
展示
瓦
四天王寺は聖徳太子が存命中に建立したとされる寺院で今も法灯を伝えます。同じく太子が建立したとされる法隆寺の若草伽藍(日本書記によると670年に焼失)と同じ型を使った瓦が用いられています。
発掘調査に伴って最近また瓦が出たみたいや![]()
創建当初の法隆寺「若草伽藍」南端の溝か 被災後の瓦?も大量に出土 https://t.co/vrIw1ltSLl
— 朝日新聞文化部 (@asahi_bunka) February 29, 2024
若草伽藍(現在、非公開)は現在の法隆寺よりも古い建築物(斑鳩寺)で塔と金堂が一直線に並ぶ四天王寺式伽藍配置(日本に公式に仏教を伝えた百済のスタイル)であったことが発掘調査からわかっています。
四天王寺を西側から
上からグーグルマップで(↑が北です)
太子の墓
常設展示に太子が葬られた叡福寺にある古墳(円墳)内部の復元展示がありました。
叡福寺16は隣の町で博物館13から近い。
現在は宮内庁管理で立ち入り禁止ですが、残っている記録から再現しています。
講師①: 一本崇之 氏(大和文華館)「古代四天王寺の残影-伝来宝物と史料からー」
一本氏の前職は四天王寺の宝物館の学芸員。四天王寺は落雷、空襲などの災害で何度も焼失したので、伝えられた資料は多くありません。再建に伴って、昭和の発掘調査が行なわれました。
フムフムと思ったこと…
•現在の四天王寺の敷地は甲子園球場二つ分に相当する11ha
舎利
•四天王寺は舎利を大事にして、舎利職を置いています。
最後に、ご監修の #小野真龍 先生のコラム。四天王寺独特の「舎利職」とは何か、また願文に秘められた思想とは。ご一読ください。#四天王寺 #聖霊会 pic.twitter.com/71bf3TktEZ
— 中田文花 (@nakatabuncho) December 30, 2020
太子が数え2歳(今でいう1歳)の時、「南無仏」と手を合わせたところ、手のひらから仏舎利が出現した![]() という話が伝わっているからです。
という話が伝わっているからです。
四天王寺にはお釈迦様の遺骨とされるいわゆる舎利と太子の手から出現した舎利と二つ。
•五重塔
昭和に再建された五重塔には階段があって登ることができます(毎月22日)。さりぃも登ったけど最上階に仏舎利が祀られていたとはあまり意識せんかった。
#聖徳太子 の月命日22日は 「太子忌」として大阪 #四天王寺 の中心伽藍は無料開放され、絵解きも。#五重塔 が開扉され、5階まで螺旋階段で初登頂。外には出られず写真🈲で、外国人率高し。11月22日は 、曲尺を持つ聖徳太子の法要が行われ #番匠堂 も開扉。仏教建築技術を大陸から導入した大工の神様。 pic.twitter.com/d7zbexlavr
— Sally_Osaka (@osaka654) November 22, 2023
•亀石(ここ撮影禁止)
亀井堂の水槽が7世紀の飛鳥時代の石で、明日香村にある酒船遺跡と同時代という話は知ってしました。今回は、四天王寺の亀の部分は後付けで元々の形は酒船遺跡とそっくりな形という話に驚き😲お堂が立っているので見えませんが現在も湧き続ける水(講演後質問しました)を利用して何か儀式をしていたという話でした。
現在は上の亀の頭と甲羅がついた水槽から、下の亀形水槽に水が流れ込んでいますが、上の水槽の頭と甲羅は後世に付け足されたもので、元の姿は酒船石遺跡の亀形石造物とよく似ていたようです。水の祭祀は王権と関わりが深く、亀形石槽と645年に飛鳥から遷都した難波宮の関係にも注目が集まりそうです。 pic.twitter.com/rLLNalNL5a
— 今井邦彦 Kunihiko Imai (@imaikuni) April 26, 2019
古墳時代のブランド石材、播磨の竜山石が使われています。
国道250号でイオン高砂店までくると忽然と現れる竜山。古墳好きならお馴染みの竜山石は、1700年前から今も現役で採石されている。まるで竜のような形をしたこの山は、美しく均質性があり軟質で加工がしやすい凝灰岩でできている。 pic.twitter.com/zc1IcPPMp0
— プチ (@tubamego) March 9, 2022
亀の池のほうも湧き水ですかと聞くべきやった💦
四天王寺の聖霊会(しょうりょうえ)の舞楽を見てきました。聖徳太子の命日におこなわれる大法要。舞も装束も音も、とてもおもしろかった。六時礼讃堂の石舞台の周りには多くの人、池には亀もたくさん。 pic.twitter.com/JCCRuQbdYQ
— Matsusaka T / 松阪崇久 (@matsusakat) April 22, 2023
•絵堂
今でも絵解きが行われる聖徳太子絵伝のルーツは奈良時代らしい。
おおきに!四天王寺の「絵堂」が31日まで限定公開されてるよ!聖徳太子の伝説を描いた壁画が納められてるんだ☆期間中は記念品ももらえて、拝観無料!#四天王寺 #聖徳太子http://t.co/Kf7IMGr1lc pic.twitter.com/1lVCLq6cPw
— Osaka Bob〈公式〉 (@Bobfamily_ogtb) October 28, 2014
絵伝は法隆寺にも伝わります
四天王寺に伝わる最古の絵伝は徳川秀忠が再建した絵堂に狩野山楽が描いたもの。江戸時代の火事による損傷があります。
伝世品(寺宝)
•直刀(飛鳥時代、国宝)
北斗七星が象嵌された刀と飾りのないシンプルな飛鳥時代の直刀のペアが伝わっています。正倉院、法隆寺にも同じペアが伝わっているので、聖徳太子の持ち物であったという寺伝はほんまかも。
•赤い布の欠片(唐花文袍残闕)
太子が着用したと伝わる緋色の衣装の一部で、飛鳥時代のものです。絵画では太子のトレードマークは赤い衣服なので、太子の所有物であった可能性は十分。
確かにこれも赤やわ
金堂のご本尊
昭和に再建された金堂のご本尊は別尊雑記に基づいて造像されました。
↓これは大阪地下鉄のポスターにある金堂の救世観音
別尊雑記自体の成立は平安時代最末期作成やねんけど、用いられたのは1321年バージョンというややこしい話。
960年に四天王寺は全山焼失に見舞われ、仏像の安否は不明。従って、後に描かれた図像の初代本尊かどうかについても不明(これも質問した)。
↓向かって左の図が別尊雑記らしい。
秋季名宝展 四天王寺の菩薩たち─観音菩薩を中心に─
— 関西の展示 (@kansai_tenji) September 8, 2023
同時開催 伽藍ノ変遷ヲ辿ル─元和ヨリ令和ヘ─
2023.9.9(土)~11.5(日)会期中無休#大阪 #四天王寺宝物館 https://t.co/WPUee9AByG pic.twitter.com/NLEdmJ3MAX
ポスターの右側には試みの観音と呼ばれる白鳳時代の像で8月の千日詣りの時に聖霊院で御開帳されます。
京都三千院の救世観音も四天王寺の本尊を模したものと伝わります。
#聖徳太子展 10/24まで📯
— 【休館中】大阪市立美術館|2025年春リニューアルオープン! (@ocmfa_since1936) October 21, 2021
大聖勝軍寺の四天王立像
三千院の救世観音半跏像
どちらもかつて四天王寺金堂に祀られていた四天王像と救世観音像を模して作られた像。
ありし日の金堂はどうだったか?と想像できるよう、試みにこれらを共に展示しています。
画像だとライトの反射で近未来的ムードに… pic.twitter.com/HR66Rv0iWl
四天王は法隆寺金堂のものとも似ているそうです。筋力ムキムキではなく文官タイプ。
(続く)