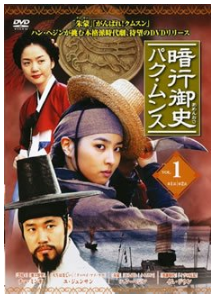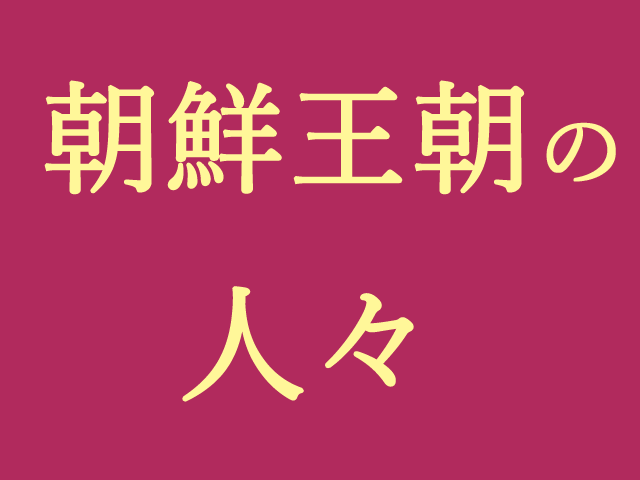🏹地方の悪政を糾弾した特命監察官「暗行御史」。
暗行御史は、国王の特命を受けて、地方に行き、身分を隠して秘密裏に地方官を観察、不正を暴く、いわば朝鮮版 “水戸黄門” “遠山の金さん” だ。身分は必ずしも高くなく、若い役人が任命されることも多かったようだ。暗行御史はいくつかの道具を携帯している。国王の「封書」(任命書) や「事目」(任務と派遣地の辞令) 、「鍮尺 (ちゅうしゃく)」(度量衡の正確さを判定するための道具) 、そしてドラマにもよく登場する丸い札「馬牌 (ばひ)」。ただこれは水戸黄門の「印籠」のような身分証とはいえない。駅で人馬を利用出来る札で、地方に出掛ける役人は誰でも持っていたという。朝鮮時代に出動した暗行御史は約700人を数える。ただ、18世紀になると汚職が御史にまでまん延し、計4回も地方に派遣されていた朴文秀のように、公明正大な判断を下したり、弱き者を味方する人物は少なかった。また英祖代の御史は、調査のため暗行御史のように身分を隠す場合もあったという説もある。

ドラマ『ヘチ』より。
民の救済に尽力した実務官
🏹 御史として地方の悪政を糾弾
朴文秀といえば、身分を隠し地方を行脚し地方役人の不正を摘発する「暗行御史 (アメンオサ)」として知られるが、彼が暗行御史に任命されたという記録はなく、同じく王命で派遣されるが身分を明かして活動する「御史 (オサ)」だったようだ。最初の派遣は1727年。公平な目で派遣地の嶺南 (ヨンナム) 地方 (慶尚道) を見て回り、英祖に不正官吏の処罰や地方の人材活用を求めた。
翌年、少論の李麟佐 (イ·インジャ) が乱を起こす。嶺南で首謀者の一人、鄭希亮 (チョウ·ヒリャン) とあっていた朴文秀は、謀反を事前に知っていたはずと疑われた。疑念を晴らすため、官軍を引き連れ嶺南に下り、同じ少論の反乱勢力をねじ伏せた。これを機に蕩平策 (タンビョンチェク) を推し進めたい英祖からますます引き立てられ、慶尚道観察使 (クァンチャルサ / 従2品) に抜てき。先の乱で散り散りになっていた農民を呼び戻して田畑を耕させ、安定させた。
その後も、干ばつや水害、重税に苦しむ人々を献身的に助けた、1731年には、湖西 (ホン) 地方 (忠清道) に派遣。干ばつが続き追い詰められた人々に自分の倉を開けて振る舞った。そんなことをしても焼け石に水だったが、地方役人や豪族にも私財を投げ打たせることが彼の狙いで、その通りになった。1741年、派遣されていた咸鏡道 (ハムギョンド) で飢饉の被害が大きく、慶尚道から1万石の穀物を運ばせ、苦しむ民を救った。こうした業績を称え、頌徳碑が建てられた。
🏹英祖の改革を積極的に推進
朴文秀は、英祖の改革政治も積極的に支持した。兵曹判書 (ピョンジョパンソ) のときには国王護衛軍の劣悪な待遇を向上させるための提案を行い、護衛軍改変 (龍虎営 / ヨンホヨン設置) の足がかりとなった。戸曹判書 (ホジョパンソ) 在籍時には財政改革をも進める。当時、人々を困らせていたのが、16歳から61歳の男子に課せられる役務だった。当時、死んだ人や子供まで台帳に載せ、税を課す不正がまかり通っていた (白骨徴布) 。朴文秀は国民の負担を減らすため、王室の収入源となっていた魚塩税を国の財源に還元し、役務な免除されていた両班からも税を集めることを提案。しかし両班から猛反発を食らう。文秀案の全ては実現されなかったが、「均役法」の実施で、役務免除の代わりに納める税は、一人当たり軍布2布から軍布1布となった。
そんな朴文秀には敵も多かった。しかし、窮地に追いやられるたびに英祖に救われる。英祖に信頼された朴文秀は、誕生したばかりの懿昭世孫 (ウインセソン) の師も任されたが、礼曹判書 (イェジョパンソ) だった1752年、懿昭世孫が3歳で急死。礼曹所属の内医院 (ネイウォン) での薬の調合に関する責任を追及され、済州島に流された。翌年刑を解かれ、右参賛 (ウチャムチャン / 正2品) という生涯最高の品階に昇進、63歳だった。そして3年後の1756年、66歳で死去。死後、英祖により領議政 (ヨンイジョン) に追贈された。
🏹朴文秀が合格祈願した七長寺 (チルチャンサ) .。
2度科挙に落ちた朴文秀が、七賢山 (チリョンサン / 京畿道安城市 / キョンギドアンソンシ) の七長寺・羅漢殿 (ナハンジョン) で祈ると、夢に解答が出てきて、3度目に無事合格したと伝わる。朴文秀の受験した1723年の科挙は定期試験ではなく、第20代景宗 (キョンジョン) が老論の粛清のち、新勢力を抜てきするために行われた特別試験だった。そのため受験者は少論だけ。合格者41名中26位でパスしている。七長寺には、今でも入試シーズンになると、合格祈願に多くの人が訪れる。また受験に向かう道すがらに食べるようにと「もち米のお菓子」を持たされたといわれ、これが現在、受験生に「くっつけ!」という意味で大福餅を贈る慣習の由来だとする説がある。