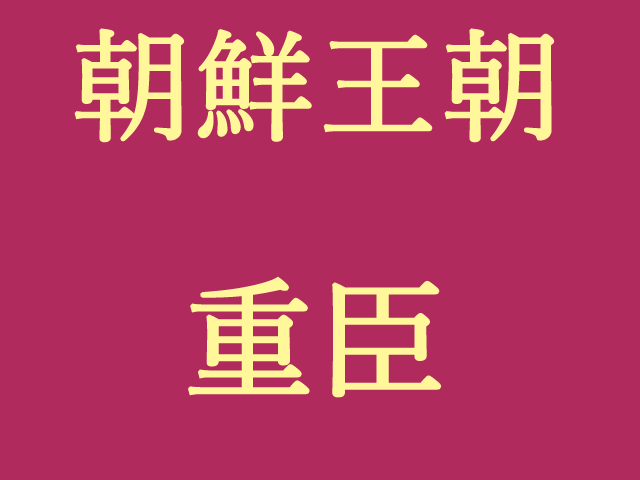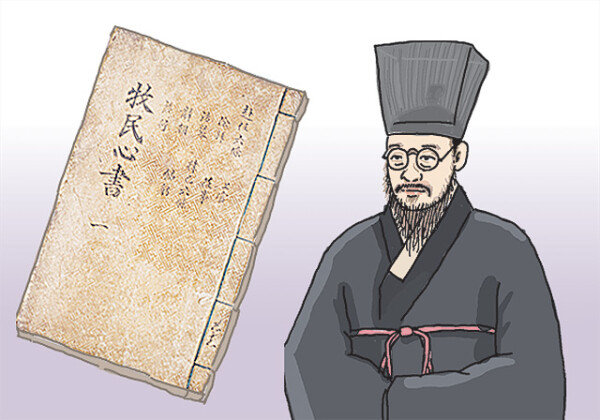水原華城を設計した朝鮮のダビンチ
■ 南人出身の天才少年
南人家系の四男として生まれる。
南人が勢力を失って以降、一家から久々に出仕した父が思悼世子 (サドセジャ) の死とともに辞職。父が故郷の京畿道広州 (キョンギドクァンジュ) に帰った年に生まれたため、幼名を帰農 (グィノン) と名付けられた。病弱だったが幼い頃から暗記力が抜群だった。
結婚した1776年、再び官僚に就いた父について漢陽 (ハニャン) に行き、実学を志すように。姉の夫・李承薫 (リ·スンフン) 、長兄嫁の弟・李ビョク (辟+木) を通じて、実学の大家・李ヨク (氵+翼) の親戚である李家煥 (リ·ガファン) と交流。亡き李ヨクを師と仰ぎ、彼の著書を熱心に読んだ。22歳で科挙の小科に合格、成均館 (ソンギュッカン) に入学して以降も、成績がすこぶる良く、早くから正祖 (チョンジョ) の目に留まっていたようだ。
23歳のとき、人生を左右する大きな出合いがあった。李ビョクから天主教 (カトリック) の書『天主実義』を勧められたのだ。開眼した彼は西学関連の本を読み漁り、天主教の思想とともに西洋の科学技術の知識を取り込んで行った。
1789年、28歳で分科に合格し、下級家臣から優れた人材を抜てきする「抄啓 (チョゲ) 文臣制度」により引き立てられる。失脚した洪国栄 (ホン·グギョン) の後を継ぐ正祖の右腕として、約10年にわたって活躍することになる。
歴史に残る丁若鏞の業績の一つが、水原華城の設計だ。1789年の漢江の船橋竣工の功績が認められ、1793年、正祖から水原の都市設計を任された。丁若鏞は、華城に西学の技術をふんだんに生かそうと考え、東西洋の美を融合させた最先端の城郭の設計図を1年がかりで作成。具体的な工事方法を記した報告書を出した (『城説』) .。また、スイス人テレンツの『奇器図説』を参照し、クレーンのような “挙重機” を
発明。その設計図と解説を『起重架図説』という本にまとめた。これにより、工期が10年から3年未満に大きく短縮されたといわれる。
■ 天主教弾圧により流刑に
哲学者、経済学者、建築家、著述家として、さまざまな方面で多大な功績を残した丁若鏞だが、南人という脆弱な基盤がゆえに、順風満帆に人生を歩めなかった。謀略により辞職と復職を繰り返した上に、正祖。急死で立場が急転。足を引っ張ったのは、天主教との関わりだった。唯一神を信仰する天主教では先祖崇拝である祭祀が認められないと分って以降、彼自身は身を引いていたようだが、天主教との結び付きを反対派に詰め寄られる。正祖生存時は地方に飛ばされるだけで済んだが、逝去後の1801年、天主教大弾圧でとどめを刺される。信者だった3番目の兄・丁若鍾 (チョン·ヤクチョン) の処刑に続いて、丁若鏞自身も、最も慕っていた2番目の兄・丁若銓 (チョン·ヤクチョン) と共に流刑生活を余儀なくされた。
■ 著書500冊を執筆し実学を集大成
官僚としては終わったが、流刑地での17年間を研究に費やした。後進の育成にも力を注ぎ、弟子と共に社会体制全面改革の主張をまとめ、実学研究を集大成する。「茶山 (タサン)」の号は、流刑中の1808年に移り住んだあずまやの裏にあった。全羅道康津 (チョルラドカンジン) の万徳山 (マンドクサン) の別名から取った。57歳で刑が解かれると故郷の広州に帰り、『経世遺表 (キョンセユビョ)』『牧民心書 (モンミンシンソ)』『欽欽心書 (フムフムシンソ)』の3部作をはじめとする500冊にも上る著書を改めて整理し、文集『与猶堂全集 (ヨユダンジョンソ)』を編さんした。
広州で75歳で没する。広州には彼の墓地や生家が保存され、隣接地に実学博物館が建っている。
よりお借りして引用させて頂きました。