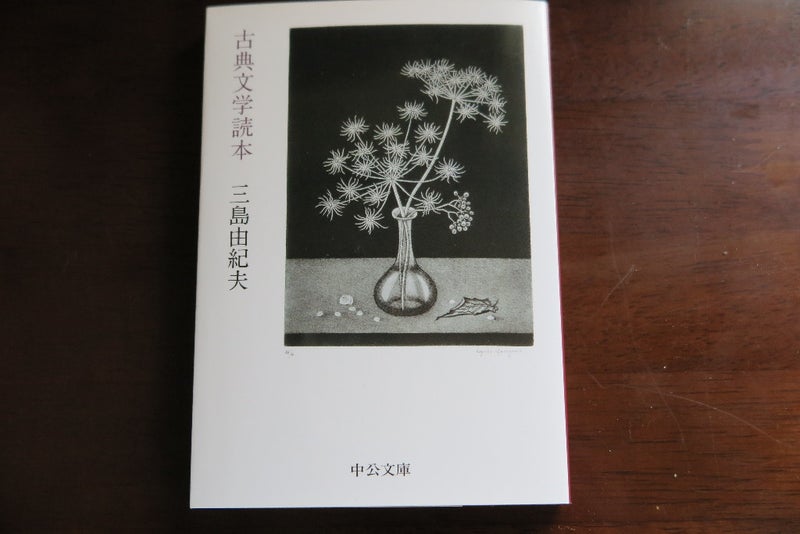
『日本文学小史』の第6章「源氏物語」で三島は語っています。
「汗牛充棟もただならぬ源語の研究に伍して、五十四帖すべてを論じようとしたところで、甲斐はあるまい。私はただ、源氏物語から、文化と物語の正午を跡づければよいのである」
まず「汗牛充棟」で躓きます。「重さが牛が汗をかくほど多く、その量が棟につかえるほど」という源氏物語の研究書の多いことをいっています。そして「文化と物語の正午」の「正午」とはたぶん「中間」ということで理解してよいのではないでしょうか。ちょっと理解しずらいかもしれませんが(私の解釈が自分寄り過ぎますが)まあ深く考えないで先に進みましょう。
この『日本文学小史』は難しい表現が多く一度では理解できないのです。何度も読み直す必要があるとはこのことです。また他の章に比べて走り書きといったのは、三島が「源氏物語」に深入りすると、当時書いていた『豊饒の海』を中断しなければならない事態に落ち込む危険があったのではないかと私は判断しています。
すでに「源氏物語」の現代語訳は谷崎潤一郎の名訳があり、さらに紫式部の描く「もののあはれ」を多くの研究者が指摘しているので、それを評しても仕方ないと考え、「花の宴」と「胡蝶」という人があまり喜ばず、また敬重もしない二つの巻を語ることにしたといっています。
「花の宴」は光源氏二十歳で社交生活が絶頂の時であり、「胡蝶」では三十六歳の彼が太政大臣の位につき、この世の栄華の絶頂の「好き心」を描き、光源氏の生涯でもっとも悩みのない快楽をそれぞれ語っているらしい。
谷崎「源氏」の第1巻途中までしか読んでいない私には「らしい」としか言いようがないのです。
三島は「このような時のつかもまの静止の頂点なしに、源氏物語という長大な物語は成立しなかった」として、物語のほどよいところに「青春さかりの美の一夕と、栄華のきわみの官能の一夕」をちりばめ、源氏物語の制作の深い動機を成していたかも知れぬといっています。
それは光源氏が「美貌の徳に恵まれた快楽の天才である」ことをこの物語を読むとき片時も忘れてはならないのです。それは紫式部が、つねにこの世に稀な美貌の持ち主である光源氏の特権として認めていると見ています。それは「源氏に委せておけば、どんな俗事も醜聞も、たちどころに美と優雅と憂愁に姿を変える」「感情と生活の錬金術」を紫式部が、「自らの文化意思とし矜持」としていたものであると語っています。
「源氏物語」は谷崎の他に与謝野晶子、田辺聖子、瀬戸内寂聴といろいろ解釈されて出版されています。私は三島が「源氏」に深入りして、もし現代語訳を試みてくれたなら、45歳で自死することはなかったろうと考えます。しかしそれは彼の任ではなかったのでしょう。汗牛充棟のものには手を出さないのが三島由紀夫の生き方なのですから。
追記:きのうは慌ただしい一日でした。身体は疲れていますが頭が冴えて眠れません。たぶん5時にはハナに起こされるでしょう。そんな時にはオンザ・ロックで起きて居ましょう。飲み過ぎない程度に!